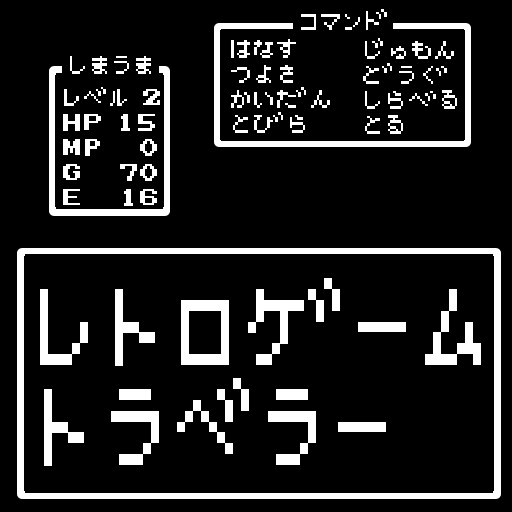この世の終わりのスイッチ
2章 核ミサイル300連射
スイッチを交番に預けた後、それから2週間が経過した。 世の中はまさに天下泰平。 さまざまな事件は発生しているものの、おおむね日本は平和であった。 そんな安穏を貪る日々の、ある夜のことだった。 僕が2階の自室でダラダラと過ごしている時。 「鱒乃助~、学校の人からだとか、電話が来ているけど」 リビングの方から母さんの声がした。 誰だろう? 柚子かな? いや、違う、違うな。柚子なら、電話をかけてくることは無い。 柚子なら、直接言いに来るだろう。 だとすると、一縷だろうか? とりあえず、一縷から愛の告白だったらどうしようと思いつつ、僕は返事した。 「わかったー、部屋の子機につないでー」 ピポ ポシュ とか、そんな電子音が鳴り、僕はその電話に出る。 「もしもし、私、梨木ミルです。鱒乃助さんでしょうか?」 あれ、ミルだ。 「はい、鱒乃助です。どうかしましたか?」 「ええ・・・少し話したいことがありまして、夜分遅くに申し訳ありません」 「いやまあ・・・別にいいけど、それで話ってなに?」 「電話でははばかられます。すみませんが、近くの公園までご足労願えませんか?」 「え? 近くの公園って・・・もしかして、今公園にいるの?」 「はい、あのスイッチのことで詳しくお話しておきたいと思いまして」 スイッチのことで話したい事がある? それに電話で話せないようなこととはどういうことだろう。 いや、違う。違うな。 もしやこれは、スイッチの話にかこつけて、彼女は僕に愛の告白をするつもりではないのか?! 発生する可能性が極めて低いイベントかもしれないが、攻略フラグが立ってしまったものは 仕方がない。 このまま全キャラ(+柚子と一縷)の攻略フラグが立てば、ハーレムエンドも夢では無いかも しれない。 ふふふ・・・いや、モテる男はつらいねぇ。 僕はそう考えて即座に返事をした。 「うん、分かった行くよ」 「分かりました、待ってます」 電話はそこで切れた。 僕は家族に外出を告げると、急ぎ足で近くの公園へと向かった。 約束の場所にたどり着くと、ミルが待っていた。 暗闇の中だからだろうか、あのキレイな彼女の黒髪が、 なんだか不気味なものに見えてしまった。 「時間にルーズな人だと、岸本さんから聞いていたのだけど、それほどでも 無いみたいですね」 「柚子から?」 「ええ、そうです」 どうせ柚子のことだ、あまり良い様には喋っていないだろう。 「まぁ、どんな内容のおしゃべりだったのかは、あなたのご想像にお任せしますが・・・ そうそう、あまり時間をとっても仕方がないですわね。本題に入りましょうか?」 ミルの髪の毛が、ブワッと夜風にまかれた。 「本題・・・スイッチのことだね」 「そうです鱒乃助さん、あなたはあのスイッチに関して、どこまでご存知かしら?」 「どこまでって言ったって、正直、何も知らないに等しいよ」 「分かりました、それでは順を追ってご説明いたしましょう」 夜風が強くなってきた。 ミルの黒髪がザワザワと風に揺れる。 鼻にかかったらクシャミの一つも出そうだ。 「茶化さない」 「テレパシー?」 「・・・鱒乃助さんは、考えている事が物凄く分かりやすいです。 どういうわけか、あなたの心は、まるで文章を読んでいるかのように、 簡単に読めるときがあります」 「・・・(超常現象だろうか)」 そういや、なにげに最近、不思議と考えている事が周囲に漏れていることがある。 「さて、そう、あのスイッチは確かにこの世界を、つまり私たちが生きているこの世界を 消滅させる為の、いえ、消滅させる能力のあるスイッチです。 その驚くべき能力に関しては、ほぼ疑いようの無いことと思います」 確かに、なんらかの異常な力を持った物体であることは確かだ。 「プチ破滅→○ テスト破滅→@ その双方ともに、そのスイッチを押してしまえば恐ろしい 結果が生み出されます。あの、奇妙なクレーターを残して消滅した駅舎のように」 「それは見たよ」 「そうです。見ていられます。私も見ました。 スイッチの持つ力は事実です。 しかし、未だに、確実に、スイッチの最期の機能は試されてはいません」 「最期の機能?」 「この世界の終末、破滅、消滅、それをもたらす機能は、実行されてはいないはずです。 確かに今、現に、この世界はここに存在しているのですから」 「まあね、そりゃそうだ」 「それでは、最期の機能のスイッチは、世界の破滅のスイッチは、まだ誰も押していないのか? いえ、それは違う。破滅のスイッチ『破滅→◎』は、既にかなりの人数が押しているのです。 少なくとも、私は押しました。世界を破滅させることを選択しました」 そう言い切ると、ミルはハンドバックからあの赤い『破滅スイッチ』を取り出した。 「これはもう押された後のスイッチです。スイッチは、押された後、戻ることはありません。 世界の破滅は、選択されたはずなのです」 「それでは、なぜ、世界は終わらない?」 「ここからは私の推測ですが、おそらくこのスイッチは『票』なのです」 「多数決のような?」 「そう、世界を破滅させるか否かの、票を取っているスイッチなのです。 ですが、多数決とは違います。 このスイッチの裏には数字が刻印されています、 この数字の個数だけ、このスイッチはある。 わたしはそう考えています」 「ふむ」 「今現在」 ミルは箱を裏返しにして、数字の刻印を見せた。 「票の行方は、256/299。私の推測どおりならば、世界を消滅させるまで、 あと43票です」 「え?」 僕は驚いて聞き返した。 「その数字の意味は、もしかして」 「はい、変化しています。・・・ふふ、ちょうどいいところに、もう一票増えました。 257/299、世界の終末まで、あと42票です」 「・・・止めることはできないの?」 「それは私にもわかりません。けど、最後の一票でも残っている限り、 おそらく世界の消滅は発生しないと思います。 まぁ、私は止める気はありませんけど」 「どうしてさ」 「鱒乃助さんは、この現在の世界が、存在する価値がある世界だと思っておられますか?」 「そんなこと聞かれても、考えたことも無いよ」 「そうなのですか? 私は考えました。このスイッチを拾う前から考えていました。 拾った後はより深く考えました」 ミルは、力を込めて語り始めた。 「市場経済の行き詰まり、政治システムの破綻、環境破壊、終わらない地域紛争、 そしてなにより、この緊急の危機に対して、何の手も打たない圧倒的多数の人間たち」 彼女の演説は次第に熱を帯び始めた。 今や身振り手振りも加わっている。 「この世界を存続させるか、消滅させるかの選択が、今まさに委ねられたのです! 私は1人の『光の子』として、この暗闇の世界を、終末へと誘い、新たなる世界の到来を 願ったのです。いえ、新たなる世界を到来させることを誓ったのです!」 「はい?」 なんだか、話が変な方向に進んできたような。 「鱒乃助さんは分からないでしょうが、この世界は本来『光の子』たる我ら 『クロノスブライト』が、『闇の子』たる・・・」 なんか、分けわかんない、奇妙な方向に演説が軌道変更してしまった。 ミルは、その妙な終末思想に凝っているらしい。 しかも誰かの受け売りと言うわけではなく、自分オリジナルの教義?らしい。 この演説は30分ほど続くので、要点だけを抽出するが、 ミルとお友達=『光の子』 その他の人=『闇の子』 光の子 vs 闇の子 →最終戦争勃発 勝利条件→全ての破滅のスイッチを押せ スイッチは宇宙創造神 クロノスブライター が、地球に与えた物。 らしい。 ・・・ふーん。 「ぜぇぜぇぜえ・・・、と、言うわけなのよ、わかっていただけたかしら?」 若干、ミルの声がかすれている。お疲れ様。 「うん、まぁ何となく」 「何となくですか」 「うん、それじゃ、そろそろ帰るよ、そろそろパソコンのレジストリの整理と、 ハードディスクのデフラグをしなくちゃならない時間なんだ」 そのヘンテコリンな終末思想さえ持っていなければ、彼女もただの可愛い女の子なのだが。 ああ、こんな人だとは思わなかったよ。 僕は引き止める彼女の言葉を振り切り、競歩の如き速度で家に帰った。 その次の日の昼下がり。 僕と柚子は、『買い物するなら七番街』 という垂れ幕がかかっている駅前の商店街にやってきた。 柚子は携帯電話の契約会社を変更したいらしい。 僕は最新のパソコンゲーム『鬼道禅師ガンダーラ』を買うのが目的だ。 「で? あんたが欲しいその『きどうぜんじガンダラ』とか言うゲームは どういうやつなの?」 実は、柚子はパソコンゲームに結構詳しい。 詳しいのだが、実際にはどんなゲームをやっているのかはあまり教えてくれない。 「えーと、確か・・・巨大ロボットに乗った禅寺の和尚さんが、悟りを開いて 宇宙精神と交感するっていうアドベンチャーゲームだよ」 「どマイナーそうね」 「そうでも無いよ。同人ゲームと言っても有名メーカーの元技術者が開発してるんだ。 使っているゲーム開発用の機材もプログラムも大手メーカーの物と同じ物らしくて、 3D画像のポリゴンが、もうすごいリアルなんだ」 「・・・そ、そう」 「ヘッドセットディスプレイなんかつけた日には・・・うん、ヘッドセットディスプレイって 言うのはヘルメットみたいな奴で、ゴーグルのところに画面が映し出されるヤツさ。 それをつけたら、本当に現実と見間違うんじゃないかってぐらいにリアルなんだ」 「え、ええ、分かったわ」 「分かってくれた? いやいや、うれしいねぇ。 この技術の進歩の喜びを分かち合えるなんて」 そんなことを言いながら、僕らは商店街に入った。 「そう言えば、一縷はどうして来ないんだっけ?」 「マス、あんた忘れたの? チルは今日、友達と映画を見る約束だったのよ。 確か、ええっと・・・なんて言ったっけ」 「・・・? そう言えばなんだっけ、忘れちゃった」 先日、僕と柚子が街に買い物に行くという話しをしていた時、一縷も一緒に行くかと 誘ったのだが、一縷は断った。 別の友人との映画鑑賞を優先したらしい。 映画を見た後、合流しようかとも言っていたのだが、一縷達の行き先のシネマコンプレックスが 4駅も離れていた為、あえなく断念したのだった。 そう言えば、その間の3駅の名前はなんだっけ? ど忘れしてしまった。 「いらっしゃいませー」 店員さんの掛け声と共に、僕達は複合商業施設に突入した。 「さて、上に行かなきゃならないね、エスカレーターを使おうか」 僕が言った時だった。 僕の横にいた柚子が、僕の右腕を キュッ と握り締めた。 その握り方はとても強くて、なんだかとても情熱的なものに感じられた。 柚子、キミはそんなに僕のことを・・・。 精一杯の甘い笑顔を向けて上げようと、柚子の方を見た。 そしたら柚子は、顔を真っ青にして、ガタガタと震えていた。 「な、なに、アレ」 「アレって?」 僕は柚子の視線を追って、その方向を見た。 ・・・売り場のフロアに、奇妙な段差がある。 まるで、規格の合わない巨大な棚を並べたみたいに、ビルの床がずれている。 それだけではない。 そもそも、このビルは、それほど広い建物じゃない。 なのに、広い、向こうまで随分ある。 まるで何棟かのビルが、いきなり何も考えずに壁をぶち抜いて、くっつけられた様な有様だ。 窓から外を見る。 窓の外には駅舎があった。 そこには、4駅向こうの駅の名前が書かれていた。 「ど、どうなってるの? マス・・・」 「いや、どうなってるって、・・・無謀な都市計画の産物かな」 「じょ、冗談言ってる場合じゃないでしょ?」 だが、奇妙なことはもう一点あった。 僕達以外の人間は、平然として、この状況を受け入れている様であった。 いや、もっと的確に言うと、この状況を、まったく認識していないように見えた。 ただ立ち呆けるしかないなか、僕らは遥か彼方に一縷らしき人影を見た。 50mほど先がシネマコンプレックスとこのビルが一体化?しており、そこから吐き出された 人の群れの中に、一縷がいたのだ。 僕は試しに一縷に声をかけてみた。 「おーい、一縷~」 呼びかけの後、一瞬、間を置いて、一縷が反応した。 「おーす。サマノスケ、岸本」 一縷は友達に別れを告げると、ビルの床の段差をいくつか乗り越えて、こっちにやってきた。 「おふたりさんもお揃いでー」 なんだか、一縷はいつも通りだ。この異常な光景は、一縷には見えていないのだろうか? 「チ、チル、これ、コレ、いったい、いったいどうなってるの?」 カタカタと小さく震えながら、柚子はなんとか言葉を放った。 いやー、今日の柚子は可愛いなー。 ・・・そんなことを言っている場合ではないかな? 「いや、その、なんて言うか、無謀な都市計画のズサンな結果ってやつ?」 「マ、マスと同じこと言わないでよー! どうしてこう、この2人は変に息があってるって言うか、変人コンビって言うか・・・ あー! もう。 これじゃ恐がっているこっちの方が変みたいじゃない!」 「ごめんごめん。 正直アタシも驚いたんだけど、友達はなんとも思っていない風だったし、 てっきりアタシの方がおかしくなったのかと思って、考えないことにしたんだ」 「じゃ、チルにも見えてるわけね?」 「そりゃね。こう、ビルとビルが無茶苦茶に合体しているとね」 そうだ。 まさにビルとビルがメチャクチャに合体しているのだ。 いや、何かが違うような・・・。 そうだ、ビルとビルが合体していると言うよりも、 建物と建物の間の巨大な空間が『消滅』してしまっているのだ。 空間の消滅と言うのはなんとなく実感が湧かないが、 『真空』ではなく、『時空レベルでの空間消失』が発生したとでもいう感じだ。 しかし・・・シュールな光景だ。 ダリだって、ここまでのシュールレアリズム的光景を見たら感動するに違いない。 「な、何がどうなったら、こんな物、出来るって言うのよ。 早く出ましょう、気味が悪いわ」 とにかく、柚子が脅えきってしまってどうしようもないので、 僕らは一旦、外に出て近くの公園に行くことにした。 同時刻、大学構内のとあるサークル棟 手書きの『クロノスブライト本部』という看板がかかった六畳一間で、 ミルはその小柄な身体から、大量の不満のオーラを発していた。 「だから、どうしてスイッチを受け取れないのです! 僕が落とした物ですって 言えば、すぐにでも引き取れるのではないのですか!?」 携帯電話が壊れるのではないかと思えるぐらいの大声。 「すみません、ミルさん。なんか怪しいやつだと思われたみたいで、 落とした場所とか、無くした状態とか聞かれて、しどろもどろに答えてるうちに なんか相手の様子が険しくなってきちゃって」 「・・・もう少し、もう少しなのです。今もネットオークションで1個落札したのです。 ・・・ええ、ええ・・・10万円です。なんですか、高いですって?! 何を言っているのです! こんな貴重な機会はもう来ないかもしれないのです! あなたたちは、とっととそのスイッチを持って帰ってくればいいのです!」 「で・・・でもどうやって・・・」 「力ずくでも、盗ってらっしゃい!」 ピッ ミルは乱暴に携帯を切った。 ちょうど時間は昼の12時。 公園はランチタイムのOLさんや、近所の学生さんで混雑していた。 僕らは空いているベンチを見つけると、そこに陣取ることにした。 「ほら、ジュースでも飲んで落ち着けよ岸本」 一縷が近くの自動販売機でスポーツドリンクを買って来た。 プルタブを開けて柚子に差し出すと、柚子はおずおずと飲み始めた。 「んっんっんっ・・・ぷあ」 「岸本、落ち着いたか?」 「ごめん、なんとか落ち着いたわ」 柚子の顔色はだいぶ良くなっていた。 「しかし、結局、ありゃなんなんだ?」 一縷が首をかしげる。 「あんなにメチャクチャな作りのビルがあったら、とっとと崩壊していてもおかしくないのに、 それなのに、あの合体ビルは平然と建っているなんてよ」 うーん。と、一縷はますます首を捻る。 「そうだね」 僕も相づちを打つ。 「あれではビルがおかしいだけじゃない。物理現象としてもメチャクチャだ」 「そうよ、そこよ」 柚子が少し復活してきたようで、会話に混ざってきた。 「そうだ! チル、あなた携帯電話、使える?」 「ああ、あるけど」 「ちょ、ちょっと貸して」 柚子は一縷の手から携帯電話を分捕ると、カチカチと凄い勢いで 操作を始めた。 「お、おいおい、岸本、何をしたいんだ?」 一縷のそんな言葉も柚子の耳には届いていないのか、 柚子は一心不乱に携帯電話を操作している。 そして3分後。 「そんな」 という言葉を発して、柚子は力無く携帯電話をヒザの上に置いた。 「なんだってんだ? 少しは説明してくれ」 一縷は自分の携帯電話を柚子から取り返すと、携帯電話の画面を見た。 そして、ぎょっとした顔になった。 「お、おいおい。冗談だろ?」 携帯電話の画面は、街のナビゲーション画面だった。 その街のナビゲーションシステムが映し出す街の姿は、明らかに狂っていた。 街の何ヶ所かで、街並みが『時空ごと』消滅していた。 アーケード街の三丁目の隣が十丁目なのはさすがに変だ。 有ったはずの区画が、まるで最初から無かったかのようになっていた。 とりあえず、これからどうしようかと考えた。 考えたのは良いのだが、僕には何の案も浮かばなかった。 「下手な考え休むに似たりってね。わたしに良い考えがあるわ」 柚子はいつもの調子を取り戻していた。 「どうするってんだ?」 一縷が好奇心でいっぱいといった感じの顔になる。 「とにかく、あのスイッチよ。 私はどうしてもアレが気になるわ」 それから一時間後、僕らはスイッチを預けた交番にやって来た。 「こんにちわー。ちょっといいですかー」 一縷が気楽に交番に入っていく。 「一縷は慣れた感じで交番に入っていくね」 「あら、マスは知らなかったの? 一縷ってば高校時代に変質者を 2回も捕まえているのよ? 確か、それで一昨年、警察から金一封も送られたハズだけど。 新聞にも載ったはずだわ? 『女子高生 変質者に華麗な一本』とか」 なるほど、一本ということは柔道かな? 一縷には変なことはしないでおこう。 「おーい、・・・あれ、サマノスケー、岸本ー、中には誰も居ないみたいだよ」 交番の中には誰も居なかった。 「誰も居ないって?」 「そうね、お巡りさん、どこかに行っているのかしら」 僕達3人は、ゾロゾロと交番の中に入った。 ガサッ ・・・? 何か物音がしたけど・・・奥のほうから ガサッ ガサガサッ やっぱり何か物音がする。 「あれ、お巡りさんいるんじゃん、おーい、おまわりさーん」 一縷がブンブンと手を振りながら奥の方に入っていった。 その瞬間だった。 ヤバッ とか 引き上げろ とか 急げ とか、そういう声があのガサガサ音と共に 聞こえてきた。 「うわああぁぁぁ?!」 一縷の悲鳴が響いた。 交番の奥から、3人ほどの若い男たちが、いきなり飛び出してきた! 男達は我先にと出口へと殺到し、その通路を塞いでいた僕達に向かって突進してきた。 うわ! とか キャア! とか、ドカドカ!とか。そういう絶叫や音が交番内に響いた。 僕は最初に飛び出してきた目出し帽の男に弾き飛ばされた。 その衝撃で横にあった机に背中を猛烈に打ちつけてしまった。 かなり、痛かった。 2人目の男が柚子を両手で押しのけた。 柚子は壁のほうに飛ばされ、背中を打ちつけて尻餅をついたみたいだ。 3人目の男が、乱暴に一縷を押しのけようとした。 一縷はその瞬間、僕が見たことも無いような鋭い眼光を放つと、 瞬時に相手の腕を捉えた。 そして見事な! 見事な・・・えーと、良くわかんない極め技で男の腕を捻り上げた。 「いて、いてててててぇぇ!! いてぇ!」 「綾手捕り天秤(あやてとりてんびん)、合気道の技さ。 おまえ動かない方がいいよ、下手に動くと腕の関節外れるから」 一縷が軽く男の腕を持ち上げる。 「いてぇええ! わかった、わわ、わかった」 「いったーい・・・まったく、なんだってのよもう・・・」 ぶつくさと言いながら、柚子が起き上がってきた。 何とか僕も立ち上がる。 辺りをキョロキョロと見渡したが、残りの男たち2人もういない。 この男を見捨てて逃げたようだ。 「あたた・・・酷い目にあった」 「もう、マスったら、イザって時に役に立たないんだから」 「いえ、その、すいません」 だって僕は格闘技なんてやってないし。 不意打ちだったし。 今のタイミングでなかったら、きっと僕の必殺技『ガンダーラハンマー』が炸裂してたし。 と、心の中でありえない反論をしておいた。 そんなこんなしていると、交番の奥から 人のうめき声が聞こえてきた。 「あ、お巡りさんじゃないかな」 柚子が奥に入っていく、多少薄暗いその部屋の電灯を点けると、 畳の上に老駐在が横たわっていた。 「あいたたた・・・やれやれ、酷い目にあったわい、・・・いや、こりゃすみません、お嬢さん。 ああ、あいつらはどうしましたか」 腰を打ったのだろうか、老駐在が腰を擦りながら出てきた。 「お巡りさん、こいつどうしよう?」 技を極めながらも、身動きできない一縷が老駐在に助けを求めた。 「やれやれ、この悪たれめ・・・いや、助かりました、ご協力感謝します。 とりあえず、暴行と公務執行妨害の現行犯ですしな」 哀れ、男は捕まってしまった。 自業自得なんだけど。 それにしても、捕まった男は開放された後も、ずっと腕の関節を痛がっていた。 一縷が少し、強めに技をかけたらしい。 「だって、あいつ、ドサクサまぎれにアタシのおっぱい、思いっきり掴んだんだぜ?!」 だ、そうである。 その後、ちょこちょことやることもあって、時間は夕方の5時になってしまった。 一縷大活躍の大捕り物ののち、僕ら3人は老駐在の感謝の言葉に送られて、 この交番を去る・・・。 「去っちゃいけないでしょ!」 柚子が思いっきりツッコミを入れた。見事なタイミングだった。 「私達はあのスイッチを探しにやって来たのでしょう、いけない、早く聞かなくちゃ」 僕ら3人は、慌てて交番の老駐在を捕まえて、あの時のスイッチについて聞き出した。 すると老駐在は、 「うむ、スイッチか? おお、あの悪ガキどもそれを取りに来たようだが、 スイッチなら、ワシの机の鍵がかかっている引き出しにあるよ」 彼らは、あのスイッチを奪いに来たのか。 「あのー、それでですね、お願いしたい事があるんですけど」 僕が切り出した。 「あのスイッチ、少しの間必要になったんです・・・しばらく貸して頂けませんか?」 「ふむ? あのスイッチを今度は貸して欲しい?」 老駐在が怪訝な顔をする。 「はい」 「・・・う~む」 老駐在はしばし考え込んだ上で、首を縦に振った。 「ま、いいわい、貸してやろう」 そう言うと、老駐在はその節くれだった指で腰から鍵束を繰り出し、机の引き出しを開けた。 「・・・ちょっと、お巡りさん、いいんですか?」 柚子が心配そうに尋ねる。 そりゃそうだろう。なんせ落し物を届けに来たというやつが、しばらくしてから、 その届け物を必要になったから貸してくれと言いに来ているのだ。 「なに、いいって事よ。必要な物なんじゃから、必要な者が持っていれば良い。 なにより、ワシは信用できる人間と信用できない人間の差ぐらい、見分けられるつもりじゃよ。 貸して欲しいって言うんだから、返す気があるんじゃろうしな」 「ほれ若いの」 老駐在は、引き出しからスイッチを取り出すと、僕に手渡した。 「大事にしなさい」 「はい、ありがとうございます」 その頃、一縷は何を思ったのか、護送を待つ若い男(めんどくさいので、犯人Cと呼ぼう) の所まで、つかつかと歩いていっていた。 僕らはそれを見てはいなかったのだけど。 「おい、おまえ」 一縷が聞いたことも無いようなドスの利いた声を出す。 「ところでおまえ、誰に頼まれた?」 「ふっ」 しかし、犯人Cは、そんな一縷を鼻で笑った。 「オレが喋るとでも?」 「ああ、おまえはすぐに喋りたくなるさ」 そういうと、一縷は犯人Cの後ろに立ち、何かした。 「いっでぇー! 痛い、痛い! 痛いです!」 「何を言ってるんだい? ふふふ」 一縷は暗い笑いを浮かべつつ、何かをしている。 僕らはそこで、ようやく一縷の行動に気がついた。 「・・・ありゃ、わしは止めたほうがいいのかな」 老駐在は、そう言いつつも止める気は無いようだ。 「ほらほら、ほら、・・・痛いの好きかい?」 「好きじゃないです! 嫌いです! 喋ります、いえ、話させていただきます!」 一縷は情報を引き出した。いや、引きずり出した。 つまり。 この人と、他の人たちは、クロノスブライトとか言うミルが運営するオカルトサークルの 構成員らしい。(彼ら曰く宗教団体。しかし、認可は受けていないらしい) ミルは、いろいろな方法で、あのスイッチを集めているらしい。 今回は窃盗まがいのことをしてしまったが、いつもならこんなことはしないらしい。 ミルが、こんなことをさせている・・・? 「梨木さん、まだおかしなことしてるんだ・・・」 柚子が頭を抱えた。 柚子はミルのことを知っているのか? そう言えば、ミルも柚子のことを知っている様子だったが。 「彼女とは、高校時代に同じクラスだったのよ」 交番の近くの公園に陣取った僕らは、ベンチに腰掛けて 柚子の話に聞き入っていた。 「梨木さんは学校ではちょっとした有名人だったわ。 彼女、学校のオカルト研究会に所属していてね」 「そんなサークルが、実在する学校があるんだ!」 なぜか一縷が喜んでいる。 「オカルト研究会は結成から長い間、たんなる研究会だったらしいわ。 別におかしな儀式とかをしているわけではなくて、ただ単純にオカルト的 知識や資料を集めて、時々発表するだけのサークルだった。 あたしも覚えているのは、高校一年の時の学校祭の展示資料ね。 あの時のサークルの部長さんは、オカルト否定論者だったみたいで、 展示資料も様々な怪奇現象を否定的に捉えているものばかりだった」 「うーん、そうか、つまんないな」 一縷は本当に残念そうにアクビをし、両手を揃えて胸をそらし、伸びの体操を繰り返す。 ・・・うーん、胸が強調される。本当にEなんだろうか・・・。 いや、今はそんなところに気をとられている場合では無いな、柚子の話に集中しよう。 「梨木さんが入ってから、サークル活動は随分変わったみたい。 彼女が2年生になった頃、3年生の人たちはみんな辞めちゃったの、 梨木さんが求めているものに、ついて行けなくなったって言ってた」 僕は身を乗り出して柚子の話を聞く。 「その、求めているものって?」 「梨木さん、奇妙な終末思想に凝ってて・・・あ、終末思想って言うのは、世界の破滅が近いぞー とかやる新興宗教には大体あるアレね。 うん、簡単に言うと梨木さんは本格的なオカルトとかを求めていて、他の人たちは 遊びとしての、娯楽としてのオカルトをやっていたかったのよ」 今度は一縷が身を乗り出した。 「娯楽としてのオカルトなんてあるのか?」 「あることはあるわよ、例えば怪談話とか、オカルトホラーの映画とか・・・、 幽霊否定論者でも、怪談話そのものを否定するわけではないでしょ? つまり、1つのフィクションとして、オカルティックな世界観を楽しみたかった人たちと、 梨木さんは一線を画していたのよ」 「で?」 一縷が聞き返す。 「その梨木ってやつの終末思想やらと、あのスイッチとが、どうつながるんだ?」 「梨木さんは本当に、近いうちに世界が破滅すると思っていたみたいなの、 それが、彼女の思考の理論的結論なのか、それともただの願望なのか・・・ それは分からない。 もしかしたら、その世界の破滅とやらは、彼女の『こうなって欲しい』という 願望なのかもしれないわね。 梨木さんは、今まさに世界の破滅のスイッチとやらを集めて全部押そうとしているみたいだし」 同時刻、ニューヨーク 、マンハッタンの国連本部 全ては明らかになった。 アメリカの研究機関の情報、EUの研究機関の情報、そして国連に協力してくれる 多くの科学者の協力により、ついにこの『破滅スイッチ』の能力が白日の下に晒されることに なった。 しかしなんと恐ろしいスイッチか。 このスイッチの力は戦略核兵器や生物兵器の破壊力を明らかに上回っていた。 度重なる実験が示す驚愕のデータの数々は、この世界そのものの有り様を 根本から覆す物に違いなかった。 このスイッチをいかにすべきか?! 人類最高の英知達が練りに練った作戦シミュレーションのパターンは2000通り以上にも達し、 さらなる数ヶ月の討議を重ねて、問題解決への最高のアプローチが導き出された。 そして、世界の意志は1つにまとまった。 この恐怖のスイッチに対して、全人類は一丸となって戦わなくてはならないのだ・・・! スイッチを集めんとする国家に対し、世界は最終的な結論を下さなければならないのだ! 今、この瞬間、世界中から集まってきた指導者たちが、 涙を、ただ涙を流し続けていた。 「やらねばならん、やらねばならんのだ・・・! 回避するのだ。全人類の存亡をかけて!」 国連事務総長が涙の演説を終えた。 人々が、拍手した、そして固く、固く握手を交えた。 「やりましょう」 「やりましょう」 「いまこそ動く時だ、全人類の未来の為に・・・!」 なんということだろう、この国連という場において、今の今までこれほどに 全世界の国々が一致団結した事があっただろうか? 今後数百年間、いや、数千年間、人々は今日という日を思い起こさぬことは無いだろう。 「うむ、それでは全世界の国々の方々に申し上げます!」 「国連決議が成り立ちました! 全世界の軍隊、警察、その他の諸機関全ては・・・」 国連事務総長が声を張り上げた。 「『破滅スイッチ』を独占しようとする日本国に対して! 全国連加盟国は、 作戦名1092。コードネーム『黒の結果』を実行します」 なお、この場に日本の大使は存在しない。 問答無用で締め出されている。 日本の何者かが、破滅スイッチを独占しようとしている。 それだけは、阻止しなければならない。 世界の平和のため、例え日本という国を消滅させてでも・・・! 全世界の軍隊が、日本攻撃に向かって出発した。 作戦名1092 コードネーム『黒の結果』 『破滅スイッチ』の独占と、その利用を目論む組織が出現した場合に発動される世界規模での 軍事作戦。 なお、作戦実行時にスイッチの所有者が、自爆的なスイッチの乱用を起こす可能性が高いと 考えられるため、作戦の決行、及び遂行は、極限までの隠匿性と速効性が求められる。 また、この作戦は大まかに言って4段階に分かれている。 第一段階 ステルス兵器による迅速な敵組織の完全包囲と、 敵対するであろう諸機関への徹底した電子戦の活用。 (情報的奇襲、あるいは情報的包囲を行う) 第二段階 敵対勢力の指揮系統の混乱を見極めたうえで、 出来うる限りの攻撃力で、第一撃をみまう。 この攻撃には核兵器の使用が優先される。 第三段階 『破滅スイッチ』は核攻撃程度では傷の1つもつかないので、 今度は対核装備を施した特殊部隊によるスイッチの回収が行われる。 なお、今回の作戦では、スイッチの多くが関東地方のとある大学 を拠点に収集されていると考えられるため、この学校が第一目標となる。 (インターネットを利用した、スイッチの取引が確認されている) 第四段階 『破滅スイッチ』の完全投棄。 宇宙空間に破棄する計画が検討されている。