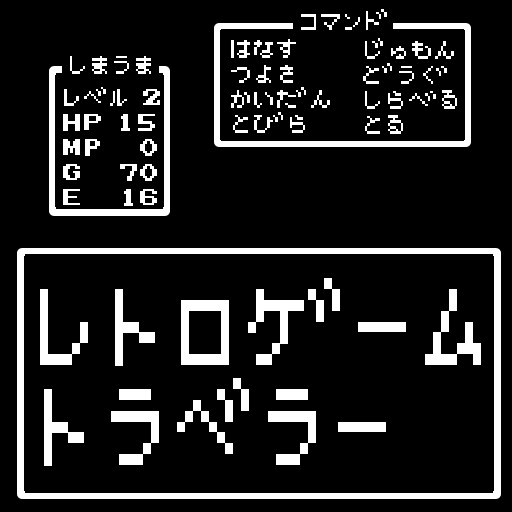この世の終わりのスイッチ
1章 スイッチと僕
この作品は、フィクションです。 作品内に登場する全ての事象は、実在のものとは一切関係ありません。 ようこそデミウルゴスへ 現在デミウルゴスは観察実験シミュレーションNo.299を 処理しています。 現在、シミュレーションNo.299は適切に運用されています。 現在、シミュレーションNo.299内部にて、危険度92%の 危険因子が発生しています。 AI.251は、以下のシミュレーションの続行が、このままでは 不可能になる可能性が極めて高いと警告してきました。 プロジェクトの管理者は至急、シミュレーションNo.299の今後の対応に 関して検討してください。 検討結果報告 以前から予定されていたスイッチプログラムの実行が命令された。 シミュレーションNo.299にスイッチプログラムを追加せよ。 命令を読み込みました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 準備が出来ました。 権限を持つ管理者は、至急◎スイッチを押してください。 この世の終わりのスイッチ ~破滅→◎ プチ破滅→○ テスト破滅→@~ ある晴れた日の朝、道端を散歩していた僕は、世界を破滅させるスイッチを拾った。 縦横13cm、厚さ8cm、の箱状の物体である。 コードの類はどこにも見当たらない。リモコンなのだろうか。 原色の毒々しい赤一色で彩られた手の平サイズの四角い箱に 破滅→◎ プチ破滅→○ テスト破滅→@ という風に、スイッチが3つ並んでいる。 その下には 15/299と言う数字も書かれていた。 どういう意味なのかは良く分からないけど、きっと製造番号か何かだろう。 ん、なに? どうして、これが世界を破滅させるスイッチか、分かるって? なんのことは無いのです。 箱の裏に 『取り扱い 注意』 『このスイッチは世界を破滅させるスイッチです。 この世を消滅させるスイッチです。 取り扱いにはくれぐれも用心してください。 世界の破滅を望むのなら◎を押してください。 プチ破滅で済ましたいのなら、○を押してください。 スイッチの機能をテストしたい方は、@を押してください。』 と書いてあるのだ。 な? 世界を破滅させるスイッチだろ? 柚子(ゆず)。 僕は、となりにいる女の子 岸本柚子子(きしもと ゆずこ)に声をかけた。 「・・・とりあえず、世界にはひまじんが最低2人居ることは判明したわ」 岸本柚子子は可愛いと、男の間では評判だ。 肩より少し下まである黒髪と、トレードマークとも言われている 額のヘアバンドと、華奢とも言えるスレンダーボディの、 どれもが今年度新入生ナンバーワンらしい。(見知らぬ先輩 談) けど、もう少し、僕の言うことも真面目に聞いて欲しいと思う。 柚子は昔から大人しくて可愛い女の子だと、周囲には思われているが、 何故か僕にだけは大人しくしない。 女の子らしく可愛くもしてくれない。 どうしてなんだろう? 僕の方に心の壁というものが無くなれば、柚子の考えが分かるときが来るのだろうか? 「2人って?」 僕は聞いた。 「あんたと、それを作った人よ」 柚子は ふふんっ と得意ぶった顔で笑った。 ちぇっ、あんまりだよ。 桜の花が満開の、春が今年もやってきた。 僕は今年から大学1年生。 その昔は受験勉強というものを潜り抜けなくては成れない、レアな 身分であったというこの学生という地位も、昨今の少子化の 影響か、身分の大安売りとなっており、僕のような怠惰な学生も 無理せず大学に入る事ができる時代になったというわけだ。 今、時間はお昼になったところ。 僕は学食に来ている。 ここのから揚げ定食は、安くてうまいと評判だ。 1日限定100食というこの人気商品は、早く来ないと食べられない。 僕の隣に居るのは、岸本柚子子。 僕と同い年の大学1年生。 高校は違ったが、摩訶不思議、大学は一緒になってしまった。 これも縁というものか? それとも、幼稚園から中学校まで一緒だった腐れ縁が焼けボックイに 新たなる未知の化学反応を引き起こさせたのだろうか? 「ああー! っこら、マス! あんた、いつになったらそのハシを咥えたまま 考え込む癖、直るの!」 柚子は口うるさく、僕の所作のことごとくを正そうとする。 幼少の頃もそうだったが、それは今でも変わらない。 ところで。 僕の名前 佐藤 鱒乃助 (さとう ますのすけ) は、冗談のような本当の名前だ。 両親が『佐藤はいっぱい居るから、せめて変わった名前をつけなくては』と考え、 考えた挙句、決まったのがこの名前らしい。 あんまりと言えばあんまりな名前だが、僕以外のこの名前を知る全ての人間は、 どういうわけかこの名前を気に入っているらしい。 「マス? ああ、サマノスケのこと? ああ、そう呼ぶんだっけ」 かぐわしいカレーの香りをお盆から漂わせながら、僕と柚子の傍に来たのは 柚子と僕の共通の友人の手塚一縷(てづか いちる)。 美人なんだから可愛くすればいいのに、今日もぞんざいに長い髪を縛って Tシャツ、ジーパン、ノーメイクで学校の中をうろうろしている。 なお、あの髪を解くと、背中の真ん中あたりまで来る。 一縷は快活そうなポニーテールを左右に振りながら、僕と柚子をキョトキョトと見比べる。 一縷は僕と柚の共通の友人ではあるが、その事実を知ったのはたった一ヶ月前のことだった。 「サマノスケ? ああ、聞いたことあるわ、マスの高校時代のニックネームね?」 サマノスケとは、僕の高校時代のニックネームだ。 どうしてそうなったのかは分からないが、そうなってしまっていた。 確か、友達の誰かが鱒乃助という名前が信じられず、サマノスケの聞き違いだと思ったとか、 そんな感じから始まったあだ名だったような気がする。 「それで?」 一縷は飢えたニワトリのように僕を見た。 「なになに? なんか、おもしろいことでもあったの?」 僕は、待ってましたとばかりに、今日の朝拾った『世界を破滅させるスイッチ』 名づけて『破滅スイッチ』を見せた。 「くっくっくっ、くはははは! なにこれ! サマノスケが作ったの?!」 一縷は僕の手の内からスイッチを引っ手繰ると、ケタケタと笑い出した。 「違うわ、マスは、こんなの作れない」 柚子は言う。 「マスは不器用だから、こんな隙間の無いキレイな箱みたいなもの、作れないわよ」 「うん? ああ、そういや、そうか」 失礼な説得が功を奏し、僕はこのスイッチ製作の犯人ではないと理解された。 「んで? 結局これなんなの? なんか、裏に数字があるな。・・・45/299? なんだこりゃ?」 一縷が首を捻った。 だから破滅のスイッチだと僕は力説を展開したが、あっけなく拒絶された。 夕方の4時になった。 今日の講義は全て終了し、僕は家路を急ぐことにした。 途中、柚子と合流するつもりだ。 あれ、どうして柚子と合流するんだっけ。 ああ、そうだ。 どうしたわけか、柚子は僕が1人では家に帰れないと思っているらしい。 僕は方向音痴の癖はあるが、家に帰れないほど酷いのは小学校と共に 卒業したはずなのに、柚子のなかでは僕は未だに方向音痴らしい。 そんなことを考えながら、廊下をプラプラと歩いていると、 こっちの方をジッと見ている奇妙な視線があることに気がついた。 キレイな女の人だった。 確か、同じ学年の新入生の人だと思う。 何か寂しげな感じがする女の人だ。年よりも少し若く見える。 その女の人は僕を見て柔らかな微笑を浮かべると、 ゆっくりと僕の方に近づいてきた。 「こんにちわ」 長い黒髪から、ふわっとしたいい匂いがした。 「わたくし、英文学部1年の梨木ミル(なしき みる)と言います。よろしく」 「あ、えっと。どうもよろしく僕は・・・」 「知っていますわ。佐藤 鱒乃助さんでしょう?」 ?どうして僕の名前を知っているんだ? 僕はそんなに有名人だったっけ。 ミルさんは、ミステリアスな微笑を浮かべながら、僕の耳元まで 顔を持ち上げてきて、こう囁いた。 「あのスイッチを大事にしてください。いずれ、うかがいますから」 そう言い終わると、彼女は去って行った。 なんというか、一瞬の間の出来事だった。 僕はそれから5分後に柚子と合流した。 「マスったら! いまだに方向音痴なんだから、これじゃあたしがいないとどうなるんだか」 とか言われた。 ちぇ、約束の時間から3分しか遅れてないのに、その言い草は無いよ。 と、心の中で言い返しておいた。 とまあ、そんな感じで、僕と柚子は同じ駅に向かった。 「ああ、そうね、マスの家は隣なんだから、これから4年間は同じ駅を 使うのよね」 なんか、柚子がブツブツ言っている。 「やれやれ、あんたは方向音痴だからねぇ、この柚子子さんが一緒に居られるうちに 駅への道筋を覚えておくのよ?」 はいはい、分かりましたよ。 それにしても、僕はそんなに方向音痴だったけ? 「そりゃそうでしょ、あんた忘れたの? 小学生の時、あんた迷子になって散々泣き喚いてたこと あったじゃない」 「いつの話だよ、確かそれ、6歳ぐらいの時の話だろ?」 「7歳よ、あんたの8歳の誕生日の14日前のことよ」 そうだっけ。 と、こんなことを喋りながら10分程歩いて、僕達2人は、奇妙なクレーターがある場所に 到着した。 「クレーターだ」 「クレーターよね」 クレーター、それは隕石の衝突や、何かの大爆発で出来上がると言う、まさにそれだった。 でもそれは、少々奇妙な所もあるクレーターだった。 直径50メートルほどのお椀型のくぼ地があり、そこに何かの溝のようなモノが走っている。 アルファベットのFの形とHの形を組み合わせたようなデザインの溝だ。 そういえば、ここ最近利用していた駅の平面図に、良く似ているかもしれないと思った。 「そう言えば、駅はどこだろう、柚子、キミ、方向間違えたんじゃない?」 「そ、そんな事無いって! あたし、道まちがってない!」 「それじゃこれは」 「そもそも、これはなに?」 その答えは分からなかった。 ただ、そのクレーターの中央に男の人が居た。 その男は、ほうけた顔で、何か、リモコン大の大きさの何かのスイッチを押していた。 原色の毒々しい赤一色で作られた手の平サイズの四角い箱のスイッチを プチ破滅→○ という但し書きが示すスイッチを、ただ、押していた。 指が離れないかのように。 さて困ったことになった。 結局、駅と線路の一部が消滅してしまったので (駅の中に居た人たちは、どういうわけかクレーターの外部にはじき出されていたらしい) 僕と柚子は、鉄道会社が準備してくれたシャトルバスに乗り込んだ。 ぎゅうぎゅう詰めのバスから脱出できたのはそれから10分後、 どうにか僕らは最寄の駅の側のバス停で降ろされた。 「いやあ、疲れたね」 僕は務めて明るく、柚子に声をかけた、しかし、柚子は黙ったままだ。 「あ、あのさ、マス、あんたも見たでしょ、あれ」 「うん。あれでしょ? さっきの電車に凄い巨乳の女の人が乗ってた」 「そんなどうでもいい乳のことじゃなくて、あれよ、あのスイッチよ、ボタンよ」 どうでも良くはないよ、あれほどの乳はそうそう無いよ。 「だからそんな脂肪の固まりを無駄に膨らませているメスのことじゃなくて、 あんたの持ってた、あの『破滅スイッチ』ってやつ・・・今も持ってる?」 「うん、ある」 「ちょっと見せて」 僕は言われるがままに、ナップザックのチャックを開いて、中に入れておいた 『破滅スイッチ』を取り出した。 ・・・?あれ、裏の数字が46/299になってる。 「これね」 柚子はしばらくスイッチを観察すると、何か真剣なまなざしで、僕を見つめた。 「このスイッチ、少しの間でいいから、あたしに貸してくれない?」 「押すの?」 「押さないわよ。 けど、もしかしたらよ、もしかしたら・・・これはあたしの推測でしかないけど」 「推測?」 「そう、さっき、いつもの駅が何かの爆発に吹き飛ばされたみたいに、跡形も無くなくなって いたでしょう?」 「うん」 「もしかして、これ、新手の爆弾テロじゃないかしら」 不穏な発言をしつつも、柚子はフッフッフッと、不敵な笑みを浮かべている。 「テロ?」 「うん、そう、簡単なことよ」 柚子はシリアスな表情を浮かべ、僕に迫ってきた。 「最近、駅とかの公共施設では、監視カメラ等のテロ対策が取られている。 なんらかの犯罪組織に所属している人が、何かをしたら、すぐに分かるようにね」 「そうだったの?」 「そうなのよ! それでよ、きっとテロリストは考えたんだわ、 『本来は無害な一般人に、爆弾のスイッチを持たせる』と」 「どうしてそんなことを?」 「マス、あんた分かんない? いい、よく聞きなさい。 爆弾を爆発させようとする人間は、必ず何かの不審な行動を起こすわ、躊躇したりもする。 あるいは、罪の意識に苛まされて、テロを起こす前に自首するヤツも出てくるかもしれない!」 「うんうん」 いつの間にやら、柚子は街灯のスポットライトを浴びながら、 フィクション作品の探偵のように推理を進めていた。 そういえば、もうすっかり辺りは暗くなっちゃったな。 「そこで、何かに偽装したスイッチを第三者に押させるのよ。 そして、この子供のおもちゃみたいなものこそ、その偽装されたスイッチなのよ!」 ビシッと柚子が僕を指差した。 「ふむふむ。 あ、でもさ柚子、それじゃ、いつ爆弾が爆発するか、分からないんじゃない? それに、爆発しないかもしれない」 「確かに、爆発の時刻が不確定なのは痛いわね、けど、たいした問題にはならないわ、 人がいっぱい犠牲になるように爆発したなら、そうしたかったと声明文を発表すればいいし、 犠牲者が少なくても、どちらにしろ社会にとって驚異に代わりはないわ。 もちろん、誰もスイッチを押さないかもしれない可能性はあるわね、けど、誰かが押す可能性が 消えるわけじゃない。いえ、現実に押していた人はいたわ。 ・・・あの駅のクレーターには、確かにいた」 ここで、柚子はシリアスモードを最高潮に高め、 その彫りの深い顔を少しうつむき加減にした。 影の濃い表情が、良く似合うなぁ。 「と、いうわけで、あたし、少しこの箱を調べてみるわ」 「まぁ、それはいいけど、どうして柚子が調べるの? 僕が調べたっていいじゃない」 「マスはドジだから、間違ってスイッチを押したりしたら困るでしょ! ああ、あんたの小学5年生の学芸会の失敗がまぶたに浮かぶわー」 「はい、持って行ってください柚子子様、お願いいたします」 次の日の朝、テレビのニュース番組は駅の消滅事件をやっていた。 僕は食卓の上に置いてある朝ごはんに手をつけつつニュースを見る。 うちの両親は仕事の関係上、揃って朝が早いので、大抵朝ごはんはこうして1人で食べる。 「謎の駅消滅事件を追う!」 「国際犯罪組織の仕業か?! それにしては、怪我人なし?」 「新興宗教クロノスブライト教、大教主語る『最後の審判』がきたのだ」 「飲むだけでみるみる痩せる! ホワイトゴールドパウダーの波動効果がスゴイ! 1ヶ月で 100kgの体重が35kgに!」 「なぜか犠牲者はゼロ。被害者は鉄道会社だけ?」 「飲むだけで背が伸びる! ナノコロイドDNA粉末『のびっこ』1ヶ月で160cmの 身長が3mに!」 「目撃者の証言、奇妙な男が不思議なスイッチを押したあと、世界が白色の光の玉に包まれた」 「ヨモギ紅茶ポピロゲンロイヤルエキス、10日分でわずか15000円」 「自衛隊の全部隊が米軍と合同演習を計画。海上保安庁も沿岸警備の合同演習を韓国、ロシア と行う」 うーむ、つまらん。 駅消失ニュース、あんましやってないぞ? そのあと、テレビは自衛隊と世界の軍隊の合同演習の話しをしていた。 よくわからないけど、ま、僕にはまったく関係の話だし、とっととテレビの電源を切った。 地球環境のためにも、電気を節約しなくちゃね。 今日も楽しいキャンパスライフのスタートだ。 電車は走っていない(駅と線路が消滅している)ため、 鉄道会社が用意してくれているバスに乗り込んだ。 ギュウギュウ詰めのバスで汲々としていると (我ながらうまいぞ) 僕の背中のほうで、押しつぶされぎみな女の子がいることが分かった。 とりあえず、振り返って様子を見る。 そこにいたのは梨木ミルだった。 きれいなロングの黒髪も、これではつむじしか見えない。 「おはようございます、鱒乃助さん」 梨木さんは思ったより小柄な人だった。 僕とは頭1つ分ぐらい違う。 ジッと見上げられると、なんか不思議な感じだ。 (そういえば、一縷なんかは僕より3cmも背が高いのだ!) 「おはよう」 挨拶されたので、挨拶し返した。 しかし、僕と梨木さんにはほとんど面識がないため、ちょっと気まずい。 会話が続かないな。 と思っていたら、向こうから話しかけてきた。 「鱒乃助さん。それで、昨日のことなのですが」 耳元で梨木さんがささやく、なんかゾクゾクドキドキするよ。 「ミルと呼んでください。それで鱒乃助さん。昨日のスイッチのことなのですが、 アレについて、考えていただけましたか?」 「アレって? 考えるって?」 「あのスイッチです。押す、押さない、どちらにするか、です」 「ありゃ、考えてないな」 「そうですか」 ミルは(馴れ馴れしいかもしれないが、心の中ではこう呼ぼう) 少々残念そうな顔をした。 「呼び捨てで結構です。それでは、今はスイッチはどこに?」 「うん、アレなら昨日、僕の友人の岸本さんがゆっくり見てみたいって言うから、 預けちゃったよ」 「預けた・・・?」 なにか、少し非難がましい感じの声。 あれ、僕、そんなに変なことしました? 「そう・・・岸本さんには、あのスイッチの価値が分からないとは思うけど」 ミルが柚子の事を言うとき、その口調にはとても冷たいものがあるように感じられた。 「鱒乃助さんは、まだあのスイッチの重要性がわかっていらっしゃらないのです。 今度、ゆっくり時間を取れるときに、教えて差し上げます」 ミルの寂しげな顔に、まったく不釣合いな妖しい笑みが浮かんだ。 ・・・そんなことがあってから学校に到着。 ミルとは適当に別れ、目的の教室へと向かう。 どうでもいい講義を何個か聞き、そして時間はお昼になった。 お昼になれば、勿論学食に直行である。 今日はから揚げ定食をゲットできなかった。 これも直前の講義が時間通りに終わらなかったからだと心の中で八つ当たりしておく。 適当に日替わり定食を頼んだらゴーヤチャンプルー定食が出てきた。 僕はそれを苦々しい思いで運びながら空いている席へ向かう。 偶然そこで柚子と一縷を発見したので、一緒に座ることにした。 「犠牲者がいないって言うのがおかしいわ、あれほどのクレーターが 出来るほどの爆発なら、駅舎の中にいた人が全員死んでもおかしくないのに」 柚子はさっきからカレーうどんを眺めながらウンウンと唸っていたようだ。 柚子はあの駅消滅事件はテロだと言う線で推理を続けているみたいだが、 あれほど建物に被害が出ながら、その事件に巻き込まれた人間全員が 怪我1つしていないと言うのが、どうにも推理のネックになっているようだった。 「なんだ岸本、おまえ、カレーうどん嫌いなのか? どら、アタシが食ってやるか?」 柚子が睨めっこしているカレーうどんを、食い意地の張ったカラスみたいに 狙っている女が現れた。一縷だ。 「チル、あんたカレーばっかり食べて飽きないの? 今日もどうせカレーなんでしょ?」 なお、チルとは一縷の愛称だ。 一縷で充分に呼びやすいと思うのだが、幾人かの一縷の友人は、彼女のことをチルと呼ぶ。 「何を言うんだ! 今日のアタシはキーマカレーだぞ」 確かに、一縷が手に持つお盆にのっかっているのはキーマカレーだった。 一縷は今日もいつもの格好、ジーパンTシャツにノーメイクだ。 これであのFカップの乳房と、ロングの黒髪が無ければ、 ハスキーボイスの美少年でも通るかもしれない。 「Eだって・・・ところで、あのニュース見た? すげーのなんのって、 みんな朝からアレの話で持ちきりだよ!」 「ちょ、ちょ、E? E?」 「そうだね、驚いたよ、実は僕らは昨日の夕方、丁度あの現場に出くわしてね。 いや、生で見た者としては、信じられない光景だったよ」 「うそ、ちょ、デカイとは思ってたけど、マジ?」 「ああ、そうか、サマノスケと岸本は、あの駅を使ってたんだっけ」 「トップ、アンダー差、答えられる!?」 「20.3。 そうか、いやそれならさ、サマノスケたちは『ボタン男』ってやつは目撃した?」 『ボタン男』って何だ? 「いや、知らない? その、駅の消滅事件の時に、駅があった場所に出来たクレーターの ど真ん中に、怪しげな男が居たって話、ああ、そう言えば昨日・・・」 言いかけたところで、柚子がハッとした顔になった。 そして一縷の口を手で押さえた。 「もごもご」 「一縷、その件に関しては、あとで話があるの、マスも! お昼ごはんのあと、ちょっと いいかしら?」 「なんだよ岸本、Bだからって、気にしなさんなって、こんなもの膨れてても大して役には たたない・・・」 「いや、その、すいません、岸本様、柚子子様、ご免なさい」 なんか良く分からないが、柚子が悪鬼の如き表情で僕と一縷を睨んでいたので、 2人でペコペコと謝ることにした。 さて、と言うわけで。 と言うわけも何も無いと言えば無いのだが、僕と一縷は 構内の、とある空き教室に入り込んだ。 「いい、これからあたしが言うことを、絶対茶化したりしないで、真面目に聞いて」 柚子が僕と一縷を睨む。 「何だってんだよ岸本、一体全体、どうしたって言うんだ?」 一縷はそっけない。 「これよ、これ、マスが拾った『破滅スイッチ』よ」 そういうと、柚子はカバンからゴソゴソと例の『破滅スイッチ』を 取り出した。 「ああ、これ、あ! そうか。 マスが昨日、拾ったって言ってたヤツだ」 「そうよ、これがそのスイッチ、あたしは昨日の夜、マスからこのスイッチを預かって、 家に持って帰って調べようとしたわ」 「それで?」 「箱自体はプラスチックに『良く似た』材質だった。 結局、箱のどこにもフタや継ぎ目が見当たらなかったから、あたしはこの箱の底を 切り取って、中を見ることにしたの」 「ふむふむ」 このふむふむは僕だ。 「まず、カッターの刃を当てたわ、そしたら・・・カッターの刃は、食い込むどころか、 次々と刃がボロボロになった。 次に、日曜大工に父さんが使っていたドリルを持ってきた。 数分間、ドリルの刃を当てていたら、ドリルの刃が面白いように無くなっていったわ、 そして、次に、あたしはこの箱にハンダゴテを押し付けた」 「随分な折檻だな、それで?」 一縷が面白そうに、柚子の話を聞き込んでいる。 どうやら興味を持ったらしい。 「ハンダゴテをいくら当てても、箱は少しも溶けなかった、いや、それどころじゃない、 箱には少しも熱が伝わっていなかった」 「ふむふむ」 このふむふむは一縷。 一縷は好奇心に目を光らせながら、箱をコンコンと叩いている。 あれ? 裏の数字、45/299じゃなかったっけ? 85/299だったっけ? とか、ブツブツと言っている。 「そしてあたしは、最後の賭けに出た。 ダイヤモンドの粉がちりばめられているグラインダーを引っ張ってきて、 この箱に押し付けたわ、ええ、あの時、あたしは意地になっていた」 「ほう」 これは一縷と僕の2人同時。 「やめておけば良かった、ダイヤモンドのカッターは、歯が立たなかったわ、 それどころか、箱に押し付ければ押し付けるだけ、ダイヤモンド刃が欠けていった」 「え?」 一縷が奇妙な笑い顔ような表情になった。 「ああっと、えっと・・・冗談、だろ?」 「あたしはマジよ。冗談なんかで言えないわ、これは本当。 この箱は、少なくともダイヤモンドよりも強度がある、何か、未知の存在で出来ているわ」 同時刻 アメリカ合衆国にて 「大統領、失礼いたします」 ここはアメリカ国防総省ペンタゴン。 この五角形の頭脳の要塞の地下1000メートルの所に、 秘密の核実験施設『ネクロドグマ』が存在する。 「アスハリ君か、入りたまえ」 アスハリと呼ばれた白人青年は、全身を小刻みに震わせながら 大統領が待つ、この部屋に入ってきた。 「大統領、プロジェクト『マジックステッキ・トゥエルブ』の結果が出ました」 「うむ」 大統領は威厳たっぷりに答えた。 「聞こうか」 「結果から申し上げますと、プロジェクト『マジックステッキ・トゥエルブ』は失敗いたしました。 核実験施設『ネクロドグマ』で爆発した100メガトン級の水素爆弾の爆心地にセットされた 『破滅スイッチ』は、完全に無傷で残存しました。 ・・・プロジェクトは満場一致で、この」 こう言うと、彼は震えた手つきでアタッシュケースを開けた。 その中には厳重に密封されている子供のおもちゃにしても出来が悪い 赤い小さな箱が有った。 「この、冗談みたいなスイッチを『どうすることも出来ない』と判断しました」 大統領は静かに聴いていた。 このスイッチの存在への苦悩からだろうか、 最近の彼の面持ちには、陰がより深く入るようになっていた。 「封印も出来んのだね」 「はい、捨てることも出来ません、どういうわけか、しばらくすると 封印した場所から消えて、別のところに同じモノが空から降ってくるようです」 「なんと言う事だ」 大統領は頭を抱えた。 「酷いジョークだよ、これは、どんな悪魔なら、こんなスイッチを作ることができるという のか?」 「あるいは」 アスハリ君が、呟いた。 「こういう考えは、許されないかもしれませんが。 ・・・神が創ったのかもしれません」 その時、スイッチの裏の数字は、89/299を示していた。 その30分後 日本のとある大学構内。 この後、しばらく僕と一縷は、柚子の言う『破壊できない未知の物質』の 話を信じられなかったが。 「コンロにかける」 「ガスバーナーで焼き切ろうとする」 「家庭用漂白剤をかけてみる」 「ハンマーでぶん殴る」 などの実験を繰り返したが、このスイッチがまったくもって破壊不可能であると 判断せざるを得なかった。 なお、ハンマーでぶん殴るのは柚子に止められた。 「間違って、スイッチが押されちゃったらどうするの!」 と、カンカンに怒られた。 「それでどうする?」 一縷が僕の顔を覗きこむ。 「うん、そうだな、僕は1つ、いいことを思いついたよ」 「なに?」 「なに?」 一縷と柚子は、興味津々のようだ。 「お巡りさんに届けよう」 2人が『こいつは何を言っているんだ』という目で僕を見る。 まあ、その、なんというかさ、そもそもこれは僕が道端で拾ったものなんだし、 メンドくさいものは、誰かにゲタを預けちゃったほうが楽だと思ったんですけど、ダメですか? 結局、柚子も一縷もスイッチをどうするかのいいアイデアが出なかった。 不戦勝と言う形で僕の意見はこのディスカッションで勝利を収め、 僕達3人は、大学の一番近くにある交番にやってきた。 ここはこの付近では一番古い交番だそうで(柚子 談)、レンガの壁が時代を感じさせつつも 古臭さは感じさせない建物だ。 『チカンは許さない! 泣き寝入りはしない ~女性の担当員が応対します~』 とか 『声かけしよう、みんなで防犯』 とか 『知らない人について行かない ~大きな声で助けを呼ぼう~』 とか、そういう張り紙があちこちにあった。 「こんにちわー」 一縷が元気いっぱいに交番の中に声をかけた。 「はいはい、どうしました?」 中から、交番の歴史に負けないぐらい歴史を感じさせる 老駐在が出てきた。 「アタシたち、落し物を届けに来ました」 「うんうん、落し物だね、どんなものかね?」 一縷は妙に得意げに、その手に握られた『破滅スイッチ』を差し出した。 「これでーす」 「うむ、これだね。それじゃ、この紙にキミの住所氏名、電話番号とか書いて、 それから、どこでどんな具合に拾ったのか、なるべく詳しく書いて・・・」 僕が書こうと思っていたのに、いつのまにやら、一縷が書き始めている。 まぁ、こうして、僕らはこのスイッチを手放すことにした。 これでこのスイッチと僕らの関係は終わり、後は何が起こっても 傍観者でいられる、そう思っていたのだが。