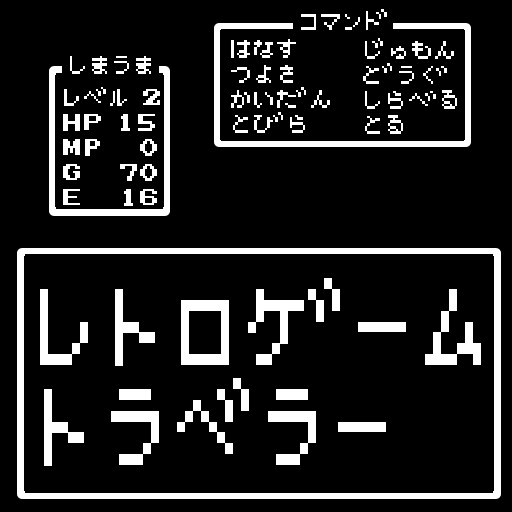マンハンター コマユバチの城
6章 拾ってきた夢
あくる日の朝。 俺はベッドの上で目を覚ました。 昨晩は繭華が泊まっていったはずなのだが、部屋を見渡しても繭華の姿はどこにもなかった。 俺が買ってやった服は洗濯したのか、キレイにしてハンガーにかけてあった。 それきり、俺はまたしばらく繭華の姿を見失った。 繭華が俺の部屋を訪れなくなってから、結構な時間が経った。 破く気も失せたカレンダーを見ると、そこだけはまだ先月だった。 元々、自堕落な生活を続けていた身なので、曜日や日付の感覚はほとんど無かったのだが、 それにしても時間の感覚がまるで無くなった。 繭華が居ない部屋は、ひどくがらんどうな空間のように感じられた。 ベッドに横たわり、天井をただ見つめていると、本当に暗い、なにか途方も無く暗い何かで 心が満たされていくような感じがした。 始めて、自分の死を考えた日のことを思い出す。 あの頃は、病による死を宣告されたばかりのあの頃は、毎日がこんな気持ちだった ことを思いだす。 この感情の名前が分からない。 この、暗い谷底に無限に落下していくような感情を、みんなはなんと呼ぶのだろう。 俺は思わずコンポのリモコンを取り、無意識のうちにスイッチを入れていた。 たまたまかかったラジオでは、誰かがリクエストした歌が流れていた。 その中のフレーズの1つに、俺はハッとした。 「そうか、寂しいって、こういう感情のことを言うのか」 街に初雪が降った。 俺はその雪が降るさまを外で、散歩の道中で見ていた。 結局、俺に残された最後の趣味は散歩だったようで。 これはこれで悪くないのだが、それでももう少し残された日々を 有意義に過ごせはしないものかとなんとなく思ってしまう。 ふと立ち止まる。日が暮れるのが早い。 夕暮れも無い夕方の時間を過ぎると、すぐに真っ暗になった。 ラジオをつけると、どの周波数もマンハンターの猟奇事件に関して 騒ぎ立てていた。毎日毎日、日本のあちこちで起こったという人喰い事件。 気が狂った連中の奇天烈事件が、ここ最近のメディアが騒ぎ立てる日常だった。 つい先日などは隣町でも20人の人間が殺されたらしい。 3日前は都心の方で100人以上の人間が消えたとか、殺されたとか言っていたっけ。 なんでも全体で見ると、毎年日本で自殺する人間の数の3倍を上回る人数が食い殺されているのだ そうだ。 恐ろしい事件だとは思う。 しかし、どうでもいい。 俺はどのみち、そう長くは無い。俺の死因は病死以外にはないだろう。 心配することは何も無い。メディアが騒ぎ立てるようなセキュリティーの充実や マンハンター対策などは、してもしなくても俺にとって大差は無いのだ。 それにしても、どこのラジオ局もマンハンターについてしかやらない。 どうなっているんだ、こんな役に立たない話は聞きたくも無い。 ・・・イセカオル 俺はふと、そのラジオ番組のことを思い出した。 なぜだろう、なぜか忘れていた。 繭華が俺の家に来なくなってからずっと、触れてはいけない記憶のように感じて、 俺はずっとイセカオルのラジオ番組を避けていた。 俺は気がつくとラジオのチューナーを合わせていた。 「・・・えー、それでは最近できたコーナーで、 『聞き間違い大将』の時間がやってまいりました! えーと、これはですねー、みなさんが面白い聞き間違いをしたんだよー。 と言ったような自分の体験を寄せてくださっても結構ですし、あるいは 知り合いの聞き間違いで面白いのがあったから紹介して欲しいぞ! といった、そんな内容の話を集めているコーナーなわけです。 それでは・・・おっ、気が早いね、もう最初のメールが届いているよ。」 空を見上げると、すごい勢いで暗さが広がっていた。 なんとも言えない感情を湧き起こさせる風景だった。 この感情の名前も、俺には分からなかった。 侘しさとか、寂寥感とか、そう言ったらいいのだろうか。 どうもだめだ、いまいちピンとこない。もっと別の言い方は無いのか。 『それでですねー、聞いてくださいカオルさん、そしてリスナーのみんな! 私のネタはこれです。 去年のクリスマスに友人が言った言葉「トナカイのそりに乗ったサンタクロース」を 「トナカイに跨ったサンタクロース」と聞き間違えてしまったんです! って・・・ええーー。それはちょっと、どうでしょう、壮絶な聞き間違いですね。 っていうか、聞き間違いって、言うよりも、それって勘違いとかそういう領域だと私は思い ますね・・・。 でもま、いっか! そういうのもありですよね! ・・・あり? あっていい? えーと、ガラスの 向こうで局長がオーケーサインを出してます。オーケー、オーケー? オッケーだそうです! しかし「トナカイに跨ったサンタクロース」って、どんな人なんでしょうね。 私としてはサンタさんは優しそうなお爺さんのイメージがあったんですが、跨ってしまうと大変 ですね。なんていうかこう、筋骨隆々なイメージですね、戦国武将みたいな、あの赤いふかふかして そうなサンタ服の上からでも全身の筋肉が発達しているのが分かるスーパーおじいちゃん的な イメージになっちゃってます』 ぷぷっ、思わず笑ってしまった。 なんだよ、あんまりだよイセカオル、と、そんな感想を持った。 こっちは自分の死を考えてセンチメンタルに浸っているというのに、 この女ときたら、何が筋骨隆々なサンタだ。 「ふぅっ」 無意識にため息をついていた。 なんかどうでもいいという気分になってきた。 暗い気持ちも、自分の死も、病気も、マンハンターも、なんかもう、どうでもいい。 そんな気分になってきた。 雪はまだ降っていた。 この雪も、積もることは無いだろう。地面に落ちた雪は溶け、雨が降ったのと変わらないくらいに 濡れていた。 そうしていると、後ろから声をかけられた。 「キミ、そこのキミ」 若い男の声だ。 足音がする。2人か。 振り向くと、青っぽい色の制服らしき物を着た成人男性が2人立っているのが見えた。 どういう人間なのか、一瞬、分からなかった。 1人は自然体に立って、こっちを隙の無い様子で伺っていた。 もう1人は若干、不自然な姿勢・・・両手を軽く持ち上げ、すぐに何かを取り出せるような姿勢を していた。 「キミ、こんな時間に何してるの」 自然体に立っている方が話しかけてくる。 ここまできて俺はようやく、この2人が警官の格好をしていることを理解した。 「何って・・・散歩ですよ」 「散歩? こんな時間帯に? それじゃ、別に目的地があるとか、そういうわけじゃないんだ」 「はい」 「マンハンターって知ってる? テレビとかでやってるでしょ、アレアレ、気をつけてね。 1人で外にいると危ないから」 「いましがたも、ラジオで聞いてましたよ。怖いですね、気をつけてないと」 「そうそう、散歩もいいけど、これからは早めに切り上げた方がいいよ。 それとね、ちょっと聞きたいことがあるんだけど」 ちょっと、か? そっちが本題という口ぶりだが。 「2人組みでの男で、パジャマ姿の男の子を連れまわしているのがいるらしいんだけど知らない? お巡りさんたちね、そいつら捜してるんだけど、ここいらで見かけたとか、なにかしら話を聞いた とか、そういうことは無い?」 何の話だ? 正直、まったく聞いたことが無い。 「すみませんけど、今始めて聞きました。パジャマの男の子? 家出かなんかですか?」 「うん、まあそんなとこ、見かけたら、すぐ110番とか、もよりの警察に教えて欲しいな」 「ええ、構いませんよ」 「それとね」 まだあるのか。 「野球帽の男の子、知らない? こう、背丈の小さい子、家出っぽくって、そういう子の話、 聞いてない?」 ・・・ドクッ。 心臓がわずかに鼓動を早めた。 野球帽の子供? 繭華か? いや、早合点するな、そうと決まったわけじゃない。 いや、仮にそうだとしても、何だと言うのだ。どうということもない。 「さあ・・・それだけじゃなんとも分かりません。野球帽の子供、ですか・・・。 思い出してみると、何人かそういう子供も見かけたような気もしますけど・・・ どれが該当しているのか分からないですね」 ・・・こんな言い方で、警察が納得するだろうか。 「ま、そうだろうね」 意外に納得したようだ。 「その子供も、捜索しているの。見かけたら教えて欲しい。 それじゃあ、呼び止めてすまなかったね。今日はここいらで帰るといいよ」 警察官2人は立ち去った。 何なのだろう。パジャマの子供? 野球帽の子供? それだけじゃわけが分からん。 いや、野球帽が繭華だとしても、それじゃパジャマの男の子って誰だ。 うん、待てよ。 そもそもあの2人は本当に警官だったのか? 警察手帳も見せないし、あの制服だけで警官だと言えるのか。 いや。 俺は自分で自分の考えを笑った。 いくらなんでも疑心暗鬼が過ぎる。 俺はいつからそんな、猜疑心丸出しの人間になったんだ? 警官2人と別れて、しばらく歩いた。 テクテクと、自分の足音だけが妙にリズミカルに響く。 雪は降り止まない。それどころか、ますます酷くなっていた。 ラジオではコマーシャルが終わり、またイセカオルのラジバインが始まっていた。 『えーと、次は曲のリクエストのメールですね。 これはなんと、久しぶりにハガキです。みなさん、ハガキですよー! いや、ここ最近、っていうか5年くらいずっとメールしか来てなかったような気がして、 そんななかの久しぶりの本物のお手紙です。いやーお懐かしゅうございます。 えーと、それじゃあ内容を読ませていただきます。 「カオルさん、こんにちは」はい、こんにちは。 「数年ぶりにラジオを聴いたところ、懐かしい声を聞いてびっくりしました。 まだやっていたんですね」 はい、ありがとうございます、って、ちょっとちょっと、まだやってますよ、こちとら 長寿番組なんですよ? 「昔が懐かしくなり、ついついハガキを書き始めてしまったのですけど、今もハガキは 届くのでしょうか? 心配です」 ちゃーんと届いてますよ。ちゃーんと。ハガキを寄越す人がいないだけで(笑) 「曲のリクエストをお願いします。昔の物で恐縮ですがスフォルツェスコの歌で compactという曲です」 はいはい、コンパクトですねー。おお、懐かしい。忘れてました、昔、流行りましたねコレ。 確かビールのコマーシャルソングに起用されてましたっけね』 しばらくして、そのコンパクトという曲が流れ始める。 歌の内容はいたってシンプルだ。 女が空の上から街を見下ろして、「こんなにコンパクトに見える街にあなたがいるうんぬん」 とダラダラと続けるものだ。 ・・・街を見下ろす女。 俺はなんとなく直感で動き出していた。 目的地はあの廃ビルだ。 繭華が街を見下ろしていたビル。 俺は、いつのまにか繭華があのビルにいるのは当然のように感じていた。 会いたいとか、話をしたいとか、そういう感情は無かったような気がする。 繭華があそこにいるかしれない。そう思っただけで、俺の足は自然と動いていた。 深夜の人のいない廃ビル。 辺りは暗く、足元は極端に悪い、濡れた冷たい鉄筋はそれだけでも凶器みたいに感じられて、 この前来た時よりも数段不気味に感じられた。 足を滑らせて落ちでもしたら一大事だ。 ゆっくりゆっくりと確実に上っていく。 しばらく進むと、街の明かりがかすかに届き、周囲がぼんやりとだが見えた。 これなら大丈夫だろう。 ほどなくして、前に繭華を見つけた場所に着いた。 鉄骨の端に立って、街を見下ろす小さな人影があった。 「繭華」 俺は声をかけた。 「うん」 フラリ、と、危なっかしげに振り返る小さな人影。繭華だった。 繭華は俺の姿を確認すると、もういちど街を見下ろした。 「どうしたの」 繭華が聞いてきた。 「ラジオで、お前のリクエスト曲が流れていたぞ」 「ボクの?」 「ああ、ス、ス、スなんとかの古い歌で、コンパクトとかいう曲だ。聞いてなかったのか」 「スフォルツェスコの歌で、compact、だよ。そう、リクエストが通ったんだ。 昔聞いてた時は、リクエスト、1回も通んなかったのに。 ・・・アレ? そういえばどうしてその歌がボクのリクエストだと思ったの?」 「最近、久しぶりにラジバイン聞いて、それでメールを打てる環境を持ってないやつがいるとしたら、 お前ぐらいしかいないと思ってな。あとは歌の歌詞かな。・・・今のお前にぴったりだった」 繭華の口元が軽く笑ったように見えた。 「キミはやっぱりストーカーみたいだねぇ。才能があるよ。」 「そりゃどうも」 「それで、用は終わり? 用が済んだのなら・・・もう帰ってよ。 ボクはこれから大事な人と会わなきゃいけないんだ」 「そうか、そりゃ仕方ないが。 最近、うちに来てないじゃないか、後でいいからたまには俺の部屋にも遊びに来いよ、飯ぐらい 食わせてやるよ」 「野良犬じゃあるまいし、餌がもらえるからってなついたりしないよ」 繭華はふと、俺を見た。 その目は、とても鋭い目だった。あまりにも鋭い、攻撃的なその目線に、俺はめんくらって 一瞬、ひるんでしまった。 次の瞬間、繭華は低い姿勢で俺に突っ込んできた。 ドタン! バン! バシン! 気がついたら、俺は床に倒れていた。 足と後頭部がジンジンと痛む。なんで足と頭が痛いのかもよく分からない。 どうも繭華に足払いをされて、俺は仰向けに倒れこんだらしい。 後頭部が痛いのは、倒れたときに打ってしまったからのようだ。 それで繭華がどこに行ったのかというと。 そいつは俺の腹の上に跨っていた。 「こんなに簡単に出来たのは君が始めてだ。ボクは自分に自信が持てて、とても嬉しい」 「そりゃどうも」 「キミに一応説明しておくと、これはマウントポジションというやつだ。 ボクの両脚でキミの腕を押さえつけているから、キミは抵抗できない。 ここで格闘技なら顔を殴ったりするのだが、ボクはこいつを使う」 繭華は背中の辺りから、ナイフを持ち出した。 「これで切ってしまえばおしまいさ・・・これて分かったろう。キミは弱い。 こんな所にいてはいけない。今すぐにも家に帰るんだ。 ああ、そうそうそれともう1つ、今後、二度とボクを捜してはいけない」 「いや、そう言われても」 ガスッと、繭華は俺の耳元にナイフを突き立てた。 「分かったと言ってくれ、頼む」 繭華の目は、真剣だった。 どう答えようかと思案し始めたところで、下から人が上ってくる足音が聞こえてきた。 「はいはい、そこまで、そこのナイフの女、武器を捨てな」 鉄骨の階段を上って、男が二人やってきた。 俺が先ほど出会った警官だった。 繭華はゆっくりと俺の上からどいた。 そして俺の手をとって俺を立たせる。 その2人を、警戒心むき出しで睨みつけたままでだ。 「野球帽のガキってなお前か」 先頭に立った小柄な男が喋った。 それにしても妙にガラが悪い。さっき会った時はこんな感じだったか? 「どうした、警官に武器捨てろって言われてんだ。武器捨てろよ」 繭華は答えない。油断無くナイフを構えつつ、半開きのリュックにもう一方の手を伸ばす。 「ほら、そこの散歩してた兄さんも、とっととこっち来て、そこ危ないから、それで この階段から降りて、家に帰んなさい」 クイッ。 繭華が俺の上着のすそを引っ張る。行くな、ということか。 「さて、ここでクイズの時間です」 繭華が警官2人組みに向かって変なことを言い出した。 「警察は階級に関してとても厳しい社会だと言われています。 そこで質問、警部と警官は、どっちが偉い?」 小柄な警官が笑った。 「おいおい、ふざけんのも大概にしろよ、人を馬鹿にしくさってっと痛い目みるぞてめぇ」 「答えなかったり、答えを間違ったりしたら、この人殺すよ」 繭華は俺の首元にナイフを突きつけてきた! 「警官なんでしょ? それとも市民の命はどうでもいい? さぁ、答えて、警部と警官は どっちが偉い?」 「・・・」 小柄な方の警官は、急に黙りこくってしまった。 「警部」 後ろの大柄な警官が答えた。 「ハイ」 繭華がニッコリ微笑んだ。 「不正解」 パンッパンッ。何かがはじける音が2回した、鋭い衝撃が連続して走る、何かが焦げるような 匂いがする。 繭華が連装式の散弾銃を発砲したらしい。 何かが警官に命中したようだ。 大柄な方、小柄な方、わずかにタイミングがずれつつも、2人が倒れるのはほぼ同時だった。 「・・・おいおい、繭華、本物の警官だったらどうすんだ」 「本物なら間違えないよ。そもそも警官という階級は無いんだ。 だから、この設問はどっちを答えてもダメなのさ」 「いや、それにしてもよ」 そこでだった。 倒れたはずのニセ警官2人の体が、わずかに動いたように見えた。 次の瞬間には、そのうちの1つ、大柄なほうのヤツが俺たちに向かって黒い影となって突進してきた。 小柄な方も視界の片隅で立ち上がり、傷を押さえつつビルの階段を駆け下りていった。 ヤツらは気を失ったわけでも、死んだわけでもなかったのだ。 世界の全てがスローモーションになったように見えた。 大きなニセ警官の手元には、キラリと光る物があった。 そしてそれに対して俺は、無意識のうちに立ちはだかっていた。 ナイフが俺の腹に刺さったりしたらヤバイと本能的に思ったので、 ・・・何を思ったのか俺は相手に手を突き出して、ナイフの刃を掴んでいた。 俺とニセ警官は、ナイフを中心にして、にらみ合ったまま立っていた。 しばらくそうしていただろうか、ニセ警官の力が抜け、案外あっさり膝から崩れていった。 やはり散弾銃の弾はちゃんとこいつにダメージを与えていたらしい。 やれやれ。 このときの俺は、これで良かったとか、何でこんなことしたんだろうとか考えていた。 しばらくして、手が妙に熱い感じがした。 なんだろうと思い自分の手を見ると、俺の手の平はナイフの刃でざっくりと切られて、血が ダクダクと流れていた。 なんか温かいなと思ったら、自分の血の温度だったのだ。 「・・・キミ、キミ! しっかり!」 なんだろう、いつもは沈着冷静な繭華が慌てふためいている。 リュックから包帯や薬品を取り出し、器用な手つきで俺の手に応急処置を施していく。 「バカ、あんな攻撃避けられたのに! キミがケガをする必要なんて無かったのに!」 「はいはいそうですか、どうもすみませんねー」 「どうして、こんな無茶を!」 「そりゃ、お前、お前がだいじだからさ」 ああ、キザッたらしい。自分でもよくこんなセリフを吐けるものだと思った。 けど、もういい、こうなったらもうなんでもいい。勢いに任せてやってしまえばいい。 俺は怪我をしていない方の手で、繭華をギュっと引き寄せた。 かなり強引な、力任せな感じでだ。本当はもう少し力を抜いてフワッとやりたかったのだが、 そんな力加減の出来る余裕はなく、引き摺り寄せるような勢いで、繭華を抱きしめてしまった。 ゆっくり動いたら、繭華が逃げてしまうような気がして、つい、そうしてしまっていた。 繭華は、どうしたわけか全身の力を抜いて、パフッと身を寄せてきた。 俺の胸の辺りに頬をくっつけて、なにやら顔をモソモソ動かしている。 コートの上からとはいえ、その仕草が少しくすぐったかった。 「・・・キミは」 繭華がつぶやいた。 「キミは本当は、女の子を口説くのが得意なナンパ師なんだろう。 病気とか、死にそうだとか、そういうの全部ウソなんだろう」 「ウソなら最高だったな。でも残念、俺が死にかけなのはウソじゃないし、俺は ナンパ師でもないぜ、自慢じゃないが特定の彼女は作ったことがねぇーんだ」 「それこそウソだ。絶対ウソだ。キミはウソつきだ。 ・・・まぁいい、そろそろ離してくれないか」 俺は名残惜しかったものの繭華を離した。 「ボクとしてはあの銃撃で2人とも動けなくしたつもりだったのだけど・・・。 詰めが甘かったか。まあいい、もう1人の方、追いかけないと」 繭華は散弾銃とナイフをリュックにしまい、当然のように歩き出した。 「おいおい、追いかけるのか?」 「1度敵対した以上、そうするしかないよ、マンハンターは1度狙った獲物や、しくじった相手は 絶対にあきらめないからね。まあ、今度こそキミは自宅に戻りなよ。後始末はボクがする」 不思議と頼りがいのある繭華の言葉だったが、俺も男だ。 繭華に着いて行くと主張したが、繭華も頑なに拒否する。 専門技能も知識も訓練もない半病人がいても足手まといだとか、散々言われたが、俺も俺で意地に なっていた。 ここで繭華を1人で行かせてしまったら、それこそもう2度と会えなくなるのではないかと思って いた。 「やばくなったらすぐ逃げること」 3分ほど押し問答をした結果、繭華は折れた。 万が一に備え、俺は先んじて痛み止めを飲み、繭華についていった。 繭華は地面に落ちている血の跡を追っていた。 ニセ警官の怪我は深手だったのか、ポタリポタリと血の滴りが少しずつ、しかし確実に残っていた。 繭華は慎重に辺りを見渡しながら進んでいく。 もう時間は深夜11時。途中、人は1人もいなかった。 たぶん、みんなマンハンターを恐れて家から出ないか、早めに帰宅しているのであろう。 数百mも歩いただろうか。 血の跡は今は使われていないらしい倉庫に続いていた。 辺りは背丈ほどの枯れた草で覆われている。かなり前に本来の持ち主に捨てられたものらしい。 大きなシャッターの横に人間用のドアがあり、それは半開きになっていた。 誰かが通ったのか、それとも元からそのままだったのか・・・俺には判別がつかない。 繭華は扉の周囲を見渡し、ゆっくりと近づき、念には念を入れてあちこちを調べる。 罠も何もないことを確認して、繭華は滑るようにして建物の中に入っていった。 俺もゆっくりとだが、それに続く。 建物の中はわずかに明るかった。天井があちこち壊れており、上から月や星の明かりが 降り注いでいた。 建物の中には、かなり異様な匂いが立ち込めていた。 はっきり分かりやすく言うと、臭かった。何かの腐敗臭がどこからともなく漂っていた。 建物の中には特に何も見当たらない。 しかし、床には確かに血の跡があり、ここにあのニセ警官が入ってきたらしき形跡は見えた。 あのニセ警官はどこに行ったのか? 種明かしは単純だった。 建物の奥の床に、床下収納に使われるような蓋があった。 それはわずかにずれていて、血の跡はその中へと続いていた。 繭華は迷うことなくそこに近づく。 そして蓋を開け、中を慎重に覗き込んだ。 繭華は数秒もそうしてはいなかった。彼女はすぐに蓋の下の空間に入っていった。 俺もその後を追った。 蓋の下にはハシゴがあり、地下室へと繋がっていた。 地下室は元々あったもののようで、かなり古いことはよく分かった。 周囲はコンクリート打ちっ放しで、飾り気は何一つ無かった。 空気にひどい腐敗臭が混じっていた。上の匂いの原因はここだろう。 地下室の奥には何か台のようなものがあり、そこに判別できない奇妙な物体が多数並んでいた。 それはマネキン人形のパーツのような物だった。 手らしき物、足らしき物、バケツに入ったドロドロした物・・・。 「・・・食べ残しだよ、見ないほうがいい」 気遣いはありがたいが、もう見てしまった。 グロい。グロテスクではある。しかし、どちらかというと現実味が無い、奇妙奇天烈な光景だった。 その台の手前辺りで、誰かが倒れていた。 先ほどのニセ警官の小柄のほうだ。動かない。 「こと切れてる」 繭華がニセ警官の顔をのぞく。 確かに死人の顔だ。目を開けたまま、身じろぎ1つしない。 死んだ振りではない、変なことをいうようたが、それは本当に死体らしく見えた。 「トドメを刺す手間が省けたな、繭華・・・繭華?」 繭華に声をかける。だが、返事が無い。 どうしたのかと繭華の様子を確認する。 繭華は台の上にある何かを見ていた。一点のみを集中して見ていた。 そこには生首が置いてあった。10代半ばの、男の子の頭が、少し腐敗気味ではあったが、 そこにはあった。 「トオル」 生首には元々名前があったのだろう。 何とも言えない奇妙な声で、放心した表情で、繭華はトオルという名前を何度も呟いていた。 生首を見た後、放心状態になっていた繭華を連れ戻すのは大変だった。 人間の形をした立ち木のようにフラフラと立っているだけの繭華を背負って地下室を脱出。 その後もお姫様だっこをしたり、疲れてきたら今度は肩を貸す形で歩かせるなどしてようやく 俺のマンションに着いたのは午前2時を回る頃だった。 途中でタクシーを拾ったのは正解だった。 本当はかっこつけて繭華を抱えたまま帰ってきたかったのだが、半病人の俺では体力が無さ過ぎた。 それからどうしていたか、正直よく覚えていない。 繭華をベッドに寝かせ、自分は最低限の着替えをして、そこからどうしたのか。 いまいち記憶があいまいだ。途中で寝たのは確かだ。 とにかく俺が目を覚ましたのは帰ってきてから10時間後の昼で、それから とりあえず食えるものを、オートミールを用意して、自分で食べて、半分を繭華の近くにおいて 眠気が押し寄せてきたので、もう1度眠ってしまった。 目が覚めたら夕方の5時くらいになっていた。 繭華はベッドの上で体育座りのような姿勢で座っていた。 見ると、オートミールは食べたらしく、器は空になっていた。 しかし繭華の様子はおかしくて、いつもと違うのは相変わらずだった。 目は焦点を合わせず、どこも見ていない。言葉をかけても、何の反応も無い。 肩を揺するとほんの少し反応するのだが、それにしても揺するのをやめるとすぐに元に戻ってしまう。 これはどうしたらいいのか。 当初は途方にくれることもあったが、考えてみればなんのことはない。 どうやら飯は食べるようなので、最低限の栄養補給の食事は用意する。 それ以外のことは、どうでもいい。たまにトイレには自分で行っているようなので、そんなに 問題は無い。 2日もすると、繭華にほんの少し変化が現れてきた。 体育座りをするだけだったものが、ベッドに横になったりするようになってきた。 話しかけても無視気味なのは相変わらずだったが、それでもまあ、少しはマシだった。 劇的な変化が現れたのは、それからさらに3日後のことだった。 「ねぇキミ」 繭華が数日振りに自分から喋った。 「おお、なんだ? なんでも言ってみろよ」 「オートミール以外も食べさせてよ」 飯の催促だった。 その日は、久しぶりに普通の食事が出来た。 この日のために腕を磨いておいたチャーハンを食べさせる。 缶詰のコーンポタージュを温めて出すと、繭華はそれも喜んで食べた。 「ねぇ」 繭華が右手にスプーンを持ったままポツリとつぶやいた。 「キミは何も聞かないんだね」 「ああ、そうだな。まあ、言いにくいこととかあるだろうし」 「そういうキミの姿勢、ボクは悪いとは思わないけど、たまにはキミから聞いて欲しいな。 聞かれないと言い辛いこともある」 「うん、わかった。あの日のことだな、そしてあの生首のことだな? それじゃあ、あの日のことを話してくれよ繭華、まとめまとめでいいから」 繭華は無表情に語りだした。 「ボクが弟を捜しているというのは言っていたよね。 そしてこの街で弟らしき人の姿が目撃されたことも。 ボクはたまに駅の傍にあるネットカフェを利用してて、そこの伝言板に弟を捜しているというメモ を置いてきたんだ。 数日前、そこを確認すると、弟が書いたというメモが残されていて、そこにあのビルで待つって 記してあったんだ。 最初は信用できなかった。だって話が上手すぎるというか、そんな急に本人に出くわすなんて 思ってなかったし。 それで数日そのメモの真偽を確かめようと思っていたんだけど、数日後にはさらに新しいメモが あって、そこにはボクと弟、それとボクらの親以外知りようも無い秘密が書かれていた。 それで、会いに行こうと思って、あのビルに行ったんだ。だが、弟は現れなかった。 来たのはあのニセ警官だった」 繭華はさらに続けた。 「それでピンと来たんだ。 これは罠だってね。でも、他にも重要なことがあった。 あのニセ警官たちがボクをおびき寄せたんだとしても、あの2人は弟に関して、何か知っているのは 確実だ。 そう思って、それで急所からはなるべく外れるように散弾銃を撃ったんだ。結果としてキミに怪我を させたことはは申し訳なかった。 ボクの思惑はその後8割がたは当たったというところかな。それで、あの地下室に辿り着いて、 それで、それで・・・」 「あの首は、弟の物だったのかい?」 「・・・何年も経っているから、最初はよく分からなかったけど。見ているうちにすぐ分かったよ。 これはトオルだ。間違いない。トオルだって」 「そうか」 それ以上、俺はどう言ったらいいのかわからず、俺は窓の外に視界をやった。 「ねぇ、ボクがさ」 「ああ」 「ボクがもっと急いでいたら、もっと早くトオルを見つけてあげることが出来ていたら、あの子は 助かったかな。 マンハンターに食べられる前に、どうにかしてあげることができたかな」 「殺すつもりだったんじゃないのか」 「ああ、そうだ、忘れてた。どうしてトオルを助けるんだろう。そうだ、ボクが、ボクが殺して あげなきゃいけないのに、トオルを殺して、それで、ボクも銃で頭を打ち抜いて死んで、それで 全てが終わるんだって考えていたんだ」 「もう、いいんじゃないか」 「いいって? なにがさ・・・何がいいってさ!」 繭華がやおら立ち上がり、俺に掴みかかってきた。 「キミに、キミに何が分かるって言うんだ! キミは両親の惨たらしい死を見たことがあるのか! あんな、あんな結末を見て、他に何か、なにか言うことは無いのか!? キミは、キミは死んでさっさと消えてしまうだろうから何も考えていない、だろう、けど。 それでも、残された者は生きていくんだ! 家族が消えたこの世界で、もう戻れない記憶を持った まま、生きていく者の気持ちが! キミに分かるのか! キミに!」 俺は、何も言い返すことが出来なかった。 いや、言い返したところで何になるだろう。 俺は卑怯者なのだ。可哀相な病気でとっとと死ぬということを免罪符にして、生きることに正面から 向き合わなかったろくでなしなのだろう。 「なんとか言ってくれよキミも! もう少し急げばどうにかなったとか、そもそもこんなことを しようと、親戚の家を飛び出してこなければよかったとか、そういうことを言ってくれよ! ボクはどうすればよかったのか、言ってくれよ!」 繭華の弟は死んでいた。 おそらく、長くても数週間前には死んでいた。 それは、冷静に考えれば因果応報だったのだろう。 憎しみを抱いた人間を殺し、両親を殺し、そして最期には自分もまた、マンハンターに殺される ことになった。繭華の弟、トオルには、それ相応の罰が下されたと考えることも出来るだろう。 そして繭華は、弟を殺すことなく、死ぬ理由を1つ失った。 ようは、ただそれだけのことだった。 それから繭華は泣きに泣いた。泣きまくった。 涙も声も枯れるほどに泣いて泣いて泣きつくした。 俺はただ、そんな繭華の傍にいて、その背中を優しくなでるぐらいのことしかできなかった。 数時間、子供のように泣き続けた繭華は、疲れきったのだろう。 フッと気を失うみたいに眠りについた。 あの日。繭華の弟の死を確認したあの日。 あれからさらに数日が経った。 繭華は、ずっと俺の部屋にいた。やることが無いのだろう。 部屋の片隅で体育座りしているか、何度も何度も見た雑誌を読み直すかぐらいのことしかして いない。 繭華の精神的ショックは、俺の想像より遥かに大きかった。 まず、食べられない物が増えた。 あの日の翌日、カレーライスを作り、食べさせようとしたら食べられなくなっていた。 本人も「もしかしたら食べられないかもしれない」と思ったらしいのだが、口にしてみて だめだったらしい。 肉という肉が全て食べられなくなっていた。本人の希望もあり、何種類か料理のパターンを変えて 試してみたのだが、全てだめだった。豚、牛、と言わず、鳥肉も全滅だった。 赤い物もだめだった。血を連想させるらしい。 イチゴやトマトはだめ、ケチャップもだめだった。 本人の話を聞いた上で俺もいろいろと考えてみたのだが、どうも繭華はマンハンターを人間では ないものとして強く認識し続けていたらしい。それで相手を人とも思わず、殺すことができたの だろう。 ところが、弟の死体や生首を見て、繭華の心はようやく、マンハンターと呼ばれるものが化物では なく、まごうことなき人間だということに気がついたのだ。 いや、と言うか、マンハンターを人間以外の何かであると思い込み続けることが不可能になった のだ。 結果、繭華はこれまで彼女が見てきた全ての死体、人肉の欠片、血を思い出した。 それらは瞬間的に繭華のトラウマとなり、彼女を苦しめ続ける悪夢の記憶となったのだろう。 なんとか食べられる卵料理、大豆製品、米、パン、野菜類でできる限りメニューを作るが、 バリエーションに限界がある。 食も細くなっており、ただでさえ痩せていた繭華は、ますます痩せてしまった。 俺は肉付きのいい女が好きなんだと言って、冗談交じりで高カロリー食を食べさせようとして いるのだが、実際どれだけ彼女の体を、健康を維持できているのかは分からなかった。 繭華が自分から無理に食べることもあるが、なんどか夜中に吐き戻してしまうことがあり、 無理はさせないようにしている。 病院に行かせたいところだが、本人はなるべく外出したくないと言う。 俺は発作が酷くなっていた。 繭華の世話をしているときに2回ほど倒れてしまった。 倒れるたびに体が訴える苦痛は強くなっていた。 薬の量を増やし、病院で新しい痛み止めをもらった。 これ以上強い薬はモルヒネしかないと言われた。 俺の体は確実に限界に近づきつつあったが、俺は今こそ生きたいと思っていた。 日に日に痩せ細っていく繭華のためにも、自分のためにも生きたいと感じ始めていた。 そんなある日のことだった。 その日も早めの夕食を終えたところだった。 床にじか置きしてあるテレビの電源を入れると、マンハンターに関するニュースばかりやっていた。 「・・・警察では政令指定都市や首都圏に優先的に警察官を配備する方針で、一部議員からは地方を 見捨てるつもりかと批判の声が上がっています。都市の治安維持に関して詳しい○○大学の教授に よれば、ここ最近のマンハンター事件の発生件数は異常であり、これ以上発生すると、司法当局が 犯罪を捌ききれなくなる飽和状態となり、治安が崩壊する可能性があるとも示唆しています・・・」 「こんなのばっかだね」 食器を流しに片付けてきた繭華がテレビを睨みつける。 「このあいだもマンハンターに関して専門家だとかいう人がでてきてどや顔で喋っていたよ。 マンハンターは脳の機能障害の極端な事例だとか、もともと人間は同属殺しのキラーエイプと 呼ばれていたとか言っていたよ」 「勝手に言わせとけばいいさ」 「そいつによるとね、進化というものは環境に適応して起こるもので、それを考えれば、 人間は人間と戦い続けるうちに、人間に対して強くなるんだそうだ。 その最終形態の1つが、人が人を食べるという異常行動なのだとさ」 繭華は途中でリモコンを拾い、俺のほうに歩いてきた。 そしてベッドに座る俺の脚の間に座り込んだ。 「寒いから、毛布かけてよ」 俺と繭華はいつからこうしていただろう。 俺は繭華に恋しているのだろうか。 好きなのは確かだ。けど、強烈な恋愛感情を感じるわけじゃない。 なんと言ったらいいのだろう。 繭華を抱きしめる。別に嫌がる様子もないし、それどころか繭華は俺に背中を押し付けてくる。 繭華に対する感情は、可愛いという感じではない。 自分にとって必要なもの、という感じだった。 俺は、この自分の感情を上手く表現する言葉を知らない。 なんと呼んだらいいのかわからない。 まるでいままでの自分は半身が大きく欠けていた不完全な代物で、こうして繭華を腕の中に 収めていると、その欠けていた半身がかっちりと組み合わさったような感覚だった。 「なあ繭華」 俺は、何度か考えていたことを口にしてみた。 「俺ら、結婚しない?」 プくッ。 繭華が笑った。また、あの分かりづらい笑い声でかすかに笑った。 「ボクなんかと結婚して、どうするつもりなのさ。っていうか・・・」 また繭華はクスクスと、いや・・・プクプクと、笑う。 「いろんな手順をすっ飛ばしすぎじゃないかキミ。 まずそういうのって違うだろう?」 「どう違うんだ」 「まず、キミはボクを学校の裏手に呼び出すんだ、そこでキミはボクに付き合ってくださいと 交際を頼む」 おどけた様子で、繭華は知ったかぶって喋る。 「それで?」 「仮にボクがキミの彼女になったとして、それから数ヶ月は清い交際を続けて」 「ほうほう」 「結婚を依頼する前に、まずはキスだ」 「キスならいつでもできそうだ。今からするか?」 繭華は、そこで少し下を向いた。 「キミがしたいなら、いつでもしてくれていい」 「なんだそりゃ」 「ボクは今、とても弱っている。心も体も、衰弱しているよ。誰かに優しくされて、 求められたりしたら、断りきれないな。弱っているボクには、なんでもできそうだよ? ほら、キミ、チャンスだ。女をモノにするチャンスだ。 キミはもてそうに無いから、このチャンスを逃す手は無いよ。ファーストキスはボクで妥協して おくといい」 「おいおい」 俺は繭華の頭を撫でた。 「そんなこと、言うもんじゃないぜ」 「弱っているボクにすら、そういうことができないのかい? この卑怯者」 「おまえは俺のことをそんな卑怯者だと思っているのか?」 繭華が体をよじる。肉の薄いお尻が俺の脚の間でもぞもぞと動く。 「キミの部屋で最初に一緒にラジオを聞いたときさ、不思議な気持ちを感じたんだ」 「どんな」 「キミと同じ空間にいると、とても心が安らぐんだ。キミと一緒にいると、欠けていた心の何かが、 全部埋まるんだ。魂っていうのかな・・・そういったものがさ、何かとピッタリはまったような 気がして。・・・ずっと男と女の間柄って、もっと燃え上がるジェットコースターみたいなものだと 思ってた。でも、ボクはそうならないみたいなんだ。それが分かった」 繭華も、俺と同じような気持ちを抱いていたのだろうか。 俺は毛布を引き寄せ、自分と繭華をくるんだ。 その晩は、本当によく眠れた。 夢の中で、俺は繭華と一緒に捨て猫を拾って育てている夢を見た。 とても幸せな夢だった。