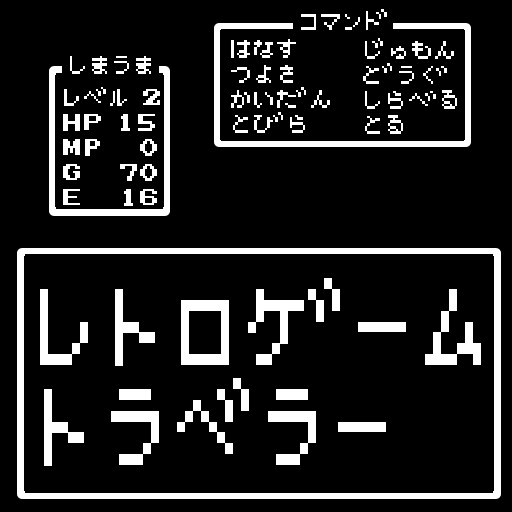マンハンター コマユバチの城
4章 ぬくもり
目が覚めると日付が変わっていた。 寝ぼけた目で辺りを見渡す。昨日の夜はソファで眠っていたらしい。 時計を見る。朝の7時、外は少し明るい。 「おはよう」 足の先のほうから声がした。 繭華だ、まだいたらしい。 見ると髪の毛が濡れていて、全身がこざっぱりとキレイになっている。 風呂にでも入っていたようだ。 「いや、人心地ついたよ。風呂も無ければ無いでなんとかなるんだけど。 自分でも臭いからね。ん、楽になった」 「・・・そりゃあ良かった」 「それでキミ、ご飯まだ?」 「俺が作るのか」 しばし厨房に立つ。 食材が少なく、大した物は作れそうに無い。 しかたなく、魚肉ソーセージを薄切りにしたものをフライパンで焼いたもの、 それとインスタントの味噌汁と、レンジでチンするご飯を用意した。 野菜が無いことに気づき(味噌汁にワカメは入っていたが)タクアンを入れておいた ドンブリを丸ごと出した。 ちゃぶ台にいろんな物を並べると、なんかそれらしい飯に見える。 「いただきます」 心なしか目を輝かせている繭華がすごい勢いで食い始めた。 作ったほうとしてはこうして食べてくれるとうれしいのだが。 それにしてもすごい食欲だ。普段食ってないかのようだ。 「味噌汁と、ご飯ちょうだい」 俺が箸を付け始める頃には、おかわりを要求してきた。 「ふんふーんふん」 腹が膨れて上機嫌になったのか、繭華は俺のベッドに寝転び 雑誌を見始めた。マンガや車の雑誌を次々と手に取り、気に入った記事を見つけては 読みふけっている。 Tシャツと短パンというラフな格好で、無防備なことこの上ない。 しかし、あまり女に見えない。髪の長い小学生男子のようにも見える。 俺はふと、あるアイデアを思いついた。コイツに何か可愛い服を着せてやったら 面白いのではないかと思ったのだ。 俺は早速、妹に電話を掛けた。女の子の可愛い服を、出来るだけ安価に、 気軽に買える店はどこかにないかと聞くためだ。 数コールの後、妹が電話に出る。 俺が自分のアイデアを喋ると、和泉は思った以上に食いついて来た。 「おにいにしてはいいアイデアじゃない? なるべく安い店って言うのがセコ過ぎると思うけどさ。 まあ、無駄に高いブランド物の服を買われるより、相手も気楽だろうけど」 和泉が教えてくれたのは駅前のビルに入っている店だった。 最近、店舗数を増やしているチェーン店だそうで、女子中学生から女子高生までを ターゲットにしている店らしい。名前は「HEKATEKA TRIBE」というのだそうだ。 意味はまったくわからん。 「おい繭華・・・買い物があるんだ、ちょっと付き合ってくれ」 俺は雑誌を読みたいと渋る繭華を、少しばかり強引に連れ出した。 片道20分の道のりを歩き、俺と繭華は例の店、へかてかなんとかに到着した。 時間は午前11時ちょうど、この日一番乗りの客が俺らである。 道行く途中、繭華は随分としつこく聞いてきた、どこに行くつもりだとか何を買うんだとか。 スーパーは道の途中にあったし、俺も「和泉に教えてもらった所があるんだ」としか 言わなかったしな。 それで着いた店がこれだ。 俺は早速店内を物色する。繭華に似合いそうな服は無いかと見て回るが。 「女の服なんて、分からんな」 和泉の学校が終わるのを待って、あいつについてきてもらえば良かった。 これじゃ何を見ればいいのかも分からない。 繭華を見ると、繭華も俺と同じようにキョロキョロとしている。 なんだか知らない家に来た猫のようである。 「キミはあれか? 妹さんの服でも買いにきたのか?」 「違うよ、そうじゃない」 そこで繭華は深刻そうな顔をした。 「・・・キミは女装の趣味があるのか・・・」 「それはマジボケか? それとも狙ったボケなのか? お前の服だ、お前の」 一瞬、繭華はキョトンとした顔を見せた。 「キミは何を言っている?。ボクが? こんなフリフリのついたスカートや、花柄の服をボクが 着るのか?」 「おおそうだ。そんな男みたいな服しかないんじゃさ、どうにもならんだろう。 金ならいくらか持ってきた。高い物は買ってやれないが、ここはそこそこ俺にも手が届く価格帯 らしいからな。とにかく好きな服選べよ、金は出してやるから」 「・・・」 繭華はオロオロしなから、いくつか手近な服を取った。 「ボクは」 「ボクは?」 「こういったもの、よく分からないんだ。学校もずっと制服で通っていたし、おしゃれなんかした こと無かったし。化粧もしたことがない。そもそも興味を持ったことが無かった」 俺たちがそういう話をしているのをどこかで聞いていたのだろう、 店員らしき人物が、俺たちに近づいてきた。 「あらあら、彼氏、彼女にプレゼント? いいんじゃない、ようこそいらっしゃいませ、 ヘカテカトライブに。あたしここの店長のヒロよ、よろしくね」 と、挨拶してきたおっさんがいた。 おっさんである。年は50ぐらいか、やたらスレンダーなボディをしていて、 ぴっちりとしたTシャツとジーパンというスタイルである。 なにかやたらとクネクネと動いている。どこかの振り付け師かダンサーによく似ていた。 「ちょうどいい、店長さん、すまないがツレに合う服を一式都合して欲しい。 予算は20000円ぐらいが限度、なるべく可愛いやつを頼みたい」 背に腹は代えられない。俺はこの店長を頼ることにした。 「アーん、オッケー、オッケー、きっと素敵な服を用意して差し上げるから。 あら、彼女帽子で隠しているけど髪も長いのね、肌もキレイで、これならどんな服も 似合うわー。うふん、ヒロが最高のおしゃれを彼女のために見繕ってあげるわ! あらん、でもそれっと彼氏の目の保養のためかしら、いやん! 初々しいカップル。 うらやましいわー! あたしも彼氏ほしー!」 店長はそう言い残し、店の奥に戻っていった。 「おお! よかっな繭華、服、選んでくれるってよ、俺たちみたいな センスの無い人間が2人で、どうしようかと思っていたところだが・・・繭華?」 見ると、繭華は呆然と立ちすくんでいた。 後で聞いた話では、本物の濃いオカマを生まれて始めて目の前にして、思考が停止していたそうだ。 さて、それからきっかり10分ほど経過した。 「お待たせーん。選んできたわよたっぷりと!」 オカマ店長のヒロが、たくさんの服を持って、店の奥から出てきた。 ふと見ると、さっきはいなかった女性店員が店長の後ろに控えている。 「彼女、こういう服、着慣れてないかと思ったから、みっちゃんに来て貰ったわ! さあさあ試着室で着替えてもらいましょ!」 小柄な繭華は試着室にあっさりと連れ込まれた。 それでみっちゃんという店員さんがあーでもないこーでもないと、服を着させている。 わずか数分で、着替えは終わったらしい。 「さあ彼氏、ごたいめーん」 オカマ店長に背中を押され、俺は試着室前の特等席へ。 みっちゃんさんが試着室のカーテンをさらりと開けると、そこには可愛いらしさでいっぱいの服を 着せられた繭華がいた。 上も下もフリフリだらけの服と長いスカート、ピンク系の色でまとめてある。 野球帽も剥ぎ取られ、髪はそのまま落としている。頭に付けるアクセサリーは 何パターンかの候補があるようだ。今は大きなリボンをつけている。 「へぇ・・・いいじゃん」 俺は思わずそういった。 そんな俺のコメントにみっちゃんさんが付け足す。 「甘ロリってところかな。彼女、華奢で子供体型だから、こういうの似合うでしょ? どうかな、気に入った? まだ履いてないけど、靴も新調したら税込みで18700円。 これからデートなら靴は新調しないほうがいいかなー。靴抜きで13000円ね」 「繭華はどうだ?」 「・・・ズボンがいい、スカートはスースーするから、昔から嫌いなんだ」 「すまない店員さん、この姫様はこんなに可愛い服をお気に召さないようだ」 オカマのヒロが手元にある服をいくつかチョイスしている。 「そうねぇ、あたしとしてはもっとフリフリしたロリータっぽいのが良かったんだけど? 彼女、ボーイッシュなのが好きなのかしらん? うふふ、それはそれでオッケーよ。 それならこれとこれとこうしてあーして」 「店長、いっそこっちをあーして、こっちをそーして、あれがこうなってそれがこうなっては いかがでしょう?」 「あら! いいわね、さすがみっちゃんだわ、じゃ、早速試着タイムね」 「さ、お客様、お手数ですが、再度こちらへ」 シャッと、試着室のカーテンが閉じられ、また着替えが始まる。 腕時計を見る、そんで5分、再度試着室のカーテンが開かれた。 今度の服はブレザータイプの学生服みたいなやつだった。 男子が着るようなやつだが、淡い青系の色でまとめられている。 まがりなりにも一応、女ものなのだろう。あちこちに小さなフリルやらが付いている。 「もう少し、装飾が大人しいやつがいいな。これじゃ一歩間違えれば舞台衣装だ」 繭華の注文はなかなか手厳しい。まあ、言いたいことは分かるが。 「あらーん、残念ねー。彼氏、それでいい? 可愛いのがいいんじゃないの?」 「着るのはそいつなんで、妥協しときます。おとなしめでお願いします」 結局、もう1回、繭華は着替えさせられた。 最終的にはなんか普通の服になっていた。 「ミリタリー風の大きめのパーカに中は白いセーター、キャップが好きらしいから、 ツバが大きめの黒いのを選んでみました。横にシルバーでハートの刺繍が入ってます。 下は発熱素材で作られたジーンズと組み合わせて、しめて15800円ですね」 と、みっちゃんが説明する。 「それでお願いします」 やることが無く、立ちっぱなしだった俺は、なんか少し疲れていた。 そろそろどこかで一休みしたいと考えた俺は、近くにある喫茶店に行くことにした。 名前はルフランという。利用したことはなかったのだが、前々から気になっていて、 一度利用してみたいと思っていたのだ。 繭華を引きつれ、店内へ、エプロン姿のおばちゃんに案内された窓際の席に座る。 「キミは、こういうとこ、よく来るの」 「いや、初めてだな。まあ、たまにはいいんじゃないかな、こういう所も」 おばちゃんがさりげなく水とメニューを置いていく。 「なんでも好きな物頼めよ。おう、1回言ってみたかったんだこういうの」 「ふぅん」 繭華は興味なさげに相槌を打つ。 「・・・おお」 メニューになにか気になる物でも見つけたのか、繭華は小汚いそれをじっと見つめている。 「なんでも頼んでいいの」 「お手柔らかに」 「これが食べたい、チョコレートパフェ」 思ったより意外性のないやつだと思った。 2人で軽い食事を終え、駅前の通りに出た。 俺はスパゲティナポリタンを食べた。味はけっこう良かった。 「まあまあ美味いものが食えたな」 「そうだね、君の料理よりは10倍はマシだね」 少し傷ついた。 「それでさ、キミ、買いたい物があって出てきたんでしょ? それ買ってそろそろ帰んない? そろそろボクとしては雑誌の続きが読みたいのだけど」 「・・・」 と、言われてさて困った。 買いたい物とは繭華の服だったのだが、どうも繭華はそれ以外の何かを俺が 買うつもりなのだと思っているようだ。 ここで「いや、買いたかったものはお前の服さ」とか「手に入れたかったのは着飾ったお前さ」 と言いたい所だが、そんなことを言う自分を想像すると、あまりにもキザったらしいような気が したので、言わなかった。 「そうだな、それじゃあお目当ての店に行くか」 かくして2人でスーパーに買い物に行くことにした。 買いたい物としては、何がいいだろう。 とりあえず米だな。10キロ。それと味噌とインスタント食品各種と缶詰だ。 繭華と一緒に、マンションの部屋に帰ってきた。 「ただいまー・・・よっと」 10キロの米は少々重かった。 しかしこうやってドサドサと食糧を買い込むと、なぜだか所帯染みている感じがするから不思議だ。 繭華には軽い荷物を持ってもらった。 彼女はそれを適当にその辺に放置すると、まっしぐらに俺のベッドに向かった。 そして雑誌を取り出し、読みふける。あそこを自分の場所だと思っているのだろうか。 「少しは買ってきた物を片付ける手伝いをしてくれよ」 「どこに置いたらいいか分からないもの、キミに任せるよ」 繭華はリビングに転がっていたクッションを引き寄せ、それをうまく使い、ゴロゴロと 楽な姿勢を取っている。勝って知ったる我が家のような雰囲気だ。 「なあ繭華」 「なに」 「今日は楽しかったか」 返事が出るのに、ほんの少し時間がかかった。 「楽しかったよ」 その日の夕飯は、やっぱり俺が作った。 今度はケチャップ味の炒めご飯に卵焼きを乗っけてみた。 そろそろレパートリーが厳しい。どうにかしないといけない。 そしてその夜は2人で早めに寝た。 午後10時には寝た。先に寝たのは繭華だった。 繭華の寝息を聞いていると、俺はなんだかこの寝息を聞きながら眠ったら とても気持ちよく眠れるのではないかと思った。 俺はその晩、捨て猫を拾って育てている夢を見た。 とても幸せな夢だった。 『イセカオルのラジバインのお時間です! って、はい、お時間ですって、いっつも言ってますね。 もうちょっと変わった言い方はできないものでしょうか。 飽き気味ですかね、飽き気味です。 バリエーションを増やしたいと思う今日この頃ですが、どうにも他に いいアイデアを思いつきませんね。 ま、そんなことはどうでもいいからまず最初のコーナーです。 えーと、数日前からレギュラーコーナーと化した「教えて師匠!」に たくさんのメールが届いています。良かったねー、いっぱい来たよー。 一応、初めて聞く人も多いだろうから、説明しておきます。 このコーナーは普段疑問に思っていること、分からないことをラジオを通じて 他のリスナーに聞いて教えてもらおうという他力本願なコーナーです。 まあ、似たようなサービスがインターネットにもありますけど、ねぇ、こっちは・・・ねぇ こっちはこっちで面白いみたいで、えー、いいかと思います。即時性ってやつですかね。 それじゃあどんどんいきますか! それでは最初の質問です。 ラジオネーム「ピー介」さんから。えーと 「僕は焼肉を食べるとき、どうしてもあの内臓系が苦手なんです。だめなんです。 友人にホルモンが大好きというやつがいまして、そいつが俺の前で大量のホルモンを 焼くんです。それがもう、見るのも嫌なのです。 みなさんはどうですか? 内臓系、平気ですか?」 とのことでした。 うーん、内臓系かー。カオルはね、えーとピー介さんには申し訳ないんですけど 平気ですね。取り立てて大好き! ってわけでもないですけど、普通に食べられます。 うーん、でもこれはね、こればかりは人の好みというものは違うわけですから、 無理に勧めるのも食べるのもいくないです。いくない。 さて、それじゃあピー介さんの師匠になってくれるリスナーのみんな! オラに知恵を分けてくれ! ってことでここで新曲をかけときます。 地元インディーズバンド、カステラクインテットさんの曲で 「おしゃれ王朝ビクトリア」です、時間は5分3秒。プラスCM3分で8分ぐらい。 その間にメールくださいね。メールアドレスは・・・』 目が覚めると、ラジオがかかっていた。 繭華がつけたものらしい。つけっぱなしだった自分の腕時計を見ると 時刻は11時を指していた。 「おはようねぼすけ君。それともこんにちはかな?」 繭華はベッドの上で胡坐をかき、猫背で雑誌を読んでいる。 Tシャツに短パンというラフな格好は、数日前と変わらない。 昨日買ってやった服はハンガーに吊るされて、俺の服と一緒に置かれていた。 部屋の片隅にある鉄パイプを組んだだけのシンプルな洋服架け、 そこに見慣れない女物の服があるのは、なんとも言えない風景だった。 「俺、こんなに寝てたのか」 「気持ちよさそうに随分寝ていたよ。起こさないようにしていたけど。 そうそう、ご飯、作っておいたよ。テーブルの上に置いといた。 好きな時に食べなよ、ボクはもう食べたからね」 言われて気づく、かすかな食い物の匂い。 グルンと首を動かすと、確かにちゃぶ台の上にご飯がある。 ・・・ご飯だけ、だ、白い銀シャリだけ、もう冷えているのだろう、湯気も立っていない。 「ご飯の共は何がいい? ふりかけ、卵、海苔、納豆、漬物、いろいろあるよ」 「少しはおかずもつけてくれよ」 「ボクは料理を作れない、期待しないでくれ、まあ、炊飯器はなんとか使えた。 家庭科でご飯を炊く勉強をしていて助かったよ。ああいう勉強が、本当に役に立つんだね」 白い飯だけでも充分うまかったが、少し寂しかった。 ラジオでは、イセカオルがずっと喋り続けている。 『さてさて、「教えて師匠!」続きます。 次は、ちょっと変わったものを見たよー! というメールです。 ペンネーム 独眼竜幸村さん。 「カオルさんこんにちわ」はいこんにちはー。 「私、先日変わったものを見たんです。近所にある温室の中で、いつまでたっても蝶にならない イモムシを見たんですよ。しかもそのイモムシ、いっぱい卵が食いついててちょっとキモチワルイの です。あれってなんですかね?」 コレに対して答えてくれる人、募集しますー。 えーと、あて先はこちら・・・。 あらら? すぐに答えが来ました。ってか早。 早過ぎ。えーと、お答えします。ペンネーム アゲハ蝶さん。 「それはコマユバチに寄生されたイモムシです。 そのイモムシはそろそろ死んでしまうかもしれませんね。 葉を食い荒らすイモムシは、植物から見れば害虫ですから、 コマユバチは大事なものを食い荒らす悪いヤツをやっつける 益虫でもあります」 って、へーそうなんだ・・・。そんなのいるんだ、全然知らなかった』 「コマユバチだってよ」 俺はご飯に生卵をかけながら言った。 「益虫なんだって、寄生虫って言うとちょっと怖い気がしたけど、いいヤツもいるだな」 「そうだね」 繭華の反応は、ひどく薄かった。 それからどうしたかというと。 どうもしなかった。ただ、2人でグータラしていた。 窓のカーテンを全開にして、家具がほとんどない殺風景な部屋の中、陽だまりが広がる フローリングの床にただゴロゴロしていた。 時間が過ぎていくなかを、太陽の日差しが少しずつ動いていくことすら感じながら、 ただ2人だけで時間の感覚も無く過ごした。 ほとんど喋りもしなかったが、常に手の届くところに繭華がいてくれて、俺はなんだか とても満足していた。 驚くべきことだが、俺たちはそうして夕方までダラダラと過ごしていた。 繭華は暇になってないかと、何度か心配になって顔色を伺ったりしたが、 なんということもないようで、彼女はただボーッとしていた。 「なんだかさ」 繭華は寝転んだまま、気だるそうにつぶやいた。 「猫みたい」 「猫?」 「そう、猫。猫ってさ。仕事も学校も無いじゃん。 食べ物を探して、ありつくことさえできれば、あとは腹が減るまであったかい安全な場所で 昼寝しているだけでしょ、あいつら。ボクも、なんか同じだなと思って」 「なんか食うか?」 「動いてないから、ほとんどお腹は空いてない」 「そうか」 ベッドの枕元にある時計が、午後4時を示していた。 繭華は腹が減っていないというが、それでもそろそろ何か飯の支度をしようと思った。 フローリングの床から立ち上がる。 一瞬、立ちくらみのような感覚があった。 意識しないふらつき。足元がおぼつかない。 なんだ、これは。 俺は自分の体に強烈な違和感を覚えた。 いや、これは、俺はよく知っている。この感覚は。 突然、激しい痛みが俺を襲った。 「グ、グゥ、ウワアアアアアッ! アガガガッ!」 痛みが、ヤバイ、悲鳴が、立ってられない、腹の辺りで爆弾でも破裂したかのように 痛みが・・・痛みが! 「なに、なに?! どうしたの?!」 あの、普段はあまり表情を変えることのない繭華が、あわてて俺に駆け寄ってくる。 「・・・いや、なに、タイシタこと、ネェですよ」 痛みは変わらないが、それでも慣れれば対処はできる。 突然の悲鳴ぐらい、押さえられないことも無い。 それでも、床にうずくまる姿勢を変えることはできない。 ズキンズキンという痛みを通り越し、ガリガリガリガリと、内臓がドリルで かき回されるような痛みが、ひたすら続いていく。 歯、食いしばって、かっこ悪いが口からよだれたらして、足の先から手指の先まで 猛烈に力を入れて、なんとか踏ん張る。 手の皮が多少ちぎれたり、足の爪が多少割れたりしても気にならない、そっちの方が 痛くなれば、この痛みを少しでも忘れることが出来るから、それで少しマシになる。 「ちょ、ど、どうしよう、どうしたらいい?」 繭華は俺の背中を擦っているが、そんなことではどうにもならない。 いや、少しは楽になるか、しかし痛みの総量は変化しない。 「・・・棚に」 参った、喋るのもキツい。 「棚に、薬ある、3錠、水と」 それだけ、言うのが精一杯。これでも頑張ってるんだぜ畜生。 繭華の行動はすばやかった。棚にある痛み止めの薬を手に取り、正確に3錠取る。 それを俺に手渡し、水をコップに半分ほど持ってくる。 俺はそれをなんとか口にし、そこで始めて座り込んだ。 「いや、はぁ、はぁ・・・かはっ、悪い。心配かけたな」 「・・・すごい痛がりようだった。これがキミの病気?」 「まあな、今もまだ痛いが・・・それでも薬を口に出来たたけでも気持ちが違う。 じきに効いてくるよ。・・・ああ、。少しずつ楽になってきてる」 本当はそんなに早く薬は効かない、でもこういうのは気の持ちようというものもある。 薬を飲む。そういう対処方法をやったというだけでも、気持ち的にはだいぶ違うのだ。 「それにしても、酷い有様だよ」 「ああ、いや、自分でもマジでビックリしたわ、ホント、マジか?って言うほど痛かった。 いや、シャレにならん。いや、ホントホント、今までで一番痛かった」 ふと額に手をやると、ひどい脂汗をかいていた。 「うわっ、なにこれ」 「タオル、持ってくるよ、少しでも横になっていたほうがいい」 繭華はすぐに濡れタオルを持ってきた。 彼女の手で額や顔を拭かれると、なんだか痛みやストレスまで無くなっていくような気がした。 本当に、気持ちの持ちようでちがうものだとつくづく感じた。 「病院でも行くかい? それとも救急車でも呼ぶ?」 「いやいや、そんな大事じゃないって、気にすんな」 「君の痛がりようを、ビデオで撮って、是非ともみせてやりたいよボクは。 あれが大事じゃないって? 大事の見本みたいな痛がりかたしたくせに」 「そんなにひどかったか?」 「そりゃあもう・・・本気でキミが死ぬんじゃないかと思った」 結局その日は、いつごろ寝たのかよく覚えていない。 ベッドに横になった俺を、繭華がずっと看病してくれていたような気もするが、 いまいち覚えていない。 繭華のやつ、俺が死ぬかもしれないって思ったって? 奇遇だ。俺も自分が死ぬかもしれないと、ちょっと思った。 翌日の朝、繭華は半ば強引に俺を病院に連れ出した。 平気だ平気だと俺は言ったが、繭華は聞く耳を持たなかった。 しかたなく、それほど遠くないところにある大きな病院へ行く。 俺の体の変調の正体を突き止め、それでいながら治療方法を発見できずに 対処方法として痛み止めだけ処方した医者がいる病院にだ。 病院に入り、受付で話をし、待合室で診察を待つ。 待つこと30分。俺の番が来た。 前にも見てもらった初老の医者に、また見てもらう。 っていうか薬を出してもらうためにたまにここには顔を出しているのだ。 顔馴染みみたいなものだ。 「ふむ、ふむ、ふむ」 いつもどおりの検査と、いつもと同じ問診。 何もかも代わり映えしない。 「木戸さん」 木戸・・・ああ、俺の苗字だ。 「はい」 「体のほう、拝見させてもらいました。薬はまだ効いてますか?」 「ええ、よく効いてます」 「効きが悪くなったらすぐに言ってください。少し強めの薬を出しますから。 今はいい薬がありますから、生活から痛みを取り除いて、質の高い生活を送ってください」 「はあ」 「それでですね木戸さん。正直に申し上げます。 もう少し詳しいデータが揃わないとわかないところも多いのですが。 ・・・木戸さんの病気は、かなり進行しています」 「と、言うと」 「残されたあなたの人生は、残り少ないです。 ・・・ホスピスとか、今から少しでも考えて置いてください。 パンフレットとかを看護士から受け取って置いてください」 「どうだった?」 診察室を出ると、すぐに繭華がすっ飛んできた。 「何とも無いってよ。とりあえず薬だしとくから、痛かったら飲めってさ」 「・・・そう」 繭華は俺の目をじっと見つめてくる。 何かを推し量るような目だ。 「分かった。早く帰ろう、お腹が空いた」 無言のまま、2人でマンションに帰った。 「無言の帰宅ー」 おどけて言ってみたが、笑えないジョークだったらしく繭華は笑わなかった。 部屋に入り、俺は飯の支度をし始めた。 繭華は部屋に入り、立ちすくんだまま外を眺めていた。 「キミ、あまり長くないんだろ」 単刀直入、ぶっきらぼうにそう言ってきた。 「ああ」 医者の言うところではそうらしい。 「怖くない? 死ぬのって」 死が怖いか、か。 俺はずっと、自分の死を考えてきた。 自分が死体になるところを想像した。 自分がいない世界を想像した。 死の恐怖におびえ、何日も眠れないこともあった。 だが、最近ではあまり気にしなくなっている。 自分が死んだ後の世界には、確かに自分はいない。とても寂しいと最初は思った。 しかし考えてみれば、自分が生まれる前には自分はいなかったのだし、 そこで自分のいない時代、過去が寂しいとは思わないのだから、未来が寂しいというのも、変だろう と思った。 それに死の恐怖といっても、死んだ後というのはつまり、無いのだから。 何も無いということを、怖がるというのも変だと思った。何も無いところでは、怖いということも 無い。 生きていられるやつは、生きていればいいのだし、生きていけないことになったやつは、 後は死を待つだけ。いや、俺という人格のストーリーがそこで途切れるというだけの話。 そりゃ、長いか短いかはあるだろうが。 長いやつは長いし、短い人生を送るやつは、俺より短い人生であっさり死ぬやつも多いだろう。 ま、言うなれば、死というやつは「そうなる時にはそうなる」というだけのものであって、 別段怖がる必要もないし、心配することでもない。 そりゃ、避けられるものなら避けたほうがいいと思うが、それでも避けることが出来ないなら それまでだ。 死ぬまで人間、何が出来るかって、それは生きることしかできないのだ。 「怖いと言えば、怖い。でも、怖がる必要はないものだと思う」 「そうか」 繭華は、淡々としていた。 「痛いのは怖いけどな」 「それはきっとほとんどの人が怖いだろうね」 繭華が明るく言った。 「相当なマゾヒストなら、死に至る痛みも歓喜として受け入れるのだろうけどね。 そう思うと、マゾというのは便利な物だねぇ」 繭華は心底、感心するような口調でそうつぶやいた。 「でもキミは、マゾヒストではないだろうから、痛みは怖いか」 「そうだな」 「前言を撤回するよ。・・・どうしても、君の痛みが酷くて、それを止める方法が無いのだとしたら、 ボクがキミを、・・・殺してあげるよ」 「おまえが、俺を?」 「うん、そうさ。約束するよ。痛みも苦しみもなるべく少ないように、キミを、殺してあげる」 そう言われた時、俺は、心の中の何かが、とても楽になった気がした。 大げさな言い方はしたくないが、本当に、救われた気がした。 俺は無意識に動いていた。 両腕でギュッと、繭華を抱きしめていた。 繭華の体は小さかった。小さいが、抱き心地がとても良かった。