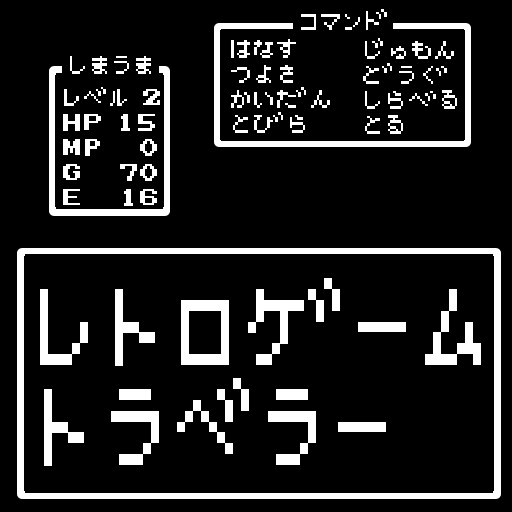ペティグリード ジュブナイルズ
4章 プールと男子小学生!
夏休みを控えた日、今日は終業式である。 おそろしく晴れ渡った空から夏の日差しが降り注ぐ、そしてどこまでも高く白い入道雲が 青い空を突きぬけていく。 朝から4年1組の教室は浮かれきっている。 もう夏休みに入ったつもりでいる生徒も多いようだ。 まだ家に持ち帰っていない荷物を前に呆然とするヤツ、学校が終わったら まっさきに遊びに行く計画を立てているヤツ。 不愉快なことに海外に行く予定について話しているヤツもいる。 ふん、ハワイでもグアムでも、どこでも行くがいいさ。 へぇ、そう、ベネチアとか行くの、ヴェネツィアですか、ふーん。 そんな教室を取り締まるかの如く、宮下先生がやってきて、 終業式前の説明、そして体育館への移動を指示する。 生徒はみんな体育館に集合、校長先生の話や、先生たちからの注意説明を受け、 羽目を外さないよう言い含められる。この辺はいつの時代も変わらないというところか。 あと、変質者に注意するように、という警告もあわせて行われる。 体育館を退出する生徒一同、体育館を離れるごとにみんな少しずつ はしゃぎ始め、教室に戻る頃にはもう無秩序を取り戻して?いる。 そこに再度宮下先生登場。さっと、教室が静かになる。 「はい、それじゃあみんな、今日は終業式だけだからこれでおしまいです。 はしゃいで帰ったりして、怪我とかしたらダメだからねー。 昔いたらしいから、終業式の帰りにはしゃいで帰ったら交通事故にあって、 夏休み中、ずっと病院で過ごす羽目になった子がね。 そうならないように、みんな気をつけて家まで帰るのよー」 はーい。と元気に返答。 きりーつ、れーい、と、日直さんの号令で終わりを告げ、今日はこれで解散だ。 他の教室でも同じような状況らしく、廊下をドタドタと走っていく生徒もいる。 私も帰ろうかと立ち上がったところで、並木少年が後ろから声をかけてきた。 「おい鳶丸! さっそくだけど今日、遊びにいかねぇか? 市民プールに泳ぎに行こうぜ!」 二カッと笑い、彼はいかにも楽しそうである。 うむ、これは好機だ。夏休み中この3人とどうやって接触を図ろうかと思案していたところだ。 向こうから誘ってくれるのならばそれは好都合。私は遊びに行くことを快諾する。 「それじゃ、市民プールの場所はわかるか? わかんないんだったらセアンにでも迎えに行って もらうけど」 並木くん、キミも少しは自分で動いたらどうだ。 どのみち迎えは必要ない、私はすでに市民プールの場所を確認済みである。 そのことを告げると、並木少年はそれならいいやと答えた。 集合は午後1時、水着と入場料の200円を忘れるなとのことである。 私は時間を見計らい、ちょうど午後1時にはプールに着くようマンションを出発する。 ここは自転車を使う。鳶丸を自転車に乗せ、短いサイクリングを楽しむこと10分、 市民プールはもう目と鼻の先だ。 私は文楽55号を自転車に乗せて走れることに自己満足を覚えながら自転車を駐輪場へ停める。 そこを出るとプール前のゲートだ。そこでは例の少年トリオ。 並木醍須、佐東セアン、野々村飛鳥の3人が待っていた。 「おーい、ここだ鳶丸! おっせーぞ!」 くっ、遅いって言ったって約束の時間から5分も経っていないじゃないか。 「ごめん、待たせたかな」 一応、そう取り繕っておく、子供のご機嫌伺いはなかなか大変だ。 「ダイスくん、鳶丸くんは5分も遅れていないよ。 なによりキミが来るの早すぎたんだよ、約束の30分は前からここにいたんでしょ? 楽しみにしていたって言っても、少しやりすぎだよ」 佐東少年がそう並木の本音を告げる。 「うっせーな、セアンは。そこはアレだよ。お前らがオレの興奮を察して、ちゃんと 早め早めに来れば問題ないさ」 無茶である。 「まあまあ、ここは鳶丸くんも来てくれたことだし、これで全員揃ったでしょ? 早く入場しようよ、時間がもったいないよ」 アスカがそう2人をまとめる。 並木少年はそれもそうだと言わんばかりに一目散に入場受付へと走っていく。 「オレ、いっちばーん!」 一番だからなんだというのだ。 さて、我々は受け付けでアルバイトの高校生らしきあんちゃんに200円を支払い、 薄いプラ片の入場券をもらう。これがあれば、一日中遊べるそうだ。安上がりである。 もちろん、私の鳶丸は完全防水だ。 最大水深135mまで潜行可能なこのボディ、塩素の薫り高き市民プールなぞ畏れるに足らない。 では、水着に着替えよう。 4人で更衣室へと向かう。男は青い扉、女は赤い扉らしい そこでどうしたのか、野々村が係りのおばちゃんに呼び止められた。 「女の子はあっちだよ」 おばちゃんのゴツゴツとした指が、反対方向の赤い扉を指す。 我々はアスカが男であることをおばちゃんになんとか説明し、 男性用の更衣室に入ることに成功する。 着替え始めると、並木少年はすでに服の中に水着を着用していたことが判明。 子供かあんたは、と言いたくなるが、そういえば子供でした、すみません。 佐東少年と野々村少年はえっちらおっちら着替え中。 ここは申し訳ないが、2人のお尻やその辺りもチェックさせてもらう。 もちろん、これは私がスパイだからだ! 私は断じて、天に誓って少年男子の尻を見て喜ぶ 変態ではない! しかし残念だ、タオルで隠しているからよく見えない。 よく見えないが、やはり2人の下半身も常人のそれとまったく違いは無いように見える。 そこでふと、私は周囲の不思議な視線に気がついた。 さりげなく周囲を見渡し、辺りを確認する。 数人の成人男性が、アスカの後姿をチラチラと覗き込むようにして見ている。 うん? 明らかにガッチリ見ている。 これは危ない視線かもしれん。アスカ本人は着替えに集中していてまったく気が付いていない。 すると佐東少年が何かに気がついたらしい。 ごく自然な振る舞いで立ち位置を入れ替え、自分がアスカの後ろに立った。 それを見て、何人かが明らかに「チッ」と舌打ちして視線をそらした。 うむ、あの人たちは幼女好きなのか、それとも幼男子好きなのか。 どちらにしろ社会的に危険な存在である。 私はあの舌打ちした連中の顔をしっかり記録し、後で警察に連絡しようかと考えた。 おや、しかしまだ、視線を感じるな。 すると1~2人、佐東少年の方を専門に見ている成人男性もいたことに気がつく。 えーと、どうしようか。 ま、好きな人のタイプはそれぞれだ。違法行為が起こりそうになったら、通報しよう。 みんな、防犯ブザーは大事だぞ。 着替えが終わったのでみんなでプールに向かう。 プールは結構な数の人でごった返していた。どこもかしこも人、人、人だ。 「うわーすげー混んでる! おいみんな、まずはどこに行く?」 並木少年はウキウキした気分を隠しきれない様子である。 そうだ、一応少年たちが着用している水着も詳しく確認しておこう。 並木少年は手足だけ露出するボディスーツみたいな水着を着用している。 白とグリーンのストライプ模様である。 これでは例の背中の傷を確認できないではないか。それほど隠したいものなのか。 かえって気になる。 佐東少年は短パンみたいな形の、よくある男の子の水着だ。 朱色に近い赤地に、テレビヒーローのデザインが入っている。 そして、これまた期待を裏切らない野々村少年の姿は。 水泳選手が着ているような、体を包む面積が大きいタイプの水着だ。 露出しているのは太ももから先の足と、肩から先の腕だ。 色はピンク地に黒いラインが入っている。たぶん女子用だ。 もはや恥ずかしがるそぶりすら見せていない。 「波の出るプールは12才以上の子でないと遊べないって、それとウォータースライダーは 体重制限ありだって書いてある。僕らは無理かなぁ」 まず何ができるのかをチェックしているのは佐東少年だ。 どこまでもマメなヤツである。 「ねぇみんな、まずは流れるプールでグルっと一周しようよ」 野々村少年は浮き輪を抱えて、はりきっている。 「よし、それじゃ、流れるプールで遊んでから、別のとこ行こうぜ」 「うん、その前にシャワーを浴びておこうね」 佐東少年の言うとおりだ。 プールの前にはちゃんとシャワーを浴びて、余計な汚れは落としましょう。 しかしマジメなヤツである。 ちゃぷちゃぷ、くるくる、と、流れるプールに身を任せる。 水の浮遊感が気持ちよさそうだ。本部にいる私は気持ちよくないのが玉に瑕だ。 並木少年は野々村少年のにいたずらしている。 浮き輪を掴み、クルクルと回そうとしているのだ。 「それそれー、ういやつじゃー、ちこうよれー」 「あーれー、おだいかんさまー」 小さな子がする遊びじゃありません! と、心の中だけで注意しておこう。 どこで覚えたんだキミたち。 おや、そういえばトリオが1人足りない。 佐東少年だ。どこに行ったのだ? 彼の姿を捜して辺りをクルっと見渡す。 お、いたいた。プールの売店で何かを買っているようだ。 どうやらシャーベットのようなものを買っているらしい。色は青だからブルーハワイと言った ところか。 看板を見ると青りんごシャーベットとあった、外した。 いやでもさ、青りんごって、青くないよね? 私がそんな心の葛藤を繰り広げていると、佐東少年がちょっとしたアクシデントに遭遇した らしい。 振り返ったところで、前方不注意なお姉さんにぶつかってしまったのだ。 ふむ、遠くて声が聞こえない。 そこで私は鳶丸の聴覚センサーを指向性マイクにモードチェンジ。 これで佐東少年とお姉さんたちの会話が丸わかりだ。 「あ、ごめんなさい、おねえさん、シャーベットかかっちゃいました」 「うう、つっめたーい。でも、こっちこそごめんねボク。あら、シャーベット半分になっちゃった わね」 「ちょっとどしたのよ? あちゃ、これは2人とも災難ね。 でも・・・」 シャーベットがかかった女性と、その友人と思われる女性が、じっと佐東少年を見る。 「あら、金髪でグリーンの瞳、可愛い! ねぇねぇ、キミ外国から来たの?」 「ううん、ボクの生まれはフランスです。でも、長いこと日本に住んでます」 「うわっ、すご! 本物の金髪だ! ねぇちょっと触らせてー、揉ませてー」 わっしゃ、わっしゃと頭を撫でられる佐東少年。 ついでに肩の辺りもペタペタ触られる。 おお、これは逆セクハラか? それとも逆痴漢か? 「う、うわわ」 「はっ、いけないわ、あたし可愛い男の子を見ると、どうしても触れたくなるのよ、ごめんね。 許可が無い限りこれ以上のことはしないわ? 安心して」 許可があればやるのか。 「よし、ボク、かわいいからシャーベット買ってあげる。知らない人から物を貰うのダメとか、 堅いこと言わないでね。これは弁償なんだから、何の問題もないでしょう」 「はぁ、まあ」 「それじゃちょっと待っててね。あ、そうだボク。ここには家族で来てるの? それとも友達で? 1人で遊びに来ていたなら、少し危ないわ。悪い人に連れて行かれるかもしれないわよ? どうかな、おねえさんたちの所に居れば、怖い人も近づいてこないけど」 悪い人はお姉さんだと思います。 「いえ、友達で来てるんです、あっちの方でプールに入っています。 あそこのツンツン頭の男の子と、茶色の髪の長い子、そして黒髪の男の子です」 佐東少年がこちらを見つけ、指し示す。 「そう、それならしかたがないわね」 「今度は1人で遊びに来てなさいよ、もしも会えたら、今度はお姉さんたちとあそぼうね!」 「はい」 1人できたらいかんぞ! 佐東少年! キミは狙われている! それにしても小さな子供を逆ナンしようということか? おそろしい、世も末という気がする。キレイな男なら、誰でもいいのか。 それとも、手付かずの新雪を踏み荒らしたいのか。つぼみの花を手折りたいのか。 佐東少年がこっちへ来る。 みんなが見えるところに腰を下ろし、シャーベットを食べ始めた。 「おーい、セアンー! なに1人でいいもの食ってんだ! 後でちょっとよこせよ! まったく、セアンのやつ、案外食いしん坊だよな」 「うんうん、セアンくんよく食べるよー」 案外、食いしん坊である、と。 こんな些細な情報も何かの役に立つかもしれない、一応覚えておこう。 その後は並木少年の提案で、ウォータースライダーに挑戦することになった。 だが、このウォータースライダーは体重制限があって、あんまり体重の軽い人は使用できない らしい。 我ら4人は全員アウトだ。だが、救済策もある。 体重が軽い人は、何人かでマットにまとめて乗ればいいらしい。 我々はそのマットとやらの力を借り、いざウォータースライダーを目指す。 それで、高いところから水しぶきと共に滑り落ちました。はい、おしまい。 ああもう! 私自身が滑らないと楽しくないじゃないか! なんか映像がでてくるだけだし! うわっ、味再現君が大量の水を私の口の中に噴出してきた! 鳶丸が大量の水を口に含んでしまったらしい。むせてしまった、ゴホッゴホッ。 そんな鳶丸こと私の背中を、セアンくんが優しくさする。 「鳶丸くん、鳶丸くん、大丈夫?」 「へっへー、鳶丸、むせてやんのー」 くっ、ダイスめ、覚えておれ。 本部の私はぐしょぬれだ。ちょっと寒い。 しかし体を拭いている暇は無い。 「おい! 今度はあっちの噴水がついている所で遊ぼうぜ! 水がブシャーって噴出してて、 面白そうだぜ!」 ああ、悪い予感がする。 予感は的中していた。 私の鳶丸は、今度は鼻の穴に水しぶきを食らった。 今度は匂い再現君から、私の鼻に向かって水が吹き出る。 鼻がツーンとする。最低だ。 結局、本部の私はぐしょぬれになる羽目になった。 今度から文楽55号を水辺で運用するときは、操縦者も水着を着用することにしよう。 そろそろ日も陰ってきた。 市民プールが閉鎖する時間帯は結構早いらしい。 スピーカーでアナウンスが入るのに合わせて4人で更衣室へ行き、混雑する中、着替えていく。 水着をバックに詰め、来た時と同じ服に着替える。 入場ゲートをくぐり、外へ出ると、かなり太陽が傾いてきているのに気がついた。 これで、私本体がプールで遊んでいたのなら、今日は本当に楽しかっただろう。 夕焼けの日を浴びながら自転車を漕ぎ、いつもの歩道橋がある交差点で解散だ。 急ぎ、鳶丸を部屋でスリープ状態にし、私は操縦席から離れる。 ええっと、コレ掃除すんの、私ですか? 私が文楽55号の操縦席を泣く泣く掃除していると、肩越しに誰かに呼ばれた。 「元之丞ちゃん、ちょっといいかね」 見ると部屋の入り口にボスが立っている。 右手でお猪口を持つ仕草をしている。どうやら呑みに行こうということらしい。 15分後、私とボスは最寄り駅の前に出ている屋台にいた。 この屋台、名前をアブラの王様という。 なにやらアブラぎった名前ではあるが、なんのことはない。 串カツの屋台なのだ。 「親爺さん、冷やと野菜セット、2人前お願い」 ボスがいつもと変わらぬ注文をする。 なんでも最近、肉類は腹にもたれるとのことで、野菜中心のメニューらしい。 それならそれで、串カツ屋を選ばなければいいのではないかと思う。 「元之丞ちゃん、この前も言ったけど、ソースの2度付けは絶対ダメだよ。 わたしの躾が悪いって思われちゃうからね」 「こっちの人は串カツ屋に慣れてないからね、こうやってお客さん同士で教えあってもらうと 助かるよ」 かつては関西で勇名を馳せた串カツ屋だったという主、斉藤弥五郎さん、78才。 生涯現役を座右の銘に、今日も元気にカツを揚げ続けている。 「へい、毎度の野菜揚げセット! 今日はししとうのいいのが入ったから、お勧めだよ」 「いやー、大将の目利きはわたし、一目置いてますんで、楽しみですよー。 それじゃ頂きますか。元之丞ちゃん、まずは乾杯」 「乾杯」 枡に入ったガラスのコップを、つつっと啜る。 もったいないから少ししか飲みません。 「それでさあ、元之丞ちゃん、どう? 今まであの3人を見てきて」 「アレは」 私は 思ったことを率直に話した。 「別に普通の子たちです。本当に、いや、普通とはちょっと違うところもあると思いますけど 十分、普通の範疇に入ると、私は思います」 「アレ、違うかな」 「違うと、思っています」 ふっと、ボスが串カツに目をやる。 「大将、ごめん、ホタテとかある?」 「はいはい」 屋台の主が少し離れたところへ行き、ホタテを貝殻から外し始めた。 ボスがまるで酒に語りかけるようにボソッと喋る。 「子供ってさ、子供なんだよね」 「どういうことです?」 「子供は、どんなにしっかりしてても、どんな能力を持っていても子供だってこと。 私はね、元之丞ちゃん。子供を守れる大人に成りたいなー、と思うのよ。 いまさらだけど、なんかさーそんなのがいいかなー、かっこいいかなーって、思うんだよね」 「はい」 「もしもあの子たちが例のアレ、だったらさぁ? きっと後々いろんな制約とか、 付くと思うんだよね。それはさ、わたしもわかるんだよね。 どんなに大人しくても、ライオンやトラやクマをさ? 自分の部屋に、あるいは自分の子供の 部屋に置いていて平気な親なんて、全然いない訳だしさ。 猛獣は檻に、入れておくべし、とかなんとかそういうことになると、思うわけですよ、はい」 少しばかり、話が見えてこない。 ただ、こういうことか。あの少年たちがもしもキャバリアという改造人間だったら、 それが公にさらされれば、ありとあらゆる大人の世界は、彼らを放っておきはしないだろう。 キャバリアは人間並みの知能を持った武装したゴリラ程度の存在でしかない。 だが、そのぐらいの力であっても、一般人からすれば十分に驚異的な能力だ。 彼らはなんらかの厳重な管理化に置かれるか、あるいはその能力が発揮できないよう 処理が施されるか。 どちらにせよ大人の世界は、世の中というものは、彼らからそれなりの自由と、少年時代の時間と 思い出を奪い去ってしまうことだろう。 「わたしはね、子供を守れない大人には、なりたくないんだよ」 それは、ボスの重大な決意表明だったのかもしれない。 「はいはい、お待ちどうさまです。ホタテ、揚げますよ? こいつはイキの良い北海道産だ。 うまいよ」 大将がホタテの仕込から帰ってきた。 プリプリとした貝柱が、次々と衣を付けられ、油の中で揚げられていく。 1つ2つとホタテを皿に並べる頃には、ボスの好きな演歌もラジオから流れ出した。 「くぅー、やっぱエドアルド・ロレンツァの『海は荒れてる南極海』はいいねぇ。 こぶしが効いてる、つまみもホタテでちょうどいいし」 ボスが、おちゃらけるようにして歌に反応する。 軽く鼻歌を歌いながら、リズムに合わせて串を振る。 ボスは酒に弱い。もう酔っ払ったのか、それとも演技をして、何かを恥ずかしいことでも隠して いるのか。 他に客も来ない、いつもの夜が更けていく。