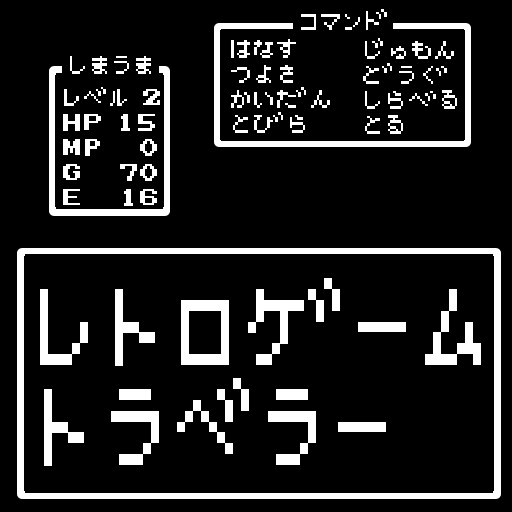マンハンター ジャコウアゲハの夢
5章 5月3日~5月4日
5月3日 水曜日 さて、事態は思った以上にとんでもない事になった。 ・・・朝日がまぶしい。 成り行きとはいえ、まさか、僕が赤の他人の女の子たちと暮らすことになるなんて、 思ってもいなかった。 あの後、アルニーが僕の両親に連絡を取ろうとしたが、僕は自分の家の事情を話した。 母は、大分前に亡くなっていること。 父は、海外で仕事をしていること、等だ。 結局、親父に連絡したのだが、 「おお、好きにしろ。俺も、お前が1人で心配だったんだ」 としか言わず、あっという間にこの共同生活を認めてくれた。 「だが・・・くれぐれも、警察とか少年法とかの沙汰だけは勘弁してくれよ」 とも、付け加えた。 それにしても豪華なベッドだ。 なんでも、元は2人の両親の部屋だったらしい。 コンコン 戸がノックされた。 「おはようございます、周平さん。今日もいいお天気ですよ」 「おはようアルニー、今起きるよ」 「はい」 洗面所を借りて、顔を洗う。 朝食はキッチンに用意してあるらしいので、美味そうな匂いに引っ張られながら移動する。 キッチンにはトーストや牛乳、目玉焼きにサラダが用意してある。 そしてそこには、薄い色合いの金髪の女の子が座っていた。 「?」 誰だったけ。 金髪の女の子が振り返る。 顔はアルニーにそっくりで、トローンとした顔つきでもぐもぐとパンを咀嚼している。 せめてパンを噛み千切ればいいのに、四角い板を咥えたまま、えんえんともぐもぐしている。 コフィだと推測した。 「あれ、コフィ?」 「おはよう、周平」 やっぱりコフィだった。 「周平さんはお席にどうぞ・・・あら、そういえば説明が遅れましたね、コフィの髪を昨日 染めました。後ろ姿だけだと、わたし達は見分けがつかないものですから」 アルニーは席に座りながら喋る。 「いろいろと考えたのですけど・・・この薄めの金髪以外、この娘には似合わなくって」 「うん、そういうことか」 「もぐもぐ・・・アルニーの髪も染めたらいい・・・ごくん」 これはコフィ。 「もう、1度コフィにやってもらったけど、あの時はとんでもないまだら模様になっちゃった じゃない」 「・・・アルニーが器用すぎる」 「コフィが不器用なのよ」 「むぅ」 「ああ・・・もう、ほら、卵の黄身が口の周りについているわよ」 アルニーがコフィの口元を拭く。 朝から誰か人の顔を見るのは、本当に久しぶりだった。 家族の団欒とは、こういうものかもしれない。 朝食を食べたあと、僕は1度自宅に戻った。 少なからず、長期の滞在になるのではないかと予想したので、当面の荷物を 持ち込む手はずだ。 アルニーがタクシー代を出してくれた。 「お爺様からのお金ですから、気兼ねなく使ってください」 と言われた。 あまりにお膳立てされている為、『はい、そうですか』としか言えなかった。 タクシーを電話で呼んで、日月家の前まで来てもらう。 それからタクシーに乗って、自宅へ行く。 自分の家の前につく、当面、必要そうなものを持ち出して、ドラム缶型の旅行バックに 詰めて持ち出す。ついでに、悪くなりそうな食品も詰めた。 タクシーの運転手の白髪のおっちゃんは、何も言わずに荷物の運搬を手伝ってくれた。 荷物を積んだタクシーと共に、また日月家に戻る。 入口の門の所にはアルニーが待っていた。彼女はタクシーを確認すると、その場で何かを操作して 鉄の門を開ける。 タクシーは館の玄関まで来て、そこで荷物を降ろした。代金を支払い、タクシーはそこで帰った。 「大荷物」 玄関にコフィがいた。 やっぱりボーッとして、どこか中空を眺めている。 「思ったよりも荷物が多かったよ。それじゃ、これから部屋に運ぶから」 僕はバックを2つ持ち、玄関に入る。 そんな僕を見て、コフィは僕の手提げバックを奪った。 「持ってあげる」 「・・・あ、ありがとう」 物凄く重たそうに持っている。なんだか悪い気がした。 それから2分後。 「手が痛い」 と言い出して、コフィは荷物を僕に返した。 時間は午前9時。 手持ちぶたさと物珍しさとで、僕はこの館の中をうろうろしていた。 やっぱり、立派な建物は作りが違うと思う。 とは言っても、成金趣味な豪邸だというわけではなく、全体の造りは思ったよりもこじんまり としており、居心地のいい建物だった。 あちらこちらから、人間の生活空間の雰囲気がする。 館というよりは、やはり『家』とか『家庭』という言葉が似合いそうな建物だ。 しばらく歩くと中庭に出た。 それほど大きなものではない。が、とにかく花でいっぱいである。 前に来た時よりも、さらに花が咲いていた。 中庭の隅のほうに真珠色の髪が見える。アルニーだ。 彼女はジーンズ地のオーバーオール姿だった。丈夫そうな前掛けをつけ、手には軍手をはめている。 彼女はいつも白いワンピースを着ていたので、なんだか新鮮な感じがした。 僕は彼女に近づいた。 「アルニー、なにやってるの?」 「ひゃあ!」 びくん! と、アルニーの体が撥ねたように動く。 アルニーはおそるおそる僕のほうを振り返り、安堵のため息をついた。 「はぁー。周平さん。おどろかさないでください。びっくりしました」 「ああ、ごめん、そういうつもりではなかったのだけど」 「今、お天気もいいし、お庭の手入をしているところです。花もいっぱい咲いてくれて・・・ もう少し、花を増やそうかと考えていたのですが」 アルニーは手元の花を愛でる。 「花、好きなんだ」 「ええ、好きです。・・・でも、それ以上に、母が好きだったし、母がいた頃は、もっといっぱい 花が咲いていたように記憶していて・・・その頃みたいにしたいなぁーって、そう思って」 「そうなんだ」 「ええ・・・あら、そうだわ、周平さん、向こうには温室もあります。見てみますか?」 「うん、見せてもらおうかな」 「こちらです」 アルニーが花の垣根の向こうに入っていく。 外から見ると良く分からなかったが、どうやらそこに道があるみたいだ。 細い道を3mも行ったかというところで、温室が見えてきた。 結構背の高い建物だ。実際、2階建てである。 外から見ると大きな鳥かごのようにも見える。 建物の中央には鉄製の螺旋階段があった。 「上の空間には、まだ何も置いていないんですよ」 アルニーは言う。 「温室の管理もしたいのですけど・・・以前の管理人さんに話を聞いたところ、温室の管理って 結構大変なんだそうです。話を聞いているうちに・・・なかなかできることではないなと 感じまして」 アルニーと僕は、鉄の螺旋階段を登っていく。 「下には、以前、母が世話をしていた植物が少しだけ残っていました。 ハーブとか、薬効のある植物のうち、寒さに弱いものはここに置いていたみたいです。 管理人さんも、外の植物までは手が行き届かなかったそうですけど、この温室は守ってくれて いたんです」 アルニーはやさしげな手つきで植物を撫でる。 その時、僕の視界で、何かが羽ばたいた。 蝶だ。ジャコウアゲハだ。 「あら、あの蝶は・・・ジャコウアゲハかしら。やっぱりここの、ウマノスズクサから出てきて いるんだわ」 蝶はふらふらとアルニーのほうに飛んで行き、彼女の腕に止まった。 「・・・」 アルニーは黙ってその蝶を振り払った。 ジャコウアゲハは名残惜しそうに彼女から離れた。 いずこかに飛んでいくその蝶を、どういうわけかアルニーが今までに見たことの無いような表情で 見ていた。 哀れみとも、憎しみとも見える感情が、アルニーの青緑色の目に灯っているように見えた。 それからしばらく後の、日が傾いてきた午後2時頃。 「ねぇ、周平」 庭に出ている白いイスに、コフィが座っていた。 イスの前には小さな丸いテーブルがあって、そこに一冊の文庫本と小物入れがある。 しかし、文庫本はなんだか綺麗に置かれたままだ。読んだ形跡とか、そんな感じは無い。 「周平、こっち来て」 相変わらずトローンとした表情で、コフィが僕を呼んでいる。 サクサクと、綺麗に刈ってある芝生を踏みながら、コフィの傍に移動する。 「どうかした?」 「あのね、あたしね、なんだか首の後ろのほうが、少しヒリヒリするの、見て」 コフィはその長い髪を左手でかき集めて、自分の前に持ってくる。 見て欲しい、とか、見てもらっていい? とかではなく、『見て』の一言。 しかたがない、僕はコフィの後ろに回って、彼女のうなじを見た。 「どうにかなってる?」 コフィの白いうなじに、赤みを帯びたところが出てきている。 「首の後ろが赤くなってるよ」 「どの辺り? 指でなぞって教えて」 「こう・・・この辺から」 僕はぎこちなく、指でコフィの首筋を撫でる。 ・・・すべすべした女の子らしい肌。 「ここまでは確認できる、服の下の背中の所までは、良く分からない」 「じゃあ、服の下も見て、ヒリヒリする」 コフィはそう言うと、服の背中の所の、一番上のボタンを手際よく外してしまった。 関節が柔らかいのか、簡単に背中での作業をこなす。 彼女が2個目のボタンに手をかけたところで、僕は慌ててコフィの手の動きを止める。 「いや、ちょっと・・・それはダメだよ」 「どうして?」 コフィが僕を覗き込むように振り返る。なんだか妖しげな笑みを浮かべている。 「だって、コフィ・・・なんていうか・・・コフィも女の子なんだからさ、そんな、肌を 男の人に晒しちゃダメだよ」 「そう?」 コフィの笑顔の妖しさが増したように見えた。 「それじゃ、周平はあたしが水着になろうとしたら、止める?」 「いや・・・それは止めないけど」 「じゃあ、水着の背中と、この服の下の背中と、周平にとってはどう違うの?」 なんだか、コフィはイジワルだ。 「水着を着ているのと、服を脱いで背中を見せるのは、行為の意味が全然違うよ」 お、今、いい感じのことを言った気がする。 「ふふっ・・・くすくすくす」 コフィが僕の言葉をあざ笑う。 「ねぇ、周平。周平がどんなことを想像したのか、考えるのはとても楽しい。でも、それは 聞かないでおいてあげる」 コフィの髪が、ハラリと乱れた。 「アルニーに聞かなかった? あたしやアルニーは肌に色素を持っていないから、日焼け止めを 塗らないと、太陽光線でちょっとした火傷をしてしまうの、・・・だから、これは医療行為。 あたしは、周平に、背中に薬を塗って欲しいの」 コフィが小さな小物入れを開けた。中にはいくつかの薬品のカプセルのような物と、チューブに 入った軟膏タイプの薬があった。 コフィはそのチューブを取り出すと、僕に手渡した。 「こういうことは、アルニーにやって貰うことじゃないの?」 「確かに、アルニーにやってもらう事、けど、アルニーがいつでも出来るとは限らない」 コフィは背中に手を回し、2番目のボタンを外した。 「アルニーは、それほど体が丈夫じゃない。いつでも、あたしの世話を出来るとは限らない」 3番目のボタンが外れる。ブラジャーの背中のヒモが見えた。シンプルな作りの、白い下着が 見える。 「だから、周平に慣れてもらうの、アルニーが病気か何かで寝込んだりした時のことを考えたら、 これは、やっておくべきこと」 4番目のボタンが外れる。 「これは、火傷の治療、そしてその練習」 5番目のボタンを外す。 「さ、周平、やってみて、上手にやってくれたら、いい点数を付けてあげる」 コフィがブラジャーのホックを外した。その白い背中が、むき出しになる。 いや、背中をむき出しにしたというよりも、何か果物の皮を剥いたようにも感じた。 コフィの背中が、何かのフルーツの未熟な果肉みたいに見える。 僕は、まるで彼女に操られるみたいに、クリームを手にとって、コフィの背中に塗り始めた。 僕が触れた瞬間、ピクッと、コフィの背中が震えた。 「んっ・・・そう、赤いところは、きっと薬が上手く塗れてない、赤いところを塗るように 心がけて」 コフィの背中に触れる。思ったよりも小さな背中で、なんだか生暖かい陶磁器をさするような 感覚。 その白い背中に、赤い線が2本ほど見えた。ブラジャーの跡だ。 「そう・・・そう・・・うん! いい感じ。周平、上手」 もう、なんだか良く分からない。頭に血が上って、クラクラする。 日焼け止めクリームの香りと、コフィの体臭が混ざったモノが香ってきている。 そのあまりにも甘ったるい匂いに、なんだか目眩がするみたいだ。 「・・・どうしたの、周平、手が止まってる。・・・ふふっ・・・もう少しだよ」 背中に塗るだけ、クリームを塗るだけ、これは練習だ。僕はそう、自分に言い聞かせる。 「・・・こんな感じでいいかな、コフィ」 あらかた塗ったつもり、コフィの背中が少し光って見える。 「ありがと」 コフィはそう言うと、さっきとは逆の手順で衣服を整え始めた。 「今日のところは20点」 「ところで、それ何点満点?」 「100点満点中の20点」 「・・・さっき、上手だって言ったじゃないか」 「だって、背中を塗っただけだもの。あたしの全身に綺麗に塗れたら、100点あげる」 コフィが振り返って、僕を見つめる。 コフィの口調は、冗談めいていたが、目は、なんだか違って見えた。 まるで、獲物を見つけた猫みたいな目で、コフィは僕を見つめていた。 「いただきます」 「いただきます」 「もぐもぐ、ごくん」 「コフィ、いただきますは?」 「いただいてます」 ここは日月家のキッチン。 本来、夕食は別に用意してある食堂で食べるのだろうが、人数が少ない為、 こうしてキッチンの一角にテーブルを出して食べている。 テーブルの上にはちょっとした肉料理とサラダ、それにパスタにスープ。 日月家は洋食なのか。 料理はどれも美味しい。僕が自分で作るものは、やはりパッとしないし、 インスタントやレトルト食品ばかりでは、レパートリーもそれほど多くないし、 それになにより、手料理なんて本当に久しぶりだった。 「おいしいよ、アルニー」 「うれしいです、いっぱい食べてくださいね」 僕は肉料理に手をつけた。 「これなに? おいしい」 「ただの鶏もも肉の照り焼きですよ」 ・・・うーん、和食なのか洋食なのか。 アルニーはニコニコと、僕の箸やらスプーンやらが動くさまを見ている。 「どうしたの、アルニー? あまり、食べていないようだけど」 「あ、いえ、どうか気になさらず、召し上がっていてくださいな。 その、なんと言いますか・・・やっぱり、男の人は、食べる早さとか、量とかも違うんだなって そう思って見ていたんです」 「そうかな?」 お、このコンソメいける。 「はい、最近は、コフィと2人きりだったから・・・この娘、結構好き嫌いが激しいし・・・ あ・・・! コフィ、あなたまた鶏肉を食べないの?」 「・・・とりキライ」 「もう、この前はから揚げが嫌いだって言ったから、今回は照り焼きにしたのに・・・ 蛋白質は摂らなきゃだめだって、先生から言われたでしょ?」 「じゃあ、アルニーのゆで卵ちょうだい」 「それでもいいけど・・・もう・・・」 アルニーは器用な手つきで、自分のサラダの上の卵を、コフィのサラダの上に追加した。 「・・・アルニーだって、人のこと言えない。肉、それほど好きじゃないくせに、いつもほとんど 肉料理なんてしないでしょ?どうしてわざわざ、今日は肉?」 「あの、それは」 「周平が、肉を好きだと考えたからでしょ?」 「そうです。そのとおりです。周平さんの好みを考えてみたんです。何か悪いの? コフィ」 アルニーが開き直っている。 「努力、ステキ」 コフィはコンソメスープの皿を両手に抱え、ズルズルと啜りだした。 なお、洋食では通常、皿は持たないし、スープは音を立てて飲んではいけない・・・。 と、僕は聞いていたのだが、このコフィの行為はマナー違反のオンパレードではないのか? 「コフィ、何回も言ったと思ったけど」 「ズルズル。あんな食べ方、めんどーくさい」 しまいには、コフィは口元や胸元がたくさん汚れてしまった。 「ごちそーさま」 「ふぅ・・・さ、コフィ、拭いてあげるから、おとなしくしててね・・・」 そんなコフィの口元を、アルニーが拭いている。 ・・・アルニーは何ぼなんでも、コフィに甘すぎるような気がする。 一応、2人は同じ年のはずなのだが、これでは母と娘というぐらいに差があるように見える。 ひととおり綺麗にしてもらったら、お腹いっぱいになったコフィは、とっととどこかに行って しまった。 コフィの後姿を見送って少ししてから、僕は言った。 「うーん、あのさ、アルニー。人の家のことをとやかく言えるとは思っていないけど、 コフィはいつもああなの?」 「は、はい・・・すみません。躾がなっていなくて・・・どうしても、わたし強く叱れなくて・・・ お姉ちゃんとは言っても、わたし同い年だし、なんだか昔からやっていることで習慣になって しまって」 アルニーは、コフィの口元を拭いたハンカチで、なにかもじもじしている。 「うん、まぁいいけど」 どうにかなるだろ。 「あの娘、他人が居る所では、全然、ああじゃないんですけど。身内の前だけなんです。 ああいうことするの」 「そうなんだ」 「きっと、甘えたいんだと思います。こんな状況だし、それに・・・その、周平さんのこと、 身内みたいに思ってるんです。周平さんには悪いとは思っていますが、・・・あの娘のわがまま や甘えを、少しでいいですから、許してあげて欲しいです」 「それは別にいいけどね。僕のやれる範囲でやってみるよ」 「はい、よろしくお願いします」 月の明かりが白樺の丘に降り注ぐ。 その青い光は、丘の真ん中の建物を照らし出す。 そして光の一部は、館の寝室にも差し込んでいる。 部屋の中には白い肌の少女が2人居る。アルニーとコフィだ。 「コフィ、今日は仕方ないけど、あまり周平さんを困らせることや、マナー違反をしてはだめよ? まるであれじゃ、2人きりの時と一緒じゃない」 鏡台の前で、その長い真珠色の髪をブラシですいているのはアルニーである。 「はーい」 と、ベッドの上からコフィが気の抜けた返事をする。 「アルニーも甘えたらいいのに」 コフィはベッドの上で寝そべりながら、暇そうにゴロゴロしている。 「甘えるって、なにを?」 「周平に甘えたいんでしょ?」 「甘えるだなんて」 「アルニーの考えていること、分かる。アルニーが受け入れられる男の子は周平だけだ」 コフィは、アルニーが顔を赤くしたのを見逃さない。 「どうして、そんなこと分かるの?」 「だって、あたしが受け入れられる男の子も、周平だけだもの」 コフィがニヤニヤと笑う。 だが、コフィの顔も少しばかり赤く染まっている。 「周平となら、きっとうまくやっていける。ねぇアルニー」 コフィはベッドの上で胡坐を組んだ。 「周平に、ここに住んでもらおう」 コフィの表情に、ここ数年来無かった明るさがともる。 まるで、それこそノーベル賞級の発見だと言わんばかりに、自分のアイデアに自信を持っている ようだ。 「住んでもらっているわよ?」 「今は違う、周平はお泊りしてるだけ。そうじゃなくて、ずっと住んでもらうの、今年も、 来年も、10年後も」 「それは・・・」 「なに、アルニー、いやっていうことはないでしょ」 「いやじゃ・・・ない」 「あたしにはアルニーが必要、周平も必要。アルニーにはあたしが必要で、周平も必要。 なら、周平に、あたしもアルニーも、必要になってもらったらいい」 「うう・・・それは、なんだかすごく、その、すごくすごいことを想定しているような・・・」 「いいじゃん」 コフィは片膝を立てる、そうするとパンツ丸見えだよ、と、アルニーは思った。 「3人で暮らそう。周平だって両手に花、きっと喜んでくれるよ」 『あの少女の血液がある』 その情報がデマなら良かったのだが、残念ながらそうではなかった。 『例の姉妹の1人は病気持ち、今は容態が安定しているが、幼い頃は手術もしている。 その手術の際に、あらかじめ自分の血液を採取しておいて、それをさらに手術時の輸血に 使用したようだ。その時にいくつかあまりが生じ、病院側は保管していたらしい。 これは廃棄されるものをその病院関係者が入手したもの。なお、この情報も、その病院関係者から のものである』 私は我慢できなくなってしまった。 ありとあらゆるつてを使ってその病院関係者とやらと接触し、血液を入手した。 ついでに言うと、その病院関係者とやらは喰った。確か4月の20日のちょっと後のことだ。 味は不味かった。特に臓器が最低だった。医者の不養生だ。 冷蔵庫を開ける。 そこにはキンキンに冷えた血がある。 ・・・もう、我慢できなくなっている。 だが、まだだ、まだ、情報を集めるべきだ。 本人を喰うのは、まだ先だ、今は、人の肉への飢えを、この代用品で満たそう。 血液の入った袋の口を開け、吸う。 吸う、吸う、吸う。ちょっとした吸血鬼気分だ。 ・・・うまい。何てうまい味だろう。 いけない、口の動きを止めなくては、あっという間に3分の1を飲んでしまった。 ・・・ああ、塩味と鉄味のシンプルにして絶妙なバランス。各種ミネラルが豊富に溶け込んでいる この味は、地上で最も上手いスープだと言える。 ちょっと子供の味がする。子供の頃の採血なのだから当然なのだが・・・。ふむ、自分でも 感心する。 魚介類も畜産物も農作物も、同じ種類であっても取れた場所や時期で味に違いがあると言うが、 人間にもあるのだと分かる。 しばらくはこれで我慢しなくては、さぁ、余分な興奮は押し留め、狩りの準備を進めよう。 -------------------------------------------------- ◆ 5月4日 -------------------------------------------------- 5月4日 木曜日 日月家周囲の見廻りを自主的に行う。 今日は暑いくらいに天気がいい。 足元の砂利を蹴り飛ばしながら、僕は順調にマウンテンバイクをこいで行く。 しばらくして、お目当ての鉄塔が見えた。高圧電線を通す鉄塔だ。 僕はその鉄塔の下に回って、上を覗き見る。高さと明るさでクラクラする。 やはりここだ。 先日、インターネットに流された盗撮映像から判断し、カメラの位置を割り出した。 昔からの土地勘も駆使した結果、カメラはここ以外に取り付けられないと推理したのだ。 通常、このような高圧電線は高い柵で覆われているのだが、たまに何の障害も無く近づける 塔も存在する。ここはまさにそうだった。 さて、どうするか・・・。 カメラがまだ生きているとは限らない。 こういうものを長時間使うとは考えにくいと思ったが、どう転ぶにせよ、こういう手合いは 排除するしかないと思い、僕は意を決して塔によじ登り始めた。 周囲に誰も居ないことを確認しながら、慎重に登っていく。 ほどなくして、僕はカメラの前に・・・いやいや、後ろについた。 マイクがあるらしいので声は出さない。 慎重にカメラの前を塞ぎ、あちこち弄り回しながらバッテリーを抜いた。 カメラを鉄塔に取り付けている金具を緩め、取り外すことに成功した。 一仕事を終え、僕は鉄塔を降りる。 しかし、手の込んだことをすると思う。 カメラ自体はかなり高性能の物だ。さらに望遠レンズもつけている。良く分からないが高そうだ。 それに水中撮影用の防水ケースを付けている。ケースは本来は透明なのだが、それだと人に 気づかれやすいからだろう、スプレー塗料か何かで黒く塗ってある。 さらに、なんと言うか感心した事がある。電源はソーラーパネルだった。 小型の物だが、ここなら日当たりもいいし、かなりの電力の供給源になっていた・・・と思う。 くどいようだけど、僕はこういうのは良く分からない。 カメラの後ろには配線があり、そこには何かのパーツが付いている。 小型のコンピューターにロボットアームのようなもの、それにおそらく電波を発信する物が 付属している。 全部でいくらするんだろう。20万円はするかもしれない。 僕はこの機材をリュックサックに詰め込むと、もう少し、見廻りを続けることにした。 朝から見廻りを続けて、もうお昼になる。 僕は館に帰ることにした。 カメラはもう発見できなかったが、あれからもう1ヶ所、カメラがあったと思われる場所を 発見した。 崖の斜面に大きな三脚だけが置いてあった。 双眼鏡で確認すると、ここから確かに日月家の庭が見えた。 盗撮者はカメラだけ回収したのだろうか? 三脚だけ置いてあるのは良く分からないが、のちのち、この場所を使うつもりなのかもしれない 思い、思い切って三脚を崖の下に捨てた。 ガラガラ・・・・カン・・・ガッシャーーーン! 三脚は、海岸に打ち上げられたタコみたいになった。うむ、ちょっと気分がいいぞ。 館に帰り、『この先アポマイク』でチャイムを鳴らす。 すぐにアルニーが出て、僕は自転車をゆっくりとこいで行く。 「おかえりなさい、周平さん。あの・・・どうでしたか?」 アルニーが館の外に出迎えに出てきてくれた。 強い太陽の日差しを浴びて、白い髪と肌が輝いているように見える。 「とりあえず、カメラのあった位置を確認してきたよ、1ヶ所はもうカメラは無かったけど、 鉄塔にくくりつけてあったヤツは回収して、持ってきた」 アルニーが『え?』という顔をする。 「あの、大丈夫でしょうか、そんな事をして」 「大丈夫だと思うけど、まさか『オレの物だから返せ』とは、言えないと思うけど」 「・・・そうですね、そうですよね」 「うーん、軽率だったかな、壊しておこうとも思ったんだけど少し壊したぐらいなら 犯人が修復してしまうかもしれないし、いっそ手元にあれば、のちのち、犯人に対して証拠と して提出できると思ったんだけど」 「はい、そうですね、言われてみれば、そうなのだと思います」 「・・・どんなのか、見てみる?」 僕はリュックを開けようとした。 「いや!」 アルニーが慌てて飛んできて、僕の手を止める。 「ア、アルニー?」 「・・・あの、その、ごめんなさい、怖いです。見るの。そんなわたしやコフィを盗撮していた 道具を見るの・・・怖いです」 「ごめんね、これは僕が借りている部屋にしまっておくよ」 「はい、ごめんなさい、そうしていただけると助かります」 僕はリュックの口を閉じた。 「あ、あの、周平さん、お昼ご飯の用意が出来ていますので、よかったらいかがです?」 「いいなんてもんじゃないよ、いただきます」 アルニーの料理の腕前は分かっている。 「キッチンに用意してありますから・・・コホンッ」 「?どうしたのアルニー、風邪?」 「ケホッ・・・すみません。実は少し体調が優れなくて・・・ケホッ、ケホッ」 そう言えば、アルニーは体が丈夫な方ではないのだ。 きっと、ここ最近の心労やら何やらで、体の抵抗力が弱っているのだろう。 なんとなく、顔色も悪い。 「無理したらダメだよ、アルニー」 「はい、大丈夫です。慣れっこですから、今お薬も飲みましたし、すぐに良くなると思います」 僕はアルニーの後ろ姿を見ながら、ついて行く。 なんだか、アルニーの背中が本当に細く見えた。 しばらくして、夜になった。 アルニーとコフィに「おやすみなさい」と声をかけてから、 僕はこの日月の館の、自分にあてがわれた部屋へと行った。 それにしても、この屋敷は夜になると少々不気味だ。 大きさの割に、住んでいる人が少ないためだろうか。 少々急いで、僕はベットに入り込むことにした。 僕は熟睡していた。 窓が開けっ放しだった。青白く光るカーテンがパサパサと揺れる。 そんな僕の胸元が、かすかにざわめいた。 何かの胸騒ぎかと思い、慌てて起きる。時計を見る。今は夜中の2時、辺りはまっくらだ。 「ふぅ・・・」 勘違いだ、もう一眠りしよう。 そう思った時だった。 胸元のかすかなざわめきは、物理的な物だと気づいた。 ペンダントが低周波の音を立てながら、微妙に振動を繰り返していた。 瞬間的に意識がハッキリした。 何かあったのではないか。 僕は素早くセーフティールームに滑り込んだ。 中の電気をつける。 部屋の中で何かが光っている。 その発光体の傍には電話の受話器のような物があり、光の横には『受信アリ』と書かれている。 僕は、おそるおそる受話器をとってみた。 「もしもし」 「あ! 良かった。周平さんですか?」 デジタル化された、少しくぐもったアルニーの声が聞こえてきた。 「うん、僕だよ。今、ペンダントが振動したから、慌ててセーフティールームに入った」 「はい、わたしも今入った所です」 「何かあったの?」 「わかりません。とにかく、ペンダントが震えただけで・・・すこしこちらで確認してみます」 「・・・そこから、何か分かるの?」 「書斎のコンピューターとの回線があります。何かの情報があるといいのですが、少しの間、 電話を切りますね」 電話が途切れた。 3分もしない内に、もう1度『受信アリ』の光が騒いだ。 「もしもし」 「・・・あの、周平さん」 ゴクッとアルニーが唾を呑み込んだ。 「地雷型の探知機を誰かが踏んだようです」 「それって・・・」 「あの・・・その・・・ネコかもしれないし、イヌかもしれないし・・・」 「うん、そうだね、そうかもしれない。・・・そういえば、コフィはどうしたの?」 受話器の向こうで、アルニーが息を飲んだ。 「コフィ・・・コフィはどこ? あの娘、まだセーフティールームに入っていないんだわ!」 わたし・・・あの娘を見つけて、部屋に入れなくちゃ!・・・ケホッ、ケホッ」 アルニーが慌ててセーフティールームから出て行こうとする。 僕はそれを慌てて止める。 「アルニー、君は行っちゃだめだ。ここは僕に任せて」 少しぐらい、かっこつけてもいいかなと思う。 「ちょっと見て廻ってくる。20分したら戻ってくる。20分して戻ってこなかったら、 ・・・警察か警備会社の人を」 「・・・はい、グスッ・・ケホンッ、ごめんなさい、よろしくお願いします」 「行ってくる」 僕はセーフティールームから這い出した。 腕時計をつけ、痴漢撃退スプレーを持つ。 何も起こらないことを期待しよう。 館のバスルームから水音がする。 コフィはシャワーを浴びていた。彼女は時折、こういうことをしている。 シャワールームから出て、コフィは気づいた。 「着替え、忘れた」 とりあえずバスタオルでかるく体を拭く。長い髪から水滴が滴り落ちる。 替えのパンツが無いので、しかたなくさっきはいてたパンツをはくことにした。 けど、パンツもネグリジェも無かった。 「?」 全裸で歩き回るのもどうかと思うので、バスタオルを身体にぐるぐると巻いた。 こんな格好で歩いていて、周平に見つかったらどうしようかと思うと、少しドキドキした。 グイッとバスルームのドアを開けると、 そこに見知らぬ男性が立っていた。 周平は部屋から出て、聞き耳を立てた。 何かの水音がする。 「コフィが喉が渇いて・・・水を飲んでいる・・・と、いいのだけど」 スプレーを構えつつ、キッチンへと移動する。 コフィの目の前に立っている見知らぬ男性は、年齢は20代半ばで、体格は普通だった。 だが、服装と雰囲気は、普通ではなかった。 服装は黒いジャージ姿。黒い帽子に黒い手袋、黒いウェストポーチに黒くて真新しい運動靴。 息は荒く、なんだか良く分からないがハァハァ言っている。肩で息をしている。 コフィには、病気で苦しむ人みたいに見えた。 「・・・誰?」 その男は、コフィの下着を持っていた。 「こら、あたしの下着、返せ」 コフィは全力で怒った。 けど、全然怖くなかった。 男はハァハァ言っているだけだ。・・・なんだか変だ。 男はコフィの体をジロジロと見ていた。バスタオル1枚のコフィの体を品定めしている。 「コフい」 コフィは、男の発音がおかしいと思った。それじゃ『こふい』だ、『こふぃー』って伸ばせ、 と思った。 「おれを待っててくれたんだね、おれを誘惑してるんだね? なんていけない娘だ。 お仕置きしてあげるよ、いい娘にしてりょよ、可愛がってやりゅから」 男が、コフィに襲い掛かった。 ドカァ! と勢いに任せて一気にコフィを押し倒す。 コフィの両手を組み敷いて、男は全ての体重を、コフィのほっそりした身体に乗せる。 「やべ、やべ、やべ、いい匂い、たまんね、やべ、やべ、やべ、やべ」 「いたい・・・! いたい! どいて! いたい!」 コフィは思った。・・・腕がいたい! 手がいたい! コフィは男の下で暴れた。 そして、その白い脚が、男の股間に命中した。 コフィは、なんだか気持ち悪いものを踏み潰したような感じがした。 男が崩れた。床に倒れこむ。 コフィは駆け出した。男が怖いというよりも、気持ち悪かった。 数分後、男は復活した。 「コフい・・・コフい・・・てめぇ・・・! こっちがしたでにでてりゃあいい気になりやがっ て! ふっ殺してやう!」 殺してやる、ころしてやる! お前なんか! 男はコフィの後を追いかける。 コフィの洗い髪の匂いを鼻でたどり、追いかける。 しばらくして、コフィが見つかった。彼女は息切れして、歩き始めていた。 「コフい! 待て! そこにいりょ!」 男が追いかけてきた。逃げなきゃ、逃げなきゃ! コフィは自分の脚を懸命に動かしたが、男の足の速さは半端ではなかった。 「おれの言うこと・・・聞けよ! 待てって、言ってるディヤリョ!」 男は強烈に興奮していた。 闇の中に躍る、綺麗な金髪。 必死になって走り、動かし続ける白い脚が、その付け根まで見えそうだった。 洗いたての、つやつやした太ももに、本気でかぶりつきたくなった。 ウソみたいに白くて、まるで何かのお菓子みたいに見えた。 コフィの走る姿を見て、『この女は、白い尻を振って、おれを誘っている』男はそう勝手に 解釈した。 ・・・気持ち悪い、気持ち悪いのが来る・・・逃げな そこで捕まった。 男はコフィの髪を捕まえ、廊下の床に引きずり倒した。 「アウッ!」 コフィはしたたかに背中を打った。 しばらく息が出来なかった。 「あぅぅ・・・」 息が出来ない、呼吸が出来ない、声を出せない。 男が覆いかぶさってくる。 今度は両足も組み倒され、コフィの両腕は頭の上で、男の片腕で押さえつけられた。 「コフい、てめぇふざんな! 自分から誘っといて、自分から裸になっておいて、蹴るとは どういうことだ、ああ? きょら! てめぇみてぇなクソガキには、おれが世の中の渡り方を、 常識ってもんを教えてやりゅよ!」 コフィは、男の気が狂っていると思った。 男が、コフィの唇を奪った。 コフィは逃れようともがいた。 男が、コフィの口の中に思いっきり舌を入れた。 やめて・・・やめて・・・お願いやめて・・・。 コフィは、感情が爆発して、泣き出した。 お願いだから・・・やめて・・・。 周平はバスルームの前に着いた。 バスルームの電気が点いていて、戸は開きっぱなしだった。 そして戸の下には、女の子の物と思われるパンツが、クチャッとなって落ちていた。 周平は意を決してバスルームに飛び込んだが、そこはもぬけの殻だった。 その時、どこかで誰かが倒れる音と、男のわめき声が聞こえてきた。 周平が見たものは、廊下の脇に投げ捨てられたバスタオルと、押し倒された全裸のコフィと、 その上に圧し掛かる男の姿だった。 「コフィ!」 「・・・しゅうへい・・・周平! ゲホッ、ゴホッ・・・たすけ・・・たすけて! 周平!」 男は周平の姿を見ると、口元を抑えて走り出した。 逃げ出そうとしている。 「・・・この! 待て!」 周平は追いかけようとしたが、その周平をコフィが掴んだ。 「ケホッ・・・ゴボッ・・・ゴホッ・・・しゅうへい・・・」 良く見ると、コフィは全裸で・・・そして口元から多量の血が流れ出ており、その裸体を 赤黒く染め上げていた。 「コフィ・・・コフィ! しっかりしてコフィ!」 周平はそばにあったバスタオルをコフィにかける。 「あたしは・・・あいつが・・・ワケの分からないことを言いながら・・・ケホッ キスしてきて・・・それで・・・気持ち悪くて・・・思いっきり噛んで・・・そしたら、 血がいっぱい出て・・・」 コフィは震えている。 「じゃあ、この血は?」 「あたしのじゃ、無い。ケホッ、ケホッ、あいつの舌の血」 男の姿は、もう闇の向こうにまぎれて、見えなくなっていた。 「アルニーの所に行こう、コフィ」 「待って」 「どうして?」 「アルニーに、こんな姿見せたくない。アルニーに心配させたくない」 「・・・」 「あたしはシャワーを浴びて、血を洗い落としてからアルニーの所に行く」 「・・・」 「あたしがどこにいたのか聞かれたら、シャワーを浴びてたって言って。 知らない男の人が来ていたけど、それは周平が追い払ってくれた。 と、そう伝えて」 「わかった。じゃあ、とりあえずアルニーに連絡を入れる。コフィは無事だと伝えるけど、いい?」 「うん、それでいい」 僕とコフィはバスルームの前まで来た。 「周平、アルニーに連絡して、それが終わったら、あたしがシャワーから出るまでそこで待ってて」 「うん、わかった」 コフィがシャワールームに入った。 僕は2階に行って、アルニーの部屋に行く。 コンコン ドアをノックする。 「アルニー、僕だ、周平だよ。コフィの無事は確認した」 中からくぐもった声で「周平さん・・・?」と聞こえた。 ほんの少しの間が空いた後、ドアが開き、アルニーが出てきた。 「周平さん、あの、コフィは? コフィは何処に?」 キョロキョロと、アルニーがコフィを探す。 「コフィはシャワーを浴びてたんだ、無事だよ、今はそのままシャワーを浴びてる。 詳しいことはあとで話すよ。しばらくしたら、コフィと一緒にこの部屋に来ると思うけど ・・・いい?」 はい、待ってます。と、アルニーは言った。 僕はバスルームに着いた。 コフィに到着を知らせる。 「コフィ、僕だよ、周平だよ。今、アルニーに知らせてきた。アルニーは部屋にいるよ」 返事が無い、ただ、シャワーの水滴の音だけが聞こえる。 「コフィ、どうかした? なにかあった?」 コンコンと、シャワールームの戸を叩く。 「・・・しゅうへい」 コフィの声がした。 キュッと音がした。シャワーが止まって、辺りが急に静かになった。 「・・・しゅうへい・・・出る・・・」 「ああ、ごめん、僕は出るよ」 「だめ、そこにいて」 ガラッ! シャワールームの戸が開いて、そこから全裸のコフィが出てきた。 「コフィ! ちょ、ちょっと、僕はまだ出てない!」 「・・・見て」 「・・・?」 「あたしの身体に、血の汚れがないか、見て」 「あたしの身体に、1つの血の汚れも、残っていないよう、確認して」 コフィが裸体のまま、迫ってくる。 「コフィ・・・」 「汚れが残ったままじゃ、アルニーの前に出られない。お願いだから、確認して」 コフィは後ろ向きになった。前は自分で見られても、後ろは分からないわけだ。 「・・・大丈夫、綺麗だよ」 「ありがと、着替えるから、出てって」 「・・・うん」 僕はバスルームから退去した。 それから15分後、僕達3人は、アルニーの部屋にいた。 アルニーはさっきからずっとコフィを抱きしめたまんまだ。よっぽど心配だったのだろう。 そう考えると、コフィの心遣いは本当にありがたい。 もしもコフィが血まみれのところをアルニーが見たら・・・アルニーが失神する様が、 手に取るように想像できた。 「もう、いいでしょ、アルニー。くるしい」 「ふぅ、うぇ、グスッ・・・グジュ・・・コフィ・・・コフィ・・・良かった。 本当に良かった・・・」 アルニーはコフィをグニグニと抱きしめる。 それから5分ほどが過ぎて、ようやくアルニーはコフィから離れた。 「・・・周平さん、本当に、本当にありがとうございます。周平さんが居てくださらなければ、 今頃、本当にどうなっていたことか・・・」 「ありがと、周平」 「いや、いいんだ、とにかく、間に合ってよかった」 本当は間に合ってなどいなかったのだが・・・。 アルニーに侵入者等に関して、事情はある程度説明したものの、全ては語っていない。 コフィの意向もあるし、何より、これ以上アルニーに心労をかけたら倒れられてしまうのでは ないかというおそれもあった。 「コフィ、今夜はこの部屋で寝なさい。もう、何もないとは思うけど・・・心配だから」 「うん、分かった」 などと言っている。 コフィはそそくさとアルニーのベッドに滑り込んだ。 その横にアルニーが入る。 しかしなぜなのか、コフィはアルニーから少し離れて、2人の間に人一人分のスペースを作った。 「周平も、一緒に寝よ?」 などとコフィが言い出した。 「周平、聞こえなかった? ここ、ここに周平が入るの、3人で寝よ」 コフィが僕にウィンクして、手をヒラヒラさせてベットに呼び込もうとしている。 「ちょっ、ちょっとコフィ、それはだめよ」 アルニーが慌てふためく。 そんなアルニーを尻目に、僕は今後の行動を考え、まとめた。 「いいアイデアだと思うよ、コフィ」 「やったぁ!」 「ああ、周平さん・・・そんないけません、男女7歳にして同衾すべからずと昔から申しまして」 「なによ、アルニーだって、一人寝が寂かったんでしょ?」 「ああ・・・あああああああ」 アルニーはさっきから大忙しだ。 コフィを心配して顔を真っ青にしたと思ったら、今度は茹で上げられたみたいに顔を真っ赤に している。 「僕は、ベッドには入らないよ。そこの戸の横で寝る、心配だからね。毛布を持ってくる」 「ああ・・・そうしてくださると・・・助かります、ええっと・・・すみません、お願いします」 「つまんない」 コフィはふてくされたように眠りに入った。 この娘は、あんな目に遭いながらも、アルニーに気を使っているのだと分かった。 僕の申し出は、少しでも2人の心労をやわらげたいと思ってのことだったけど、 僕自身、なんだかこの夜は2人の側にいたい気もしていた。 AM 2:50 の電光表示が、腕時計と共に躍り狂う。 山道のどこか。 道の砂利に足をとられながらも、必死に走る男性の姿があった。 黒いジャージ姿をしているその男は、その手で自分の口元を必死になって押さえていた。 いたい、いたい、いたい、いたいいいいいいいぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ 多分、自分の舌には大きな傷が出来ている。出血が止まらない。 なんかおかしいぐらいに口から血が噴出す。 とにかく逃げる、一歩でも1mでもいいからあの館から離れる。 それからでないと、救急車は呼べない。いや、救急車を待っていられない。恐ろしいから。 そもそも、おそらく国道ぐらいには出ないと、こんな山道では救急車がこっちを発見して くれない。 男は走った。走りに走った。 しばらく走ると、街灯の下に人が立っているのが見えた。 そばに車もある。 男は人影を見て安心した。助けてもらおうと、近づいた。 もしかしたら、車で病院まで送ってもらえるかもしれない。 「こぼっ ごごぼぼ」 声がでない。 だが、異常事態には気が付いてくれるはずだ。男はそう信じて、街灯に向かう。 「・・・どうかしましたか?」 見たことの無いその人は、柔和な笑顔を浮かべている。 よかった、優しそうな人だ。何とかなる。そう思った。 「ごぼっ びしゃ、たしゅげで、ください、ぎゅうぎゅうじゃを・・・」 見たことの無いその人は、柔和な笑顔を浮かべている。 「おやおや、大変そうですね」 「だ、だがら、血が びしゃ 死んじゃぶ」 見たことの無いその人は、柔和な笑顔を浮かべている。 「死んだら、えらいことですね、困っちゃいますね」 見たことの無いその人は、柔和な笑顔を浮かべている。 「・・・だがら、どぶじてヒトの話を」 見たことの無いその人は、柔和な笑顔を浮かべている。 あきらかにおかしい。 その時、男は思い出した。 数日前に町内会の回覧板に乗ったマンハンター対策事項だ。 夜の夜中に出歩かない。・・・今は真夜中だ。 出歩くならば、複数人で。・・・オレは1人だ。 人目の及ばないところには決して行かない。・・・ここに人目は無い。 なにより、普段見かけない怪しい人には注意して。・・・こいつは、ダレだ。 見たことの無いその人は、柔和な笑顔を浮かべている。 「やれやれ、ダークエンジェルさん・・・でしたっけ。あなたは何をしているのですか」 男は懐から何かを取り出した。 手には軍手をつけて、ワイヤーのようなものを手繰っている。 「肉食獣から、獲物を横取りしようとするなんて、危険なことだと思わなかったのですか?」 街灯の下でワイヤーが光った。 後の事はもう、誰も見ていない。