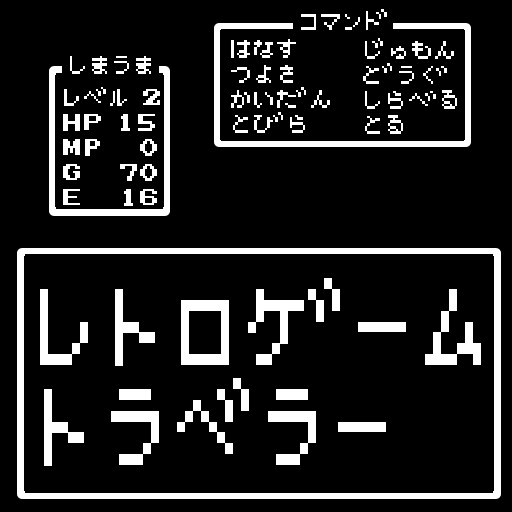マンハンター ジャコウアゲハの夢
4章 4月30日~5月2日
4月30日 日曜日 この日、生徒達の下校を確認した後、新沼は新任の枕下先生と町内の見廻りをすることになった。 本来は体育教師の島津先生と一緒に回る予定だったのだが、枕下先生が 『別の学校にいた時も私は見廻りをしていました。地域に早く溶け込みたいし、土地勘も得たいので やらせてくれませんか?』 と、言い出した。 島津先生はそれを聞き、 『殊勝な若者です。やらせてあげましょう』 と見廻りを譲った。 しばらくあちこちを見た後、2人は公民館へと寄った。 その横の体育館で、バスケットボールで遊んでいる生徒たちの声がした。 そこに、枕下と新沼がやってきた。 新沼先生が大きな声を張り上げる。 「おうい! おまえら、2年2組の生徒だな? 今日は、さっさと家に帰れと言ったじゃないか」 「ウィース。だから家に帰りましたよ。そんで時間も余ったしここに来ました」 先生達もやってこー と、生徒たちがバスケットボールを枕下先生にパスした。 枕下先生はすらっと背が高い。 身のこなしも軽いし、この運動好きの生徒たちは、枕下先生に自分たちに共通する何かを 感じたのかもしれない。 「まったく、いつまでも遊んでないで、なるべく早く帰れよ! 宿題も出てるんだろ!」 オース。と、気の無い返事。 それより先生! パスパスパース! と、騒いでいる。 ボールを手に、枕下先生が微笑んだ。 「どれ、しかたない、新沼先生、5分ほど貰えませんか?」 「ん? 枕下先生、バスケットボール、出来るんですか?」 「まぁ、少しは」 枕下はドンドンドンとドリブルを始めた。 そして、ドリブルしながらゆっくりと生徒たちに近づく。 「よし、少しだけ遊ぼう。誰か私を止めてみなさい」 枕下はドリブルをしながら生徒たちに向かって行った。 それから5分間、枕下はダンクシュートを3回、3ポイントシュートを3回決めた。 なお、3ポイントシュートは2回外した。 さすがにダンクシュートを決めたのには新沼も驚いた。 生徒たちは『うわっ、まじかよ』とか『背が高いからかねー』とか言っていた。 無論、上背だけであんなことは出来ない。 相当なジャンプ力や運動神経の持ち主であることは確かだ。 「枕下先生、もっとやっていこうよ」 と、生徒の一人に止められたが 「今は見廻りの途中です。みなさんも、余り遅くならないうちに帰宅しなさい」 そう言って、枕下はその場を去る。 新沼もそれに続く。 枕下が体育館を出た後、新沼は声をかけた。 「いや、たいしたもんです。学生時代はバスケを?」 「いえ、遊びで少々」 おいおい、遊びでダンクはねぇーだろ、と新沼は思った。 「学生時代は合気道をやっていました。いろんなスポーツを嗜むと学ぶことが多いと 師匠に言われまして、それでいろいろなことをやりました」 「ははは、それは頼もしい。私なんぞ、学生時代に柔道をやっていたぐらいですからな」 「おや、そうですか、これは心強いですね。もしもマンハンターを見つけたりしたら、 2人で捕まえることも出来るかもしれませんね」 「うむ。そうですな、しかし過信は禁物です。枕下先生、無理をしないように」 「ええ・・・すみません、軽率でした。でも、私はいつも、それぐらいの気持ちで見廻りを しています」 「ふふ。これはいい新任の先生が来たもんです。枕下先生はいい拾い物ですな、どうです? 今夜あたり着任祝いに一杯行きますか?」 「はい、お手柔らかにお願いします。実はアルコールには弱いもので」 ・・・暗闇に沈む自分の巣で、ノートパソコンの電源を入れる。 一通り、プログラムがネットを巡回してくる。 出てきた新しい情報は15件。 マンハンターは、場所によっては、ちょっとしたダークヒーローだ。 少し前に、冗談で犯行写真をネットに出したところ、一部の人々から圧倒的な支持を受けた。 今では、彼らのようなマンハンター支持層は、少なからずマンハンターの力になっている。 特に、情報収集という面においては、彼らはなかなかにやり手だ。 今回の獲物もそうだ。 日月アルニー 日月コフィの双子の姉妹。 始めて見た時、とてつもない興奮が全身を駆け巡った。 なんという幻想的なまでの美しさか。 白子・・・アルピノというものが、世の中にあるのは知っていた。 だが、この2人は違うらしい。 原因が何なのかはよく分からないが、確かに白さが目立ちすぎる。 ラードのような白さだ。アルピノではない、と言われればそうだと気づく。 これは、色素がどうこういう話ではない。まるで白い色素でもあるように2人は白い。 しかし、元々が美形の上に、この色白だ。 人間というよりも、妖精や女神のようにしか見えない。 ヨダレが垂れる。呼吸が荒くなる。欲望が止まらない。 あの白い腿に喰らいつきたい。きっと、マシュマロよりも柔らかいだろう。 そして、その甘い肉は、上等な生クリームみたいに芳醇に香る脂がのっているだろう。 もしかしたら、噛まないでも舌の上でとろけるかもしれない。 声はどうだ。 ネットで拾ってきた声を再生してみる。 やばすぎる。これは聞く麻薬だ。止められない。 こんな声で、悲鳴を上げられたらどうする。自分は自制心が強い人間だと思っているが、 きっと耐えられない。そうだ、悲鳴を全部、ウェーブデータにして録っておこう。そして、 ずっと聞き続けるのだ。 そして、なにより、あの白い背中はどうだ。 美しすぎる。ああ、自分はこれから、あそこに牙を突き立てるのだ。この歯型が、あの背中に 刻み込まれるのだ。 ・・・そうだ、なんと言うことは無い。やはり、ネットの連中の言うとおりに、行為の状況を 全て、動画にして撮っておこう。 それでいい。それがいい。なんという素晴らしいアイデアだろう。 この妖しいまでに美しい姉妹が、考えられるうる限り、もっとも残酷な方法で殺される、 その数時間の至高の芸術を、余すところ無く、一部始終、撮っておく。 そしてそれがデジタルデータとなって、半永久的にネット上を飛び交うのだ。 これから10年、100年間、人々は、この美しい姉妹の惨劇を楽しむことが出来るのだ。 まだだ、まだ・・・これほどの仕事だ、未来の為に確実にこなそう。 まだ、情報が必要だ。こういうことは、一切の証拠を残さないで事を始末せねばならないのだから。 -------------------------------------------------- ◆ 5月1日 -------------------------------------------------- 5月1日 月曜日 『*マンハンター様支援係ホームページ*』 『マンハンターに殺させたい奴ら』 『マンハンター様に、殺して欲しい人間を募集しています』 『マンハンターさん、こんな人間、おいしそうでしょ? 喰って写真をみんなに見せて!』 NEW 4月30日アップ 「木鹿毛町(匿名の情報により、このかげと読むと判明)にて、例の姉妹の新情報が投稿された。 以下に、いくつかの映像を出す」 3960×2160 動画 ここをクリック 提供者 ダークエンジェル 映像が始まる。 BGMは存在しない。ただ、夜の夜中の、風の音だけがする。 レンズが見張るのは一個の窓。 カメラは固定されているのか、時折、風か何かでぶれる以外、鮮明な画像を取り続けている。 レンズは、窓から部屋の中を、その部屋のあるじである1人の少女を覗いている。 少女は髪も肌も、何もかも白い。夜の闇に浮き上がる、幻想のような白い肌。 少女がけだるい様子で着替えを始める。 ワンピースを落とした瞬間、少女が真っ白に見えて、まるで裸のように思えたが、 ただ単に、白い下着と肌着が、肌と一体になって見えただけだった。 少女はネグリジェに着替えた後、ベッドに横になった。もう何も見えない。 映像はここで途絶えた。 3960×2160 動画 ここをクリック 提供者 ダークエンジェル 映像が始まる。 BGMは存在しない。ただ、風の音が、かすかに聞こえる。 レンズが見張るのは一個の窓。 昼の光に照らされて、本当に爽やかな時間のはずなのだが、そんな爽やかさを完全に破壊するかの ような、陰湿な映像である。 カメラは固定されているのか、時折、風か何かでぶれる以外、鮮明な画像を取り続けている。 レンズが見ているのは一組の姉妹。 2人とも、病的なほどに白い。 1人はイスに座って、もう1人はイスの後ろに立って、相手の髪をブラシですいている。 ブラシを手に持つ少女は、柔らかな慈愛の視線を、もう1人の少女に向ける。 髪をといてもらっている少女は、ただ虚ろな感じに、けだるそうにどこか中空を見つめている。 そのシーンが5分ほど過ぎ、映像は途絶えた。 「情報によると、この2人は姉妹。しかも双子。マンハンター様、双子って、肉の味も一緒なので しょうか?知りたい所です」 「いやー 美味そう。 ある意味、オレがクイテー」 「まじ、いいって。撮ったオレが言うのもなんだけど、マンハンター様に捧げるのがもったいない かも(笑)」 恐ろしさと怒りと、とにかくなんとも言いがたい感情が高ぶり、震えが来た。 僕は、アルニーの家から帰ってきたあと、また何気なくインターネットで マンハンターに関する新しい情報が無いものかと探していた。 そして、この情報に出くわした。 今まで僕は、こんな風に他人をさらし者にするところを見たことはあった。 けれど、酷いことをするとは感じたものの、正直言って他人事のように感じていた。 だが、今回は肌身にしみて分かる。 これは、恐怖でしかない。 人間という生き物が、人を獲物として狩りたてようとする意思。 徹底した無邪気な悪意。悪いことをしていると、当の本人達は、まったく感じていない。 感じていないからこそ出来る行為。 例え、どう転ぶにせよ、アルニー達に何らかの危害が加わる事態になる。 (既に、彼女たちは被害者と言ってもおかしくは無いだろう) 彼女たちに危険が及ぶ可能性は、極めて高いと思った。 実際には、彼女たち姉妹以外にもこうやって『晒されている人』は多いのだが、 それでも何か、僕は不気味な予感を抑え切れなかった。 -------------------------------------------------- ◆ 5月2日 -------------------------------------------------- 5月2日 火曜日 今日も学校は普通に終った。僕は帰り支度をする。 今日の授業は、いつもの半分の集中力でしか聞くことが出来なかった。 アルニーやコフィのことが気になっていた。 だが、僕に何が出来るというのだろうか、そんなことをずっと考えていたように思う。 そこに、水岡が話しかけてきた。 「ちょっと間宮。あんたにお客さんだって。職員室に来いって新沼先生が伝えてって」 「僕に客?」 「そう。先生曰く、『髪も肌も真っ白いのが来てる。とにかく周平に会わせろと言って聞かない』 とか言ってた」 アルニーだろうか? いや、違うな。アルニーなら、ちゃんと用件を伝えてくる筈だ。 そうなると、コフィのほうだろうか? 「わかった、行ってみるよ」 僕は職員室に向かった。 職員室には来賓用の部屋がセットになっていて、僕のお客さんは案の定、そこに居た。 「周平。やっときた」 外見はアルニーとそっくりながらも、まったくもってけだるい空気しか発散しないこの娘は、 間違いなくコフィだろう。 「おお、間宮。やっときたか」 コフィの向かいには新沼先生が座っている。 先生はなんだか『解放されたー!』っという感じの顔で僕のことを見ている。 「いや参ったよ。こちらのお嬢さんがいきなりやってきたな、『周平に会わせろ』の一点張りでな」 「どうもすみません先生。その娘は僕の知り合いの妹でして」 「おお、そうかそうか。いや、まぁ、それじゃ、間宮は来ましたから。私はこれで失礼しますので」 新沼先生はバタバタと立ち上がると、急いでどこかに行ってしまった。 「周平。聞いて欲しいことがある」 コフィは単刀直入に発言する。 「周平に、アルニーを助けて欲しい。アルニーは、本当は周平に助けて欲しい。 でも、アルニーはジョーシキがドーとか言って、周平に話をしたくないって言う」 「えー・・・と」 それはどういうことか。まさか、あのインターネットの情報のことだろうか? 「とにかく、周平にすぐにでもうちに来て欲しい」 「いますぐ?」 「いますぐ。そうしないと、アルニーはきっと、もっと大変になる」 「あら? 周平さん、いらっしゃい。あらら・・・?」 コフィに連れられて、僕はあの白樺の丘の館に到着した。 時刻は既に夕方で、辺りは朱色に染まり始めていた。 そしてどういうわけか、庭にアルニーが出ていて、すぐにコフィと僕をを見つけた。 「コフィ? さっきまであなたをずっと探していたのよ? どこに行っていたの?」 アルニーは何事も無いように振舞う。 だが、コフィは、そんなアルニーの振る舞いを跳ね除けるように喋る。 「アルニー、周平は、インターネットの、アレ知ってる。それでアルニーを助けるよう、周平に 頼んだ」 コフィは、いつもの数倍は頑張っているように見える。 「周平なら、助けてくれる。アルニーを助けられるのは、周平だけ。 あたしと一緒にここに居られる人は、周平だけ」 コフィは言い切った。 アルニーは黙り込んだ。 なんだか、親に叱られている子供のようだ。 「コフィ・・・」 「決めるのはアルニー。あたしは決められない。じゃ」 コフィは一通り喋り終わったらしく、いそいそとどこかに行ってしまった。 「アルニー」 僕は意を決して言った。 「ネットのアレ、昨日の夜に見たよ。さすがにアレは、冗談ごとじゃ済まない」 僕はたたみ掛けるようにして言う。 「アルニー。僕に出来ることがあったら、何でも言って欲しい。出来る限りのことをしたい」 「周平さん」 アルニーは、まだ喋ろうとする僕の言葉を止める。 「周平さん・・・うっ・・・ぐすっ・・・」 アルニーは泣き出した。 いや、僕は今気が付いた。 彼女はついさっきまで泣いていたのだ。いつもより赤い目と、 いつも以上に青白くなった顔。腫れぼったいまぶた。 そして、手に握られた濡れたハンカチ。 「わたし・・・わたし・・・! 昨日まで、昨日まで、家の周囲のどこを見ても、あんなに 綺麗に見えていたのに!これからの、この家での、この町での生活が、とても楽しみだったのに! たった、たった一晩で全ては変わってしまった。怖かった・・・怖くてたまらなかった!」 アルニーは、芝生の上に泣き崩れた。 「昨日の夜・・・わたし見ました。あのホームページを・・・この世界に・・・世の中に、 あんなに悪意を持った人がいて、それも、わたしのすぐ傍まで来て・・・部屋の中まで 撮られていたなんて・・・」 アルニーは泣く。ただひたすら、そのクリームみたいな肌が夕日の熱で溶けてしまうのでは ないか、そう思えるくらいに泣く。 「さっき、コフィを見かけなくなって、そして・・・わたし、コフィが悪い人たちに連れて 行かれたんじゃないかって、コフィが、コフィが酷い目に合わされていたら、どうしようって・・・ 必死になってコフィを探して、でも、自分が家から出ることもひどく怖くて・・・」 「怖い・・・怖いの! 周平さん。怖い・・・こわいよぉ・・・う、うぇ、うぇぇぇん」 子供のように、身をかがめ、泣きじゃくるアルニー。 僕は、そんなアルニーの肩に、そっと手を置いた。 「・・・ごめんね、アルニー・・・実は、僕、結構前にあのホームページを見つけていて、この前 会った時に話せばよかったんだ」 「ううっ・・・グスッ・・・いえ、周平さんのせいではありません。悪いのはあの人たちであって、 周平さんはまったく悪くありません。・・・そうだわ、グズッ・・・コフィも叱っておかなくては、 せめて書置きぐらい置いていってくれれば、わたしももう少し気が楽だったのに」 「うん、そうかな、そうかもね」 少しして、アルニーは泣き止んだ。 アルニーは立ち上がろうとしたが、足に力が入らなくて上手く立てなかったので、僕が手を差し 伸べた。 「ふふっ、わたし、なんだか童話のお姫様みたいですわね」 「・・・おおーい、アルニー」 コフィの声だ。コフィが館の上のほうの窓から顔を出している。 「お爺様のあれ、周平にも見てもらおう」 ?お爺様のあれ。とは、何だろう? そう言えば、コフィはさっき、よく分からないことを 言っていた。 あたしと一緒に暮らせるのは、僕だけとか・・・どういう意味なのだろう? 「でも、コフィ、あれは・・・周平さんの重荷になるから・・・」 「そんなこと、言ってる場合じゃないわ、アルニー。あたし、メソメソ泣くアルニーと、 一緒に居たくないの。準備して、待ってる」 コフィは顔を引っ込めて、窓を閉めた。 その様子を見て、アルニーは何かを決心した様子だった。 「あの・・・周平さん」 アルニーが恐る恐るといった具合に喋る。 「見て欲しいものがあります。部屋に来てくださいませんか」 アルニーに連れられて、館の中のある部屋に入った。 そこは書斎のようなところだった。AV機器も設置してあり、ホームシアターと言っても いいぐらいの設備がある。 用意したのはコフィだろう。だが、彼女はここに居なかった。 アルニーが機器の電源を確かめ、リモコンで何かを操作する。 そして大型モニターに、映像が映し出された。 「周平君には申し訳ないと思うのだが、この館に住んで頂けないものだろうか」 それは、一通の動画レター。 そこに写っているのは、70歳近いと見られる男性。 男性の顔には、苦悩の色がありありと見えた。 「話はアルニーに聞いた。あんなに悲しげなあの子を見たのは、本当に久しぶりだった。 本来ならば数少ない肉親である私がそこに行かねばならんのだが、ワシも病が重く、動くに 動けんありさまじゃ」 そこで、画面の老人は少し間を置いた。 「それに・・・アルニーはまだいいのだが、問題はコフィにある。あの娘は・・・祖父である ワシが言うのもなんだが、あまりにも人見知りが激しい。正直なところ、何処の病院に入れても、 ほとんどアルニーが1人で面倒を見ていたようなものなのだ。医者も看護士も、さらには ボディーガードも、誰をつけても近づけようとしない・・・。 本当に、今の今まで、祖父である私も含めてだ。・・・君とアルニーと両親以外の人間に、 コフィは心を許さなかった。 無理なお願いとは承知している。だが、どんな娘であろうとワシの孫だ。 ワシは2人が心配なのだ。 周平君。私からも頼む。どうかこの通りーー」 その初老の老人は頭を下げた。 相手がどんな人なのかは僕は良くは知らなかったが、その行為の意味がとても重いのは理解できた。 「この館に住んで、2人を、アルニーとコフィを守ってやって欲しい。 ワシには、もう、何の力も無い。はっきり言って、その屋敷を2人に残すことだけが、ワシに 出来る精一杯の事だったのだ。いろいろな全ての手はずは私が整える。重ねて頼む。2人を 守ってやって欲しい」 アルニーは不安げな目で、僕のことを見つめている。 「周平さん。この祖父の願いが無理なお願いであることは承知しています。 ・・・いきなりこんなことを頼むという事が、非常識であるということも承知しています。 ですが、それを分かった上で・・・わたしは周平さんに、ここに居て欲しいと考えています。 わたしからもお願いします」 アルニーが、そっと僕の手をとった。柔らかくて細長い手指が、僕の手を弱々しく掴む。 「はっきり言って、わたし1人の力では、無理なのです。コフィの面倒を見るぐらいなら、 どうとでもなったのです。けれども、これほど恐ろしい事態になってしまっては、わたしは・・・ わたしでは・・・もう、どうにも・・・ただ、ただ、怖くて・・・恐ろしくて・・・グスッ・・・ ウッ・・・」 アルニーが泣く。その蝋細工のような白い肌に涙が流れる。 僕の心は決まっていた。 「アルニー・・・分かった。僕は・・・その、アルニーがもういいよって言うまで、ここで キミ達と一緒に居ることにするよ」 「周平さん」 アルニーが流す涙の量がますます増えた。 「僕でいいのなら、僕がここに居る」 「周平さん!」 アルニーが僕の胸に飛び込んできた。 彼女は、その華奢な体を僕の胸にうずめる。 真珠色に光り輝く彼女の髪がサラッと流れる。こんな時になんだが、とても綺麗だと思った。 彼女の髪から、何かとてもいい匂いがした。 「周平さん、周平さん・・・良かった・・・良かったです。わたし、わたし、周平さんに 断られたらどうしようって、本当に、生きた心地がしませんでした」 アルニーの指が、僕をしっかりと掴む。 まるで僕を放すまいとするかのように。 「ごめんなさい、周平さん、ごめんなさい・・・わたしが、わたし達が、周平さんの生活を 壊してしまうかもしれない。でも、本当に・・・わたしは・・・周平さんにこうしてすがる 以外に、方法が無いのです・・・ごめんなさい」 「アルニー・・・」 僕は、少しだけ戸惑いつつも、アルニーの体を抱きしめた。 アルニーの真珠色の髪はサラサラと柔らかくて、 アルニーの身体は、本当に細くて華奢で、思ったよりも小さくて・・・とてもいい香りがした。 「周平さん・・・」 アルニーが僕の腕の中で、とても安らいだ表情をしている。 「あの・・・すみません、もう少しだけ、もう少しだけ、このまま、抱きしめていてくれませ んか。こんなことをしていると、コフィに嫉妬されてしまうかもしれないけど、でも、今だけ、 今だけここで、こうしていて下さい。周平さん・・・」 同時刻 木鹿毛町の公園 「やあ、今日は本当にありがとう。おかげで助かったよ」 公園には3人の人物がいた。 1人は水岡聡子、もう1人は彼女の友人のえっちゃん。 もう1人は新任の先生の枕下先生だ。 枕下先生は近くの自動販売機でジュースを3本買ってきた。 1つはオレンジジュース、1つはコーヒー、1つはサイダーだ。 「何がいいかな? なんだか良く分からないから、適当に買ってきてしまったけど」 枕下先生は少し恥ずかしそうにして2人の生徒にジュースを差し出した。 「はい、なんでもいいです。頂きます」 えっちゃんがジュースを受け取った。オレンジジュースだ。 聡子はサイダーを選んだ。 理由はひとつ、サイダーは500mlでコーヒーは250mlだったから。 「じゃあ私がコーヒーを貰うね」 枕下先生はそう言うと、公園のベンチに腰掛けた。えっちゃんの横しか空いていないので、 自動的にそこに座ることになる。無論、聡子が気を使った上での配陣だ。 えっちゃんの足が短いせいなのか、枕下先生の長い足が妙に浮いて見えた。 「あの、あの、先生。今日のわたし、先生のお役に立てましたか?」 えっちゃんが言う。 「はい、本当に助かりました。あなた達のおかげでこの町のいろいろなところを見て回ることが 出来ました。これで、これからの見廻りにも臆することなく参加することができます」 枕下先生は微笑んだ。 「今日はいろんな所に行ったね、さと」 えっちゃんが言う。 「うん、この辺のところは大体案内したね、あとは山道とかぐらいかな」 本当ならば、誰か先生が枕下先生を案内するはずだったのだ。 それがえっちゃんの野望のために(先生に近づきたい)今日の放課後はまるまる使ってしまった。 「山道ですか? ・・・そうですか、それはあとで誰か別の先生に案内してもらったほうがいい ですかね」 「いえ、道はそんなに複雑じゃないです」 えっちゃんが続ける。 「あの白樺の丘の上には洋館が一軒あるだけだし、他の道も大体が一本道で、登山ルートか 別の国道に出るわき道くらいです」 「なるほど、そうですか」 先生がえっちゃんに少しだけ笑いかけた。 水岡はそれを見て、まるで女でも口説くみたいな顔だと思った。 「はい、先生。・・・あの、見廻り、気をつけてくださいね」 えっちゃんは先生のことを本当に心配しているようだ。 「ありがとう。絵津子さん。・・・さぁ。ジュースも飲み終わりましたね、それでは、今日は ここまでにしましょうか」 枕下先生がベンチから立ち上がる。背が高くて、見下ろされると少し怖いくらい。 隣ではえっちゃんが、そんなノッポの先生に『乙女の憧れ光線』をビシビシと発射している。 「お家はどこですか? 送りますよ」 先生が言う。まるで小さな子供を相手にしているような言い方だ。 「いえ、いいです、結構です」 聡子の自分の家は、すぐそこだ。 「先生はえっちゃんを送ってあげてください」 聡子はその場を去った。2人のお邪魔虫は、この辺りで退散だ。 さてそれでは、これからこの日月家の、安全保障会議である。 場所は2階の書斎、会議に出席するのは3人。僕とアルニーとコフィだ。 「とりあえず周平さんに、この家の保安体制に関して説明させていただきます」 妙に力の入ったアルニーが、家の見取り図に手をのせる。 「とは言っても、そんなに大層なセキュリティーは存在しません。 敷地をグルッと囲む鉄の柵と、地雷タイプのアラーム装置、それにセーフティールーム、ここと、 ここと、ここと・・・それと・・・」 アルニーが何かのスプレー缶を取り出す。 「この護身用の痴漢撃退スプレーが、全てです」 「これだけ?」 「この家にある物は、です。さらに、ボタン1つで民間警備会社の方に緊急コールをすることも 出来ます。このコールは連絡した後、およそ30分でこの家に警備員の方が来てくださいます」 「30分か・・・」 「これでも随分、無理をしてくださっている・・・と、伺っています。基本的には何かあった 場合・・・家の中のアラームを鳴らしてそれぞれが最も傍にあるセーフティールームに入るか・・・ 家から逃げるか、と、なる・・・と、お爺様から聞いています」 「ねぇ、アルニー」 「なに、コフィ?」 「セーフティールームって、なに?」 「ああ・・・もう、3ヶ月前に説明したじゃない」 「忘れた」 「はいはい・・・セーフティールームというのは、自分たちに危険が迫った場合に、逃げ込む 避難部屋のことよ、あなたの部屋にもあるでしょう?」 「ああ、あれ、あの狭いやつ」 「まぁ、狭いわね」 「あんなので、大丈夫なの?」 「業者の人は拳銃やバールくらいなら大丈夫とは言っていたけど・・・」 「バールって、なに?」 「ええっと、バールというのは・・・」 アルニーが説明している。コフィがトロンとした顔で聞いている。 「はい、これで分かったわね?」 「うん、なんとなく」 「ふぅ・・・」 アルニーが一息つく、いつの間に取り出したのか、メモ帳の紙に何かの絵が描いてある。 ・・・バールの絵だ。 「それでですね、周平さん。そうは言っても、結局の所、もっとも良い安全対策は 『人の目を増やす』ことだと警備会社の人から聞きました」 「『人の目』?」 「はい、そばに居る人を1人でも多く増やして、人が危険を感知する確率を、少しでも上げる事 が大切なのだそうです」 「なるほど」 「コフィもわたしも、どちらかというとそれほど健康ではないので・・・周平さんのような人が 居て下さいますと、居ない時に比べて2倍くらい、危険を感知できる確率が高くなると思います」 「ちょっと、買いかぶり過ぎかも」 「いえ、それになにより男の人がいるといないとでは、犯行を犯す側の心理に、それを大きく 抑制する働きがあるとも、聞いています」 「うん、分かった、頑張ってみるよ」 「それでは、これをお持ちください」 そう言うと、アルニーは痴漢撃退スプレーと、ペンダントを取り出した。 「このペンダントに、危険を知らせるボタンが付いています。何かあったら、これを押して ください。・・・女物で恐縮ですが、これしかないもので・・・ 裏にあるボタン・・・ええ、それです。それを押してくださいますと、わたしにもコフィにも、 すぐに危険が知らされます。 わたし達も同じ物を持っています。わたし達も何かあったら、このペンダントを振動させます」 この後、幾つかの器具の使用を練習したり、地雷タイプのアラーム装置とか言う物のことも 教えてもらった。 このアラームは『踏んだものには何にでも反応する』物だそうで、『逆に言うと、踏まなければ、 象にも反応しない』と、アルニーはあまり期待してはいないようだ。 「この前は野良猫にも反応しまして・・・それに、どうしてもピンポイントでの感知になり ますので、アラームのスイッチがあるところでコフィが2時間くらいうろうろしても、 一向に反応しないときもあったし・・・」 などと、ため息交じりで説明してくれた。