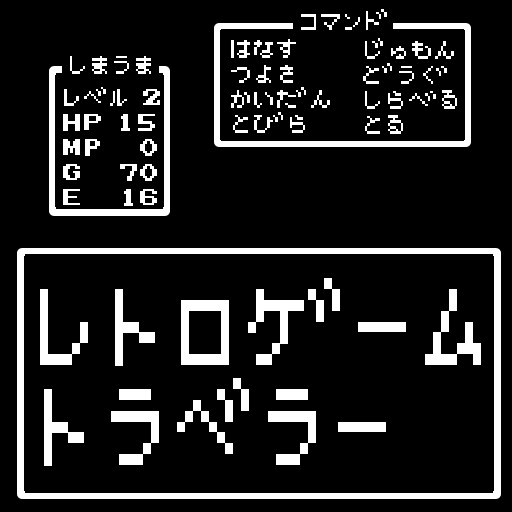マンハンター ジャコウアゲハの夢
3章 4月29日
4月29日 土曜日 僕の目の前にあるその門は、思った以上に質素なものだった。 この日、僕はアルニーの家に、予定通りに遊びに行くことにした。 女の子の家に遊びに行くなんて、数年ぶりかもしれない。 前に来たときは妖精探しの探検隊であったわけだが、今度は、この白樺の丘に招待客として 招かれたわけである。 幅3mほどの砂利の道路の途中、白樺の並木が続く途中に急な曲がり角があって、 そこをひょっと超えると、その門(と柵)は突如として現れた。 なんということもなさそうな雰囲気の、鉄の柵に鉄の門扉であったが、そこにある立て札? らしき物に 『この先、私有地。当家に用事があるお客様は、こちらのマイクでアポイントメントの内容を お伝えください』 という注意書きらしきモノがあり、妙に威圧感を持っていたりもする。 とりあえず、ここでジッとしていてもしょうがないので、僕は『この先アポマイク』 (僕が勝手にそう呼ぶことにした)のボタンを押してみる。 音は「ピンポン」という感じの、まことに普通のものだった。 「はい、日月です」 誰かが応答に出る。声はアルニーだった。 「えーと、間宮です。間宮周平です。あーと、遊びに来ました」 「まぁ、来て下さったのですね? お待ちしておりました周平さん。すぐに門を開けますので、 そうしたら中に入ってきてくださいな。わたし、途中から迎えにあがりますので、すぐに 会えると思います」 「わかりました、それじゃ」 「はい、では」 マイクの向こうの方で何かしたのだろう。 ガチャ、カチャカチャカチャカチャカチャ、チャン と、鉄の門は開いた。 早速中に入り、また、僕は歩く。 中に入っても、それほど視界に入る風景に変化は無い。 しばらくすると白樺の林を抜け、日の光が差し込む広い空間が見えた。 その空間に、白い壁の綺麗な洋館が見えた。 館の周りには花花花。一面に甘い香りを漂わせる花が咲いている。 そして、その花に包まれるようにして、白い少女が、1人、立っていた。 「こんにちわ」 挨拶した。だが、返事が無い。 「・・・」 「あの、アルニー・・・? だよね」 少女はぼんやりとした目で僕のことをジッと見つめた後、スタスタと早足で近づいてきた。 少女は手を僕の方に伸ばして、結構な早足で接近してくる。 相手と友好を深めようとしている・・・と言うよりも、相手を捕まえようとする仕草に 見えた。 少女はズンズンと僕に迫り、・・・僕の頬に両手を添えた。 顔を固定されている、とか、頭を両の手の平で押さえていると言う感じ。 「あ、あの・・・」 いきなり何を・・・と言おうと思った瞬間、少女は僕の顔を自分に引き寄せ、自分は背伸びを して来る。 少女の愛らしい顔が来る。 少女の柔らかい唇が、僕の唇と重なった。 キスされた。 キスされてしまった。 それも「チュッ」等という物ではない。 ムチュウ~っと言う感じ。 いや、そうだ、キスと言うよりも、舌と唾液を吸い込むようなキスだ。 チュッという音がして、少女の唇が僕から離れる。 僕の唾液が少女の口元に垂れ、それを少女はペロッと舌で舐めて回収する。 「ふふっ、周平・・・」 少女が笑う。「楽しい」というよりも「嬉しい」というよりも、もっと別な感じの笑い方 だった。 「あ、あの? アルニー?」 「ふふ、くすくす」 「あ、あなた達! な、何をしてるの!」 そうしていると、上の方から声がした。これは、確かアルニーの声だ。 ? じゃあ、この目の前の女の子は? 「コフィ! そこにいなさい!」 しばらくして、アルニーがやってきた。 「申し訳ございません。周平さん、・・・紹介します。この子はコフィ。日月コフィと言って、 わたしの双子の妹なんです。コフィ? 周平さんにご挨拶を」 「・・・周平・・・よろしく」 その少女、コフィはそう言い終わると、そそくさとこの場を離れてしまった。 僕はその小さな背中を見送った。 「本当にすみません、周平さん。あの娘・・・その、エキセントリックな所があるというか・・・ その、はっきり言うと心に問題があって・・・あの、でも、いい娘なんですよ。あんな事、 急にするから、ハッと見た時にビックリしてしまって」 アルニーは『あんな事』のところで顔を真っ赤にした。 肌が白い為か、一度染まった色は、そうそう無くならなかった。 「もう、どうして急にあんなことするのかしら」という、呟き声が聞こえた。 「ううん、いや、こっちとしては問題ないのだけど」 「ああ、そうそう!」 アルニーが話題を変える。 「そう言えばあの、周平さん、お昼をご一緒にいかがですか? あの、わたしパンを焼きました。 席も作ってありますので、どうかと思ったのですが」 僕はアルニーに連れられて、館の中に入った。 こういう物の価値とかは良く分からないのだが、おそらくかなりの手間と建材の費用が、 つぎ込まれた館であろう事は分かった。 「ふふっ、この家、大きいばかり大きくて、そのうえ古いでしょう? 管理が大変なんです。わたしにとっては想い出がいっぱいある大切な家なのですけど 時には自分で掃除もしますが、やっているうちにげんなりしてしまいます」 館の廊下を歩く途中、アルニーは時折あちこちを撫でて回る。 良く見ると、そこそこに小さな傷があったり、石材が欠けていたりする。 「それでも」 僕は言った。 「アルニーにとっては、大切な物なんだね」 「ええ、とても大事な家です。わたしにとっても、コフィにとっても」 さて、そうしているうちに館の中庭に出た。 そこには白いパラソルで飾られたランチの席が設(もう)けられていた。 アルニーはいそいそとそこに近づくと、籐で編まれたバスケットを開け、パタパタと 食べ物やら飲み物やらを並べ始めた。 「さ、どうぞ周平さん」 お呼ばれして、僕はイスに座る。 テーブルの上には様々な食品が並んでいる。 バターロール、クロワッサン、サンドイッチにクッキー・・・ 紅茶にコーヒー、オレンジジュースにサイダーもある。 どう見ても3~4人分はある。 「あの、周平さんが、どんなものが好きか分からないので、いろいろと用意したのです。 お口に合えば良いのですが」 なるほど。 「そうですね」 心地良い春の日差しの中、アルニーの話は続く。 「わたしの家はお金持ちですけど、わたしは・・・いえ、わたし達はお金持ちではないです。 お爺様の指示に従ってこの館を相続しましたけど、財産の大部分や館の管理費用等は わたしが満25歳になるまで、お爺様の選んだ後見人の人が毎月、振り込むことになって いるんです。おかげで大変です。本当なら住み込みで働いてくださる人を雇いたいのですけど」 「それでも、この館はアルニーの物なんだ?」 「一応、建前の上ではそういうことになります。本来は、他の人が貰うはずだったのだ そうですが」 「他の人が? それじゃまた、どうしてアルニーの物に?」 「それは・・・その、わたし達の肌の色と、妹の、コフィの心の問題がありまして」 「ああ、ごめん。込み入った話だったのかな」 「いえ、いいんですよ、別に聞いてもらっても。あの・・・ですね周平さん。 周平さんはわたしの肌や髪が真っ白なのを見て・・・『気味が悪い』とか『不気味だ』とか、 思ったことはありませんか?」 「いや、そんなこと、まったく思ったことはないよ」 むしろ、美しいとさえ思った。 「よかった」 ふぅ、と、アルニーが安堵のため息をつく。 「周平さんは、私のことを、アルピノ・・・白子だと思いましたか?」 「え、うん・・・」 違うのだろうか。 「見てください。私の肌の色」 アルニーはそういうと、腕をスッと差し出してきた。 白い。本当に白い。ペンキみたいな白じゃないけど。人間とは思えないほど白い。 白いシーツとか、いいや、ゆで卵の白に近いかな? 「私はアルピノではないのです」 「へ?」 「母も、最初はそう思っていたらしいのです。けれど、調べてみたら違っていたとのこと でした。私も実際にアルピノの方と会ったことがあるのですが、こんなに白くはないよう です。全ての方がそうではないと思いますが、私が出会った方は色素がないだけですので、 もっとピンク色に近い肌の色をしていました」 アルニーはうつむきながら喋った。 「アルピノの方は、私とは違う、もっと生き生きとした肌をしていらっしゃいます。 私は本当に白くて、白過ぎて、自分でも嫌になるのです。どうしてこんなに白いのでしょう。 せめてアルピノの方と同じであれば、気が楽だったでしょう。けれど、私はもっと別の、 正体不明の理由でこんなにも白い」 「そんなに、自分を卑下することないよ。キレイな白だよ」 「ありがとうございます。 周平さんのような方ばかりだと、本当に助かるのですけど、やっぱり、わたしやコフィは世間では 目立つのです。 ただでさえ目立つ上に、妹の療養の事を考えると、やはりこの木鹿毛町のような都会から離れた、 自然がいっぱい残っている場所でゆったりと過ごすしか無いものだから。 それでお爺様は、わたしとコフィに、わたし達が幼い頃に居て、住み慣れていたこの家をくれたん だと思います」 「なるほどね」 「つい最近まで、わたしはコフィの治療の為もあって、あの娘の入院暮らしにもついていて あげなくちゃいけなかったし、コフィの容態も、最近はすごく安定してるし、それに幼い頃に 住み慣れたこの家に戻ってこられて・・・わたし、本当に嬉しかったんです」 アルニーは微笑む。白い頬が、喜びの朱で染まる。 「大変だね、でもさ、アルニーがコフィの入院についていてあげてるって、親はどうしてるの? どっか、遠い外国とかでお仕事?」 アルニーは優しく微笑んだまま言った。 「両親は、だいぶ昔に亡くなりました。事故だったんです。それで、その時にコフィは心を 患ってしまって。それを期にです。わたし達はここを離れたんです」 「ごめん、そうだったんだ」 「いえ、周平さんが気になさることではありません。まぁ、そういうことがいろいろあって、 引越しが決まったちょうどその頃に、わたしは周平さんと、あの森で出会ったわけですね」 「うん」 「それで、わたしにはあの出会いが心に深く刻み込まれまして、それでです。 名前も分からない男の子の事を良く覚えていたんです」 あら、飲み物を注ぎますね。と、アルニーは紅茶のお替りを入れてくれた。 その、紅茶を注ぐ仕草が、真珠色の髪をかきあげる仕草が、凄く女の子らしくてドキドキした。 「そういえばさ、どうしてアルニーは、夜にあんな所にいたわけ?」 「わたしとコフィは、両親から昼にあまり外に出るなと言われていまして、出歩くことが出来る のは、夜だけだったんです。 あの、わたし達、肌に色素が無いものだから、長時間直射日光に当たっていると 肌がやけどしたような状態になるんです。今は日焼け止めの良い物がありますから 自分で塗っていますけど、当時は母が子供2人にいちいち大量の日焼け止めを塗るのが 億劫だったのでしょう」 そこでアルニーは紅茶を一口飲んだ。 右手にカップを持ち、左手にお皿を持つその仕草はまさにお嬢様といった感じだ。 「ああそうだわ、周平さん、わたしも似たようなことを思っていました。どうして、周平さんは あんな夜中にわたしの家の傍にいたのですか?」 「僕は・・・その、実は」 妖精探しの顛末について語った。 「まぁ! うれしいですわ。わたしが白樺の樹の妖精なのですか? ふふっ、光栄です。周平さん」 水岡に比べると大分まともだが、結局、アルニーにまで笑われた。 「そういえばさ」 話の方向性を変えようと、僕は続けた。 「アルニーは、昔はここに住んでいたんだよね?」 「はい」 「学校はどうしてたの? ここは小学校なんて、限られてるし、僕はアルニーを学校で見た 記憶が無いよ?」 「はい、わたし達は学校には行きませんでしたし」 「行ってない?」 「はい。母が言うには、学校では目立つ子はイジメられるということでしたので、両親が計らって、 わたしとコフィは学校には行かず、家庭教師と通信教育で済ませました」 「そうだったんだ、ああ、でもそれなら、木鹿毛高校には転入してくるの?」 「うーん、そうですね。本当は通学したいのですけど、わたし、もう大学課程も修了していま すので」 「へっ?」 今なんて言った? 「大学を修了してる?」 「あ・・・あの、はい。今年の3月に」 「・・・飛び級?」 「そういうことになります」 とりあえず、彼女はとても頭がいいらしい。 時間は、すでに午後の5時を回っていた。 あまり遅くまでここに居るわけには行かない。特にこの辺は街灯の明かりなどもほとんど無い為、 夕方までご厄介になってしまうと、家に帰る途中で辺りが真っ暗ということになりかねない。 だが、僕はなんとなく、ここを離れたくなかった。 いや、なんとなくなどというものではない。僕は、アルニーと一緒に居る時間が一分、一秒でも 長くあって欲しいと感じ始めていた。 彼女のやわらかな、愛らしい声を聞いていたい。 彼女のしなやかな仕草を見ていたい。 彼女に優しく見つめられていたい。 彼女の雪のような白い肌を見ていたい。 彼女の、真珠色の流れるような髪を見ていたい。 なんだか、そんなことばかり考える。 それでも、時間というものは過ぎていく。 僕は思っていたことをアルニーに伝えようと考えた。 「さて、それじゃあそろそろ、僕は帰るよ」 「そう、ですね。そろそろ、時間ですよね」 アルニーは少し寂しそうにした。 「それでだけどさ、アルニー。次はさ、僕がここに遊びに来るのもいいけど、 アルニーがお出かけするっていうのはどうだろう?」 アルニーがハッとした表情で僕を見つめる。 「今度、いつでもいいからさ、町のほうに出かけてみない? アルニーが暮らしていた頃と 比べて随分、この町も変わったからね、案内するよ。町の中、これからアルニーはさ、 ここで暮らしていくんでしょ?うん、僕が案内する」 アルニーの頬が、またも紅潮する。 肌が真っ白のため、本当に分かりやすい。 「はい。周平さん。それでは・・・都合のよい日時が決まったら、お伝えしたいと思いますので。 そうだわ、わたし達、電話番号も伝えていなかったのですね」 2人で、お互いの連絡方法を確かめ合った。 「今日は本当に楽しかったです。周平さん、今度会える時を、楽しみにしてますね」 周平が日月の館から帰って行った数時間後のこと、 コフィが館のキッチンに顔を出した。 「周平は、もう帰ったの?」 もう、外は暗い。日月の家のキッチンにも電気の明かりがともされている。 そこに、お昼に使ったコップやお皿、バスケットを所定の位置にしまうアルニーの姿があった。 「ええ、帰ったわよ? それにしても驚いたわ、あんなにたくさん料理を作ったのに、 全部食べてもらえるなんて」 フフッ、とアルニーが幸せそうに笑う。 なんだか手つきも軽快だ。そんな姉の姿を見て、コフィは少しふてくされた。 「周平は美味しい思いをして、アルニーは楽しい思いをして、損をしたのは、あたしだけ?」 「あら? コフィ、損をしたの?」 「うう・・・キスなんかしなきゃ良かった。まだ、口の中がエグくて、気持ち悪い・・・」 コフィはげんなりしているようだ。 「そんなに?」 「うん、周平とのキスは、もんの凄く、不味くて、えぐくて、気持ち悪い」 「そう」 アルニーはそれを聞いて微笑んだ。そして小さくこう呟いた。 「・・・それは、良かったわ・・・」